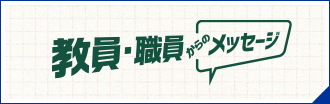千年の都、京都を駆けめぐり、 日本文化の新たな魅力を世界に発信
ゼミ・研究

-
文化学部 4年次
伊坪 哲史さん(写真左端)
-
文化学部 3年次
高峰 志穂さん(写真中央)
-
文化学部 3年次
野脇 創一郎さん(写真右端)
全国初、“京都”を学科名称に冠する[京都文化学科]誕生
京都、大原の古刹「勝林院」は、仏教音楽である「声明」の根本道場として知られ、平安末期には、浄土宗の宗祖法然が諸宗の学僧との宗論に臨んだ「大原問答」が行われた地として名高い。2013年、この寺の開創一千年を機に、京都産業大学が本尊阿弥陀如来坐像の調査を行い、納入仏3体を発見、また史料から同像の変遷の過程を明らかにしました。そんな千二百年の不思議と魅力に満ちた京都を舞台としたフィールドワークを通して、京都文化の特質というべき地域性と国際性を理解し、グローカルな視点を身につけた人材を育成する、全国初の“京都”を冠した学科『京都文化学科』が、2015年4月、京都産業大学に誕生。地域社会・地域文化の発展と創造に取り組み、世界に発信する文化学部が新たにスタートします。
自分の目で見て、手で触れて学ぶ ここでしかできない貴重な経験

小学生の頃から歴史が好きで、日本文化の道に進みたいと思っていました。日本文化コースを選択したのは、せっかく京都の大学で学ぶのだからと思ったから。調査研究では、多くの古文書に実際に触れる機会がありました。博物館に展示されているようなものを、自分の目で見て、さらに手で触れて知ることができることは、大学の学びだからこそできる、今しかできない貴重な経験だと思います。現在は、鬼についての研究をしています。京都大江山の酒呑童子の鬼伝説や、現代の角の生えた鬼のイメージがどうつくられたかについて調べています。もともと姿形のなかった霊的なものが、仏教の羅刹の影響や平安時代の山賊の影響の影響、中世の武士の姿など、さまざまな要因と説が重なって、今のような力強い鬼になったと言われており、時代背景もふまえながら調べています。残りの大学生活では、これまで日本文化を学んできた経験を生かし、海外旅行を通して、外国と日本の文化の違いについて体験していきたいと考えています。
古くこの地であったことを 今もこの地で調べることができる

京都で学び文化財に触れる機会も多くあったことから日本の歴史・文化に興味を持ち、日本文化コースを選択しました。宮崎の出身ですが、京都の大学に進んだのは、鈴木教授の北山殿の記事を見たことがきっかけでした。そして、歴史の古い京都を調べることができることに、大変感激しています。部活では郷土史研究会に所属し、寺院などさまざまな歴史ある場所を訪れています。郷土史研究会では、春と秋に京都市・宇治市・八幡市などの社寺で開催される「非公開文化財特別公開」に向けての調査や、期間中に来訪される拝観者の解説案内をしています。部活やゼミだからこそ見ることのできる場所もあり、そこで一般に広まっていない情報など住職さんから直接話を聞くことは、とても楽しく、貴重な経験です。今は、禅寺に興味を持って研究しています。禅宗の開祖である達磨が最初に日本に伝えましたが、どのように伝わって、その後広まっていったかを中心に調べています。
歴史文化を学ぶことは生活を豊かにする。 ひとつの学びが新たな視点を生む

将来、学芸員になりたいと思い、一番深く学べる日本文化コースを選びました。また、滋賀県の小野妹子の出生地でもある地で育ち、祖母が奈良に住んでいることもあり、昔から日本史に興味を持っていました。学芸員の授業の一環で、勝林院の土蔵整理に参加したとき古文書に触れることができました。そのとき、数百年前のものを実際に触れることができた幸せと同時に不思議な感覚を覚えました。ゼミでは陰陽道について勉強しています。大学で学んだ知識や経験は、新たなモノの見方・考え方になると考えます。すぐに役立つことは多くないかもしれませんが、学ぶ意義があると思います。
勝林院

勝林院は、大原の北東に位置する天台宗の寺院で、長和2年(1013)に寂源によって開基され、天台声明の根本道場としてよく知られています。文治2年(1186)に法然は、勝林院の本堂で諸宗硯学と宗論を戦わせた、いわゆる『大原問答(大原談義)』を行っています。享保21年(1736)に本堂と本尊を焼失しましたが、元文2年(1737)には、現在の阿弥陀如来が開眼供養されました。そして、2013年には勝林院が開基されて一千年を迎えました。

- 文化学部 京都文化学科
※掲載内容は取材当時のものです。