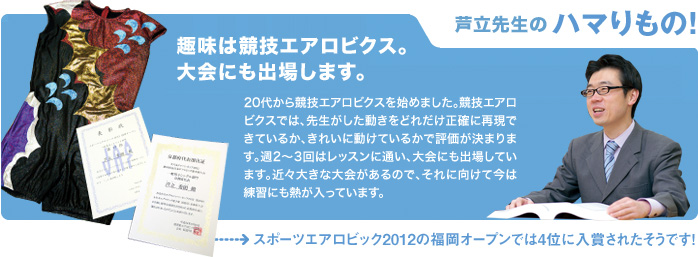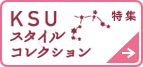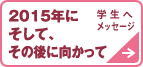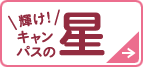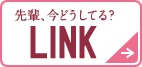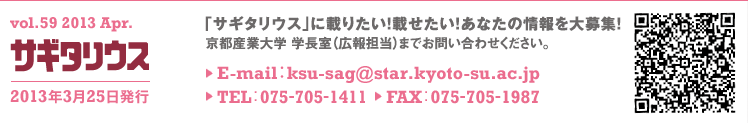- HOME
- キャンパスマガジン「サギタリウス」
- 2013 Apr. Vol.59

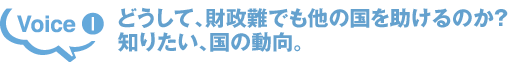
私が主に研究しているのは、 ODA 1 つまり開発途上国への日本政府からの援助についてです。政府が財政難の状態にあっても開発途上国への援助を行うのは何故なのか、大学3年生の時に興味を持った私は、行政学を学び始めました。学ぶうちに、財政難でも必ず出費される福祉などの国内向けの公共政策とODAは、政府にとって同じ位置づけなのではないかという考えに至ったことから、両者の共通点を探ることを長年の研究テーマとしています。現在はそこから派生して、政府の活動へ市民が参加することの意義など、興味の対象は多方面に広がっています。
- 1 解説:
- ちなみに、2012年度のODA予算は5,612億円。
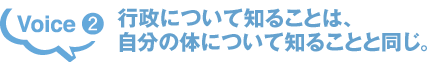
研究者として取り組んでいるのは政治学の分野ですが、大学では特に行政学の講義を担当し、法政策を学ぶ基礎として行政機関の働きや各省庁の関わりなどについて教えています。「行政」というと、堅苦しく、縁遠いものと思う学生もいるかもしれません。私自身は、国の仕組みを知るということは、自分の体のことを知るのと同じくらい身近なことだと思っています。人は暑い夏には汗をかいて体温を下げ、恋をすればオシャレの仕方を勉強するというように、何かの環境変化を受けて、さまざまな方法で自分を良い状態に変えていきます。同じように、国が何かの環境変化に適応するために行うのが 法政策 2 なのです。汗をかく理由を考えるとき、まず体の仕組みを知らなければならないのと同じように、法政策について学ぶ前に、まずは国の仕組みを知ることが第一。行政学の講義ではパスポートの発行など、身近な行政機関の働きから学び、行政がどのように私たちと関わり、社会を形作っているのかを知っていきます。そうして知識を増やすことはもちろん、しっかりとした根拠を元に自分の考えを持てるようになることも、この学びのポイントです。周りの雰囲気に流されて今の政治に批判的になるのではなく、国の仕組みやこれまでの経緯を踏まえた上で、「自分はどう思うのか」が言えるということは、今の社会で生きていく上で、大切なことだと思います。
- 2 解説:
- さらに、災害など大きな環境変化に対して行う施策が、行政改革。
国を変える大きな法政策と言える。
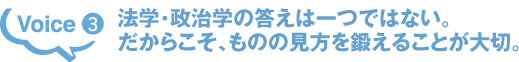
自分の考えに根拠を持つという点から、学生には地道に資料を調べる姿勢を大切にしてほしいと思います。さらに 私のゼミ 3 では、「比較分析」の力を鍛えることにも重点を置いています。研究の根拠を得るために、自然科学の分野では実験を繰り返しますが、「実際に試してみる」ことが難しい法学・政治学の分野では、実験の代わりとして比較分析を行うことが多いのです。さまざまな要因が複雑に絡み合うなかで必要な情報を得るために、適切な比較ができれば研究の質は随分変わります。そして、比較分析の力は、物事の因果関係を見つけ出す力にもなっていきます。例えば企業でのマーケティングなど、役に立つ場面は多いでしょう。知識も物の見方も、法学・政治学の学びはこの国で生きていく上で必ず助けになりますから、学生にはしっかり勉強してほしいですね。何より、せっかく生まれた自分の国の仕組みを知らないなんて、もったいないと思いませんか。
- 3 解説:
- ゼミの学生の研究テーマは、「日本の野球とアメリカのベースボール」
「関東と関西のテレビ番組の違い」など多種多様。