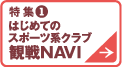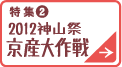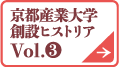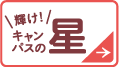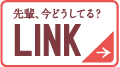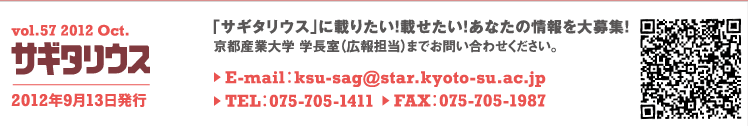- HOME
- キャンパスマガジン「サギタリウス」
- 2012 Oct. Vol.57
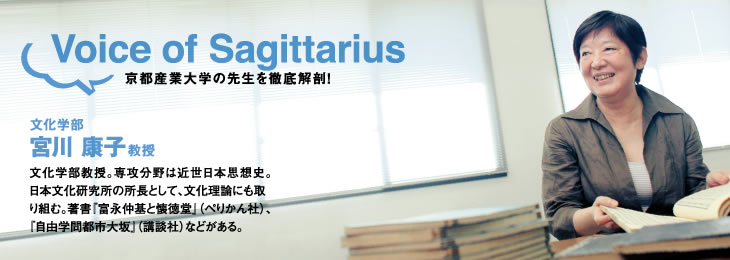
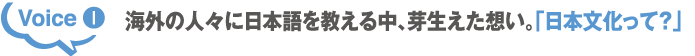
私が日本思想を本格的に学び始めたのは、30代でのことでした。大学生の頃は文学部で戦後の文学について学び、卒業してからは外国の方に日本語を教える職業を中心に、36種類ほどの仕事に携わりました。夫の留学に合わせて1年間はアメリカで生活。さらにベトナム難民センター 1で日本語教師を3年間勤めたこともありました。こうしてさまざまな外国の方と接する中、「私は、日本の文化について充分に知らない」ということに気づかされたと同時に、それぞれの文化には「ものの考え方の基礎」である思想が密接に関わっていると感じたのです。現代の日本文化、そして日本人の考え方がどのように形成されたのかについて次第に興味が募り、大学卒業から10年後、大学院に入って日本思想の歴史 2を学ぶことを決意しました。現代の思想について研究を始め、まず疑問に思ったのは、明治時代以降、日本思想の大部分は西洋哲学によって形作られているという見方が主流だったこと。そこに、興味を抱いた私は、思想の境目となった江戸時代の思想を研究。そして、現代に通じる新しさや見習うべき点をたくさん持つ、江戸時代の町人の思想に夢中になったのです。
1 解説:1975年にベトナムが社会主義に移行した際、
難民になってしまった人々の支援のためにつくられた施設。
難民になってしまった人々の支援のためにつくられた施設。
2 解説:現在、国立大学で日本思想史の講座があるのは3大学だけ。
西洋哲学に比べ、稀少さは歴然。
西洋哲学に比べ、稀少さは歴然。

「女性は家を守るもの」という考え方は江戸時代からの認識だと思いがちですが、その思想が一般的になったのは、明治になって欧米の思想が広まってからということも、日本思想の歴史を学ぶと分かってきます。女性が家にいられるのは武士などの上流階級だけで、町人や農民の家庭では外で働くのは当たり前。ある意味、江戸時代の方が女性の社会進出については自由だった、というようにも言えるのではないでしょうか。
さらに江戸時代では、誰もが学びの機会に恵まれていたわけではないにも関わらず、「自ら学ぶ」質の高い教育が行われていました。江戸時代の寺子屋では、子どもたちはまず読み書きを習いますが、現代の小学校が簡単な文字から習う「難易度順」であるのに対し、日常でよく使う文字から習う「使用頻度順」で学ぶため、例えば「藤」という難しい漢字でもすぐに教わります。読み書きの学習を半年で終えた子どもたちは、「根本的なものの考え方」の学びへ取り組み、それぞれの目的意識に合わせてより高度な学びへと進みます。これこそが町人思想 3の特徴の一つ。恵まれた環境になかったからこその、自分の意志で学ぶ熱意がありました。このように常に上を目指していくハングリーさが、発言力が弱い現代の日本人の力を高めるために、何かの参考になるのではないかというのが私の見解です。しかし、この町人文化についての研究は、その身分の低さからか今まであまり注目されておらず、翻訳されている資料はごくわずか。ほとんどが漢文や崩し字のままで、読まれることなく歴史に埋もれそうになっていま した。私の研究には、歴史に埋もれた声を拾い上げていくという意義があり、また資料の翻訳を通して、優れた知を後世に残す、という大きな使命があると感じています。
さらに江戸時代では、誰もが学びの機会に恵まれていたわけではないにも関わらず、「自ら学ぶ」質の高い教育が行われていました。江戸時代の寺子屋では、子どもたちはまず読み書きを習いますが、現代の小学校が簡単な文字から習う「難易度順」であるのに対し、日常でよく使う文字から習う「使用頻度順」で学ぶため、例えば「藤」という難しい漢字でもすぐに教わります。読み書きの学習を半年で終えた子どもたちは、「根本的なものの考え方」の学びへ取り組み、それぞれの目的意識に合わせてより高度な学びへと進みます。これこそが町人思想 3の特徴の一つ。恵まれた環境になかったからこその、自分の意志で学ぶ熱意がありました。このように常に上を目指していくハングリーさが、発言力が弱い現代の日本人の力を高めるために、何かの参考になるのではないかというのが私の見解です。しかし、この町人文化についての研究は、その身分の低さからか今まであまり注目されておらず、翻訳されている資料はごくわずか。ほとんどが漢文や崩し字のままで、読まれることなく歴史に埋もれそうになっていま した。私の研究には、歴史に埋もれた声を拾い上げていくという意義があり、また資料の翻訳を通して、優れた知を後世に残す、という大きな使命があると感じています。
3 解説:京都の「古義堂」、大阪の「懐徳堂」などの町人学問所で
花開いた思想が、先生の主な研究領域。
花開いた思想が、先生の主な研究領域。
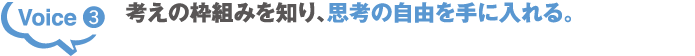
私の講義では、パワフルな町人たちの息吹を感じることで、皆さんに自ら学ぶ楽しさを感じてほしいと考えています。「成績」ばかりが現代の学びの目的になりがちですが、本気で知りたいと思ったことを「分かった!」と感じるときの喜びを実感してほしいですね。そして、たくさんの考え方に触れることで、ものの見方もさまざまに変化するでしょうし、自分の考えについても一つの狭い枠に捕らわれない自由な発想につながるでしょう。それはつまり、本当の意味で自分の考えを持つということであり、変化の激しい今だからこそ求められていることなのです。
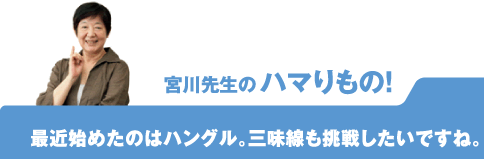
韓国での学会に備えて、ハングルを始めました。勉強のために娘に教えてもらった「宮廷女官チャングムの誓い」は意外にもはまりましたね。友人から譲り受けた三味線に挑戦するのも楽しみです。10歳の区切りごとに新しいことを始めると、次の10年も上向きに過ごせる、というのが私の信念。次は60代に向けて挑戦です。



「自由学問都市 大坂 懐徳堂と日本的理性の誕生」
宮川 康子 著 講談社 ¥1,500+(税)