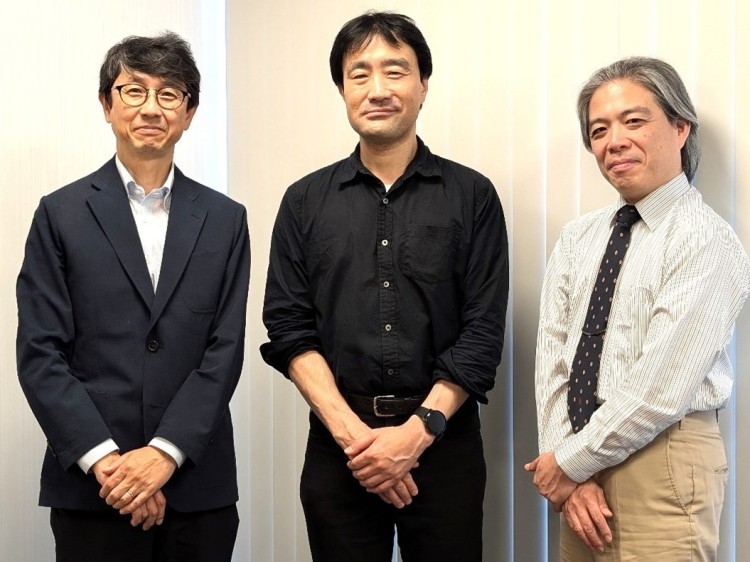【神山天文台】国産反射望遠鏡産業のルーツをさぐる: 大阪市立科学館および(株)西村製作所と共同調査
2024.06.28
京都産業大学 神山天文台は、天文学の研究・開発を行うとともに、博物館法が定める指定施設※1として天文学にかかわる資料の収集、調査、展示を行っています。この度、神山天文台は博物館活動の一環として、大阪市立科学館および天体望遠鏡メーカーの(株)西村製作所(本社、京都)と協働し、国産初の反射望遠鏡の調査を開始しました。
西村製作所は、1926(大正15)年に京都帝国大学(当時)との産学協働によって日本で初めて国産の反射式天体望遠鏡を開発し、販売を開始したという老舗メーカーです。西村製作所は本学と縁が深く、先代社長が本学の1期生であり、また神山天文台の荒木望遠鏡は同社製の反射望遠鏡です。こうした縁から、神山天文台では西村製作所における日本初国産望遠鏡の開発にかかわる資料の調査を続けておりました。そのなかで、神山天文台の青木 優美香 学芸員による調査の結果、大阪市立科学館が所蔵している古い天体望遠鏡が昭和2(1927)年に西村製作所により作られたものであることが判明しました。はっきりと製作年が確定できる市販の国産反射望遠鏡としては、現存する最古のものと考えられます※2。青木学芸員は発見時の気持ちを「資料の図面や写真、文字から得られる情報はもちろん重要ですし、それを探る楽しさもありますが、やはり実物を目の前にすると当時の人たちの気配を色濃く感じて、もっと近づきたくなりました。よく今までのこってくれていたなあと、とても嬉しくなりました。」と語っています。
そこでこの度、神山天文台と大阪市立科学館、西村製作所が協力して、この反射望遠鏡の詳細な技術面での調査を行うことになりました。反射望遠鏡製作技術の変遷を追い、日本における反射望遠鏡産業の黎明期に迫ります。本調査の結果を含め、日本における反射望遠鏡産業の勃興について、来年3月から神山天文台において企画展を開催いたしますので、ぜひ、ご期待ください。
※1 博物館法第31条により、博物館に相当する施設として指定された施設です。学芸員に相当する職員の配置や年間100日以上の開館などの要件を満たしていることが必要です。2024(令和6)年3月現在、京都市内には20館の指定施設があります。
※2 すでに江戸時代には国友一貫斎によって金属鏡を用いた反射望遠鏡が製作されていますが、一般に市販されるものではなく望遠鏡産業としては発展しませんでした。近代的な望遠鏡産業の勃興は、ガラスに銀メッキを施した反射鏡の製作技術が確立した19世紀後半以降になります。日本では1926(大正15)年に、(株)西村製作所が国産初の(鍍銀ガラス鏡を用いた)反射望遠鏡の販売を開始しています。