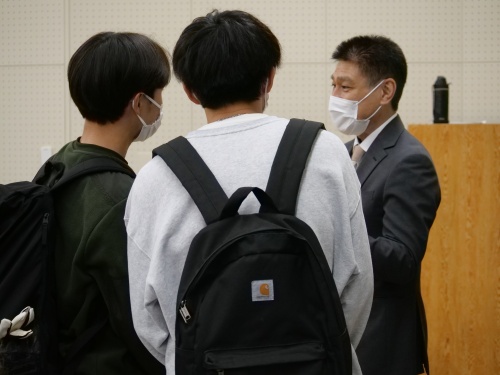【法学部】交通事故の被害者にも加害者にもならないために ー京都府警察元交通機動隊白バイ隊員から学ぶ—
2022.12.01

法学部の専門教育科目「社会安全政策Ⅱ」(担当:田村 正博 教授)のゲストスピーカーとして、京都府警察本部交通企画課交通戦略室の増田 茂 警視をお招きし、交通安全対策についてご自身の交通機動隊白バイ隊員時代の経験談を交えて講義をしていただきました。
増田警視は講義の初めに、交通安全対策は交通安全対策基本法という土台となる法律があり、交通安全対策の基本的な考え方としては「3Eの原則」に基づき対策が行われていると説明されました。
①交通工学(管理)(Engineering)
交通規制、交通安全施設等の整備、道路交通情報の提供等の整備
②交通安全教育・啓発(Education)
交通安全教育(交通安全教育指針:道路交通法第108条の28)
対象別・年齢別交通安全教育の実施、広報・啓発活動
③交通指導取締り(Enforcement)
悪質性、危険性の高い違反に重点を置いた取締り
交通規制、交通安全施設等の整備、道路交通情報の提供等の整備
②交通安全教育・啓発(Education)
交通安全教育(交通安全教育指針:道路交通法第108条の28)
対象別・年齢別交通安全教育の実施、広報・啓発活動
③交通指導取締り(Enforcement)
悪質性、危険性の高い違反に重点を置いた取締り
主に信号機のない横断歩道などにおける歩行者優先の啓蒙活動では、歩行者が自らの安全を守るための行動として、信号機のない横断歩道で手のひらと顔を運転者に向けて、止まった車の運転手とアイコンタクトで渡る意思を伝え、安全を確認してから渡る「合図横断」の実施(2021年9月より)を挙げられ、子ども向けの動画「交通安全サンバ」を紹介されました。
私たちができる取り組みの一つとして、交通事故が増加する薄暮時間(日没前後1時間)対策の「ライトアップ400」を紹介され、午後4時にはライト点灯をするよう呼び掛けられました。車は自車の存在を認めてもらえますし、歩行者等の早期発見にも繋がるほか、歩行者は反射材を身に着けることで車両から認識されやすくなります。
また、2022年4月27日に道路交通法が一部改正され、「全ての自転車利用者に対するヘルメット着用の努力義務」が公布から1年以内に施行されることに触れ、自転車利用時のヘルメット着用を呼びかけられました。
また、2022年4月27日に道路交通法が一部改正され、「全ての自転車利用者に対するヘルメット着用の努力義務」が公布から1年以内に施行されることに触れ、自転車利用時のヘルメット着用を呼びかけられました。
講義の後半では飲酒運転による死亡事故加害者の手記の朗読音源を流され、アルコールの分解には時間がかかり、2日酔いでの運転もしてはならないこと、万一事故を起こしてしまったら一生被害者に対する償いを背負うことになり、同時に社会的、経済的制裁が生まれてしまうと注意喚起をされました。
一口に交通安全対策といっても、取り組みは多岐にわたることが講義を通して学べました。
将来、警察官になることを目標にする学生はもちろん、社会的責任について各々が深く考える機会を得た講義でした。
将来、警察官になることを目標にする学生はもちろん、社会的責任について各々が深く考える機会を得た講義でした。