現場経験をもとに京都府警察本部 交通戦略室長が京都の交通安全政策を語る
2021.11.04
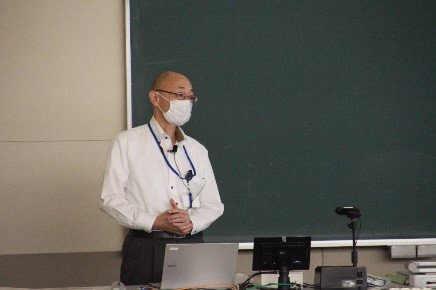
法学部の専門教育科目「社会安全政策Ⅱ」(担当:田村正博教授)の講義にゲストスピーカーとして京都府警察本部 滝清 基(たきすみ はじむ)警視が登壇されました。現在、滝清警視は交通企画課交通戦略室長として、交通対策や交通安全教育といった活動に日々従事されています。今回はご自身の現場経験をふまえて、交通事故の現状と事故防止対策、GIS(地理的情報システム)や街中での取り組みなど、幅広いトピックに関する講義を行われました。
(学生ライター 外国語学部3年次 瀬戸 うた)

まず始めに京都府内の交通事故の現状について話されました。事故による死者数は年々減少しており昨年は過去最少となったものの、年間で約50名の方の尊い命が失われています。また事故は歩行中や道路横断中に発生していることが多く、引き続き社会全体で交通事故防止の意識を高めていく必要があると話されました。
次に京都府内で年間を通じて行う交通対策「交通安全府民運動」について説明されました。この取り組みを行うのは京都府交通対策協議会で、京都府知事や京都市長ら15名で構成されています。交通事故のない安全な社会を目指すことを目的として、行政だけでなく教育関係や鉄道関係などさまざまな機関と協働で取り組んでいます。最重点として、子供や高齢者の交通事故対策や自転車の安全利用の推進が挙げられています。街中で見かけるものとしては、警察やボランティアの啓発活動がありますが、電車内でも交通安全週間に関するアナウンスが行われるなど、多くの機関が関わっていることが分かります。

交通安全対策の基本的な考え方として、交通工学、交通法令の執行、交通安全教育(英語の頭文字をとって3Eの原則)の説明がありました。さらにGIS(Geographic Information System)について紹介されました。これは画面上にその地域で起こった交通事故情報や取り締まり情報、交通安全教育などの情報をリンクさせて地図に表示するもので、次の事故を防ぐために活用されています。私たちもスマートフォンで交通事故情報マップと呼ばれるGISに近いものが利用でき、保護者や教育機関など一般の方でも自分たちに必要な情報が得られるそうです。
続いて悪質な交通違反について説明されました。飲酒運転は年々厳罰化の動きがみられますが、他にも近年問題視されている「あおり運転」について国民の関心が高まっているそうです。
ここでいくつか実際に起こった事故が紹介されました。非常に悪質で凄惨な事件のお話を伺うと、被害者に何の落ち度もないのに事故に遭っていることが分かりました。滝清警視が過去に担当された事故の発生当時の状況や、その後の裁判の判決についても詳しく説明され、加害者の無責任な行動一つで尊い命が奪われることに憤りを感じました。青信号で横断歩道を渡るという絶対的に安全であるはずの状況で事故に巻き込まれてしまった事案に触れ、「歩行者がどこを歩いていても安全な世の中にしたい」と語られました。
ここでいくつか実際に起こった事故が紹介されました。非常に悪質で凄惨な事件のお話を伺うと、被害者に何の落ち度もないのに事故に遭っていることが分かりました。滝清警視が過去に担当された事故の発生当時の状況や、その後の裁判の判決についても詳しく説明され、加害者の無責任な行動一つで尊い命が奪われることに憤りを感じました。青信号で横断歩道を渡るという絶対的に安全であるはずの状況で事故に巻き込まれてしまった事案に触れ、「歩行者がどこを歩いていても安全な世の中にしたい」と語られました。
そして悲惨な事故を繰り返さないための対策として、アルコールを販売する企業と連携して飲酒運転防止のポスターを作成して飲食店に掲載したり、あおり運転防止策の一つとして市バスの車体に注意喚起を載せたりしているそうです。他にも交通安全対策として、歩行者側へのアプローチとして子供向けに「交通安全サンバ」という歌で交通安全への関心を高めて注意を促したり、通学路で保護誘導活動が行われています。コロナ禍で二輪車の需要が増えているため、二輪車販売店における啓発活動や交通安全情報の発信もされているそうです。
さらに京都府警察と大学が連携し、大学ゼミ対抗プロジェクト「ポリス&カレッジ in Kyoto」というゼミの研究テーマに沿ったコンペ式の企画立案発表会を開催しています。本学法学部の高嶌ゼミ生が提案した『立体的に見えるトリックアートを用いた横断歩道』は、2021年8月から実際に亀岡市で実用化されています。
さらに京都府警察と大学が連携し、大学ゼミ対抗プロジェクト「ポリス&カレッジ in Kyoto」というゼミの研究テーマに沿ったコンペ式の企画立案発表会を開催しています。本学法学部の高嶌ゼミ生が提案した『立体的に見えるトリックアートを用いた横断歩道』は、2021年8月から実際に亀岡市で実用化されています。

最後に、交通警察官として忘れてはならないことについて話されました。事故によって人が亡くなるとさまざまなものが生まれます。遺族の方には大切な人を失った悲しみや加害者側への恨みが、加害者には命を奪ってしまった責任や社会的・経済的制裁が発生し、多くの悲劇や惨劇が生まれます。「我々交通警察官は、引き続き京都府内で交通事故をゼロにするために努力していきます」と締めくくられました。
今回の取材を通して現場で活躍しておられる滝清警視の生の声をお聞きすることができて、学生にとって良い刺激になったと同時に新たな気づきもあったかと思います。私たちが日常において安全に暮らすことができるのも、このような見えないところで活動されている方々のおかげだと思いました。
