【現代社会学部】自分の言葉で表現することを恐れないでほしい 元TBSアナウンサー吉川 美代子客員教授がコミュニケーションの重要性を語る
2022.12.27
元TBSアナウンサーの吉川 美代子客員教授が、現代社会学部の専門教育科目「現代社会の諸問題B」に登壇されました。「コミュニケーションとは何か」をテーマに、言葉に気持ちを込める方法や、学生が今すべきことについて話されました。
客員教授として就任された当初から、本学で教鞭を取られるたびに、元アナウンサーらしいハキハキとした声色と豊かな表情で受講生を魅了する吉川教授。当日の講義内容に加え、吉川教授による講義の魅力を学生目線で紹介します!
(学生ライター 外国語学部4年次 福崎 真子)


①吉川 美代子教授 プロフィール
早稲田大学出身。TBS入社後、「JNNニュースコープ」、「JNNニュースの森」、「みのもんたの朝ズバッ!」をはじめ数々の報道番組でキャスターやコメンテーターとして活躍。TBS解説委員やアナウンススクール校長なども歴任。2014年定年退職。2017年4月、京都産業大学 現代社会学部 客員教授に就任。

吉川教授は過去にも「現代社会の諸問題B」や「メディア産業論」など、現代社会学部の科目で登壇し、元アナウンサーとしての体験談を交えながら、受講生に実用性の高い学びを提供されています。過去の講義内容に関する記事は以下からご覧ください。
②当日の講義内容:「自分の言葉で伝える力」は世界を動かす
「コミュニケーションが、今の時代に一番欠けていることだと思います」。
吉川教授は講義の冒頭に、講義テーマを「コミュニケーションとは何か」に設定された理由を説明されました。


「コミュニケーション」とは、相手の心に届く言葉を投げかけ、相手から言葉が返ってきたときは、その意味をしっかり受け止めてあげる「キャッチボール」のこと。投げる言葉(ボール)は「具体的な中身」と「うそ偽りのない素直な気持ち」を込める必要があり、難しい言葉やきれいな敬語は必須ではないそうです。
昨今は、スマートフォン・パソコンの普及と、コロナ禍によるリモートワーク促進に伴い、他者とのコミュニケーションで扱う文字や文章を、スタンプや絵文字などの「簡易的な記号」によって代用する機会が増えています。しかし「それではいけない」と、吉川教授は警鐘を鳴らします。
世界的に有名なスウェーデンの環境活動家 グレタ・トゥンベリ氏を例に挙げ、「彼女は自分の意見をスタンプや絵文字といった記号ではなく『自分の言葉で』世界に発信しています」と紹介し、自分の思いや考えを自分の言葉で表す力が、世界を動かす大きな力になることを力説されました。
最後に、受講生に対し「大学内で友人に会う機会があれば、たくさんコミュニケーションを取ってみてほしいです。思いや考えを自分の言葉で表現することを恐れないでください」とエールを送られました。
③吉川教授による講義の魅力:受講生の心にまっすぐ届く、タマシイ宿る言葉
吉川教授による講義の魅力は何と言っても「思いの込もった話し方」です。

講義中、吉川教授が「自分の素直な気持ちが込もった言葉」の大切さを明確に示すため、自ら演技をして解説される場面がありました。
自分が友人に向かって「映画を見て感動したこと」を話すシーンを想像してみてください。次のうち、どちらが「思いが伝わる話し方」でしょうか。

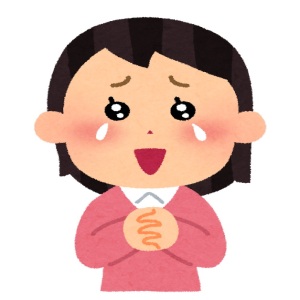
(両手をぶんぶん振る&目をキラキラさせる)
もちろん②の方が、話し手が映画を見たときの情景や感情が相手に伝わります。講義では吉川教授が、②の「思いが伝わる話し方」を実演し「話し方の違いによって、思いが伝わる度合いが変わるんだ」ということを、受講生に身を持って気付かせてくれました。
また、何か重要な事項について説明する際は、神妙な面持ちでゆっくりとハキハキした声で話されたり、逆に楽しい事柄について話す際は、太陽のような笑顔と弾んだ声色で会場を盛り上げようとされたり…。講義は広々とした大教室で行われ、吉川教授と受講生の間にはかなりの距離が空いていましたが、まるで受講生のすぐ目の前に吉川教授が立って話されているかのように、吉川教授の言葉1つ1つが受講生の心の中に届いている様子でした。
「社会に通用するコミュニケーション能力を育成しよう!」と叫ばれる昨今、「結局のところ、コミュニケーションとは何なのか?」という疑問について、専門家の方から具体的な回答が得られる講義だったと感じました。就職活動を目前に控えた受講生もおり、彼らにとって非常に貴重な機会だったのではないでしょうか。
今回の記事は「相手に情景が思い浮かぶような言葉を使いましょう」という吉川教授からの教えを意識しながら執筆してみました。読んでくださった皆さんに、吉川教授の魅力が少しでも具体的に伝わっていればうれしいです。
<関連リンク>
