【国際関係学部】地中海を越える難民たちーチュニジアから チュニジア・スース大学 ハッサン氏から学ぶ
2024.12.27
講師を務めるのはチュニジア・スース大学のハッサン・ブバクリ教授です。ブバクリ教授は地理学を専門とされつつ、歴史や開発など幅広い領域において研究活動を展開されています。また、今回は上智大学外国語学部の岩崎えり奈教授がコメンテーターとして参加されました。
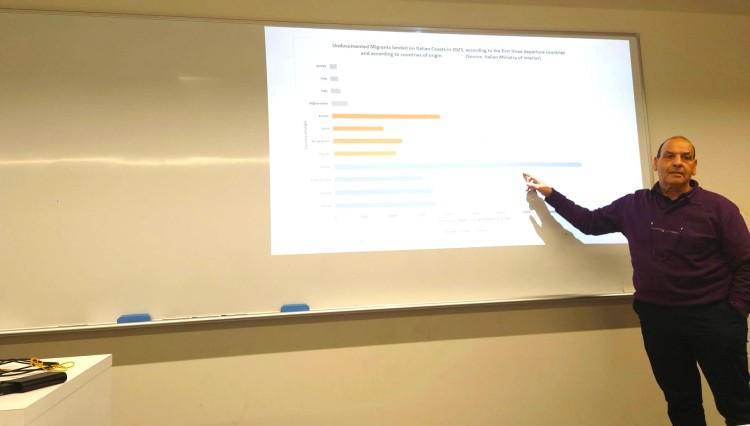
地中海における移民・難民の量的増加
講演では、主にアフリカ側の視点から、地中海移民・難民情勢について解説がなされました。初めに述べられたのはその数で、アラブの春発生の影響が色濃い2011年には、12万9,750人が地中海を越えて非正規に越境したとされます。これが2015年にはピークを迎え、この年には104万6,496人という膨大な数となりました。これはいわゆる「欧州難民危機」として知られる出来事です。COVID-19のパンデミックにより、2020年にはその人数は6万3,236人とピークに比べて少ないものとなりますが、パンデミック後社会の混乱もあり、地中海を超えようとする人々は再び強い増加の傾向にあります。
また解説においては、この人々の移動の原因が主に各地で続く紛争や政情不安にあることが指摘され、そのうち自国を脱して「難民」となっているのは一部であり、実際にはアフリカで移動を迫られる人々の8割がいわゆる「国内避難民」となっていることが補足されました。
“地中海ルート”とマグリブ三国
次に解説されたのは、具体的な移民・難民の移動ルートの詳細です。地中海をジブラルタル海峡からトルコ方面に西部、中部、東部と分けた場合、特に主要な移動ルートとなっているのは中部と東部です。このうち、東部ルートではアフガニスタン難民やシリア難民などの存在により、2010年代初頭より一定数の人の移動が確認されていましたが、中部ルートでは紛争などによる新たなプッシュ要因で、2014年頃から顕著な増加を見せるようになりました。
この中部ルートにおいて難民・移民が海への出発点とするのが、アルジェリア、チュニジア、リビアからなるマグリブ三国です。その中でも特に、チュニジア、リビア沿岸が顕著な出発点となっています。これは、移民・難民がイタリア沿岸を目指すためです。また、マグリブ三国を出発する移民・難民は必ずしもその地の人々ではありません。2023年にチュニジア・リビア沿岸から地中海を渡ってイタリア沿岸へと到着した非正規越境者の内、最も多かったのはサブサハラ諸国を現出発点とする人々です。このように、マグリブ三国は地中海移民・難民の“トランジット国”となっている現状があります。そして、こうした“通過者”はトランジット国でも必ずしも歓迎されておらず、その居住・収容環境の破綻や、当該国での排外的ナショナリズムの高揚など、新たな問題を引き起こしています。加えて、移民・難民の収容に限界を抱える欧州側が閉め出しを強め、またイタリアがチュニジアの関係当局の支援という形で、地中海への出発点であるチュニジアに収容や取締まりを“外注”するといった状況によって、アフリカ側のマグリブ三国に留まる移民・難民の数は増加しており、状況はますます悪化しています。

講演の最後には質疑応答が行われ、質問に対しては、コメンテーターの岩崎教授も議論に参加する形で回答が行われました。前述の2015年の「欧州難民危機」の主要な発生要因は何かという質問に対しては、複合的な要因があることを踏まえつつも、シリア情勢の変動(ロシアをバックアップとしたアサド政権側の反動)が影響している点が示されました。他にも、NATOの介入以降、混乱が続くリビアからの武器拡散についての質問では、リビアで大量に保管されていた武器が、カダフィー体制の崩壊で中東各地の武装勢力に拡散され、難民状況の悪化要因ともなっていることが、より具体的に説明されました。
今回の講演会を踏まえて思われるのが、我々が地中海を越える移民・難民の存在をあくまで欧州からの視点のみで見がちであったという事です。本講演は、この問題が欧州だけのものではなく、実際にはアフリカ・中東の事情と相互に関係しているという事実を強調し、より広い視野での問題意識を芽生えさせるものでした。特に、ガザ情勢やシリアのアサド政権崩壊など、中東情勢の激動が目まぐるしい今日、こうした視野の獲得は、問題分析に非常に有意なものとなるでしょう。
