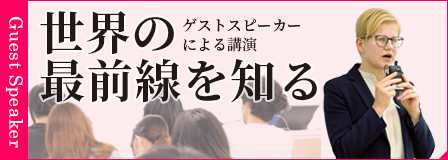【国際関係学部】外務省大臣官房G7広島サミット事務局を招いた講演会が開催され、同サミットが日本ビジネスに与える影響について学びました!
2023.06.27

6月1日(木)国際関係学部の「国際経営論Ⅰ」(担当:植原 行洋教授)の授業の一環として、「G7広島が日本ビジネスに与える影響は」が開催されました。外務省大臣官房G7広島サミット事務局次長補の大岩玲氏にお越しいただき、G7広島サミットと日本ビジネスの関係についてご講演していただきました。
(学生ライター 国際関係学部4年次 佐藤 美宇)
はじめに、7名の学生と大岩氏、植原教授でG7の内容について意見交換が行われました。学生たちは、事前課題としてG7首脳コミュニケを熟読し、合意内容が日本ビジネスに与える影響について考察していました。「脱炭素化」「グリーンエネルギー」「経済安全保障」をキーワードに学生たちの意見が発表されました。

脱炭素化と自動車産業
エシカル消費
学生からは、「エシカル消費を意識する消費者が多くなっている。企業側が消費者の新しい趣向を意識して、環境に配慮した取組をアピールすることがビジネスに好影響を与える」という意見が出ました。大岩氏からは、「G7広島サミットにおいて、日本の脱炭素に貢献する企業の広報ブースを作り世界のメディアにアピールしたことは、一定の成果があった」と現場の声を聞くことができました。植原教授からは、「『環境に優しい』『もったいない精神』をベースとしたエシカルビジネスは日本に古くから存在するもので、日本のイメージを向上させられる契機になるのではないか」という意見でした。
経済安全保障とサプライチェーン

授業の後半は、大岩氏から、外務省の業務内容やG7広島サミットの意義についてお話していただきました。大岩氏は、ご自身の職務を「理想と現実を達成できる仕事」と表現されていました。世界情勢が日々変化する昨今において、日本の平和と安定を確保するための国際関係を作ることが重要視されています。相手の立場に立ち、想像力を働かせて各国と対話を行い、ODAなども有効に活用することで、平和で安定的な国際社会という理想と日本の現実とをマッチさせることが可能となります。G7広島サミットでは、外務省は、サミット全体をコーディネートする役割を担っており、議論の中身はもちろんのこと、食事や宿泊先といったおもてなしの面においても日本らしい産品を使用することで、日本の素晴らしさをアピールすることに成功しました。
サミットでは、国際協調や経済安全保障の確立について、各国首脳による話し合いが行われました。被爆地である広島でのG7サミット開催の意義は、平和推進への強いメッセージ発信に加え、日本の地方や地場企業の魅力も広める意味があったと教えていただきました。また、「経済安全保障環境をより良くするための枠組みは国が主導で作るが、最終的には民間企業がその実現のための役割を担う」と官民連携の重要性を強調されていたことが印象的でした。
最後に、大岩氏から、「地球資源は有限であるため、人類社会を維持させるためには国際協調や引き分けの外交も時には必要である。『持続可能で引き分けの社会の実現」のためには、人に興味を持つ、差異を楽しむ、異文化に放り込まれることを快感に感じることができる人材が必要」と学生に対して期待のメッセージが送られました。
意見交換から始まった講演会は、終始学生が真剣に聴講する姿が印象的でした。国際社会に影響を与えたG7広島サミットに、実際に携わった方のお話は、どれも新鮮で興味深く、非常に有意義な時間でした。

国際関係学部の授業では、外交、ビジネス、国際協力の現場で活躍する実務家を招き、世界の最前線の知識や実情を学びます。
他にもさまざまなゲストスピーカーによる講演会を開催しています!