【国際関係学部】植原ゼミがオンラインでJETRO(独立行政法人 日本貿易振興機構)職員を招き、グローバルサウスにおけるビジネスについて学びました
2023.06.07
国際関係学部の研究演習Ⅰ・Ⅲ(担当:植原教授)で、ゲスト講師による特別ゼミナールが開催されました。ジェトロ・ニューデリー事務所の酒井氏、ジェトロ・ジャカルタ事務所の町井氏、東アジア・アセアン経済研究センター(ERIA)長谷氏をお招きし、現地からオンラインでグローバルサウスの代表格であるインドとインドネシアのビジネス環境やスタートアップ企業の動向、ヘルスケア問題に関してお話を伺いました。
(学生ライター 国際関係学部4年次 渡辺美琴)
インドネシア スタートアップの今!
インドネシアは東京23区に匹敵する人口1,000万人が暮らす都市ジャカルタを有し、ASEAN全体の人口の40%を占める大国です。平均年齢は29歳と若く、インターネットやスマホの普及も高くなっています。また、広い国土や天然資源も後押ししてさらなる経済成長が見込まれていますが、一方で、都市交通や公共サービスはまだまだ未整備で、渋滞やゴミ処理など多くの社会課題を抱えています。
そんなインドネシアでは、既存の業態が手の届かない社会課題に対してビジネスを展開するスタートアップが急成長を遂げています。シンガポールやアメリカ、日本からもインドネシア発のスタートアップへの投資が進められています。
[QR決済のアプリの事例]
背景として、インドネシアには銀行口座を持つことができない低所得者層が人口の約半分いるといわれています。よって、クレジットカードなど既存のキャッシュレス決済システムが普及しにくい環境にあります。そこで、電子マネーで利用できるQR決済のスタートアップが生まれました。国民に馴染み深い露店や屋台でもQR決済が使われています。
また、インドネシアの技術が日本に導入されるケースも現れました。愛媛県伊方町ではスマホやクレジットカードを持っていない、交通の便が悪く銀行窓口が身近に利用できない環境にある高齢者が多いという点に着目し、インドネシアのスタートアップが開発した顔認証で買い物ができるサービスの導入が試みられています。
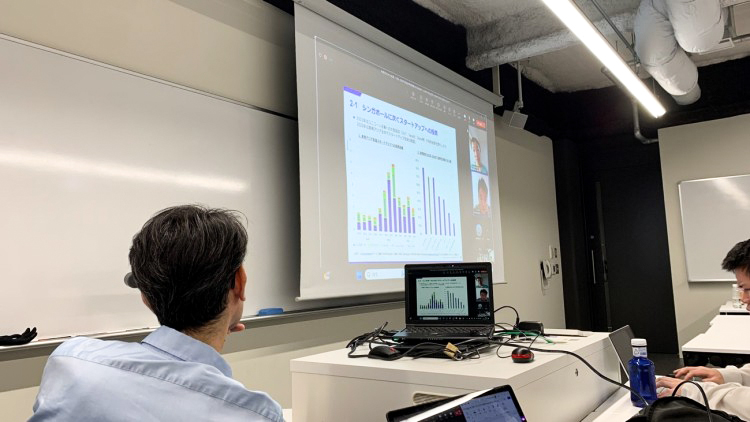
アジアの医療課題と日本はどう関わっていくのか?
私たちが当たり前のように利用している病院(医療、サービス)、医療保険制度は、世界でも珍しいことです。低所得、低学力、などのアジア貧困層は、職の不安定さに加え保健・医療サービスも受けることができません。誰もが保健・医療サービスを受けることができるようになることがアジアの発展途上国の課題とされています。
また、人口が急激に増加したことで、高齢者の数も急速に増加しました。日本は1970年代から高齢化社会に突入していたため、高齢化社会への対応経験が豊富です。今後重要度が増していくアジアの高齢者ヘルスケアに対して日本が貢献できる部分は多いと言えます。
[実際にインドネシアで表彰された日本企業の貢献事例]
日本のオレンジリンクス社は、「爪Qシール」を開発し、インドネシアで展開しています。これは、認知症の高齢者が徘徊をした時に、見つけた人がQRコード読み取り個人を特定できるというもので、爪に貼るだけのローテクノロジーで実施できる特徴があります。

世界が注目!ソフトウェア産業の中心インド
さらに、注目すべきなのがインドの高度人材です。理数系やマネジメントに優れた教育があり、インドの多様性あるバックグラウンドを活かし、グローバルに活躍する人材を育成しています。
インドの成長に伴い、日本企業はインドとの新しい付き合い方が求められる時代になっています。日本企業は小売りや外食分野でインド進出を加速しており、インドを輸出の拠点にし、アフリカなど第3カ国へ進出しようとしています。
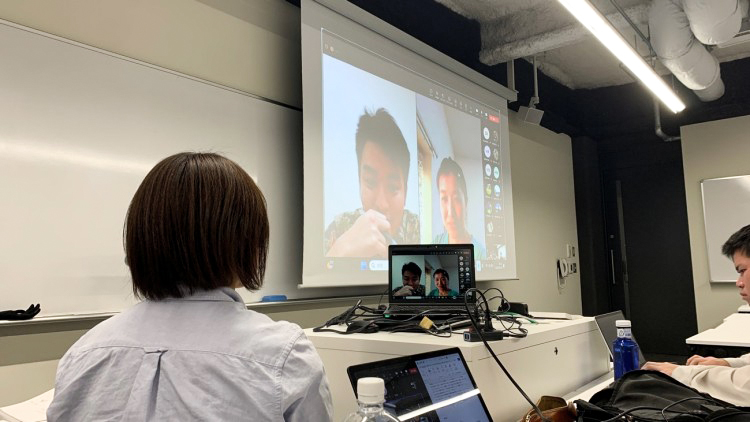
今回、植原ゼミナールでの取材を通して、グローバルな現場で活躍する方々から、リアルな世界の潮流に関して学ぶことができました。そして、学生たち一人一人がこの貴重な機会に向け事前に調査や準備を行い、質疑応答ではゲスト講師の方々に鋭い質問を投げかけており、真剣に国際ビジネスと向き合っている姿勢に感銘を受けました。

