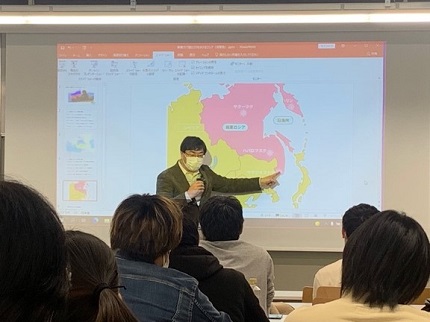国際関係学部 ニュース解説ワークショップを開催 今回のテーマは「経済活動の自由化とは裏腹に政治的な自由を認めないロシアと中国」
2021.11.26

国際関係学部では、教員が専門分野に関するニュースや今話題のトピックスなどを、学生に向けてわかりやすく解説する「国際関係学部教員によるNews解説ワークショップ」が定期的に開催されています。今回は本学部の河原地英武教授が「軍事力で揺さぶりをかけるロシア」について、ノハラ ジュン ジュリアン講師が「中国の戦狼外交とツイッター外交」について解説されました。
(学生ライター 国際関係学部3年次 板坂梨央)
はじめに、河原地教授による解説が行われ、ロシアの国際社会における存在感の変化について説明されました。
ロシアの存在感が薄れていった要因を以下の3つのことを挙げながら解説されました。
1つ目はクリミア半島の併合です。ロシアは2014年3月、ウクライナのクリミア半島を力尽くで併合したことをきっかけにG8から追放され、欧米主要国によって経済制裁を行われました。この断行は、ロシアが主導的な国家という地位からずり落ちた1つの要因といえると解説されました。
2つ目は中国の台頭です。中国は一帯一路政策の中で、かつてはソ連の一部だった地域や中央アジアの国々などを中国の経済圏に取り込んでいき、ロシアは、中国の大構想の中に組み込まれていったと解説されました。
3つ目はロシアの強みである天然資源の国際社会における需要の変化です。石炭や石油・天然ガスなどの化石燃料の輸出がロシアの外貨収入の約半分を占めていましたが、気候変動や地球温暖化問題の深刻化に伴って国際社会のトレンドは化石燃料から離れていくものになっていったと解説されました。国際社会で進む、持続可能な社会に向けた脱化石燃料の動きが、ロシアにとってはマイナスな要素となっていることを初めて知ることができました。
このように世界の新しい流れについていけず埋没してしまっている状態のロシアが、自分たちの存在を示すことができるものが軍事力で、ウクライナに9万人規模のロシア軍を送ったり、北方領土で軍事演習を行ったりと、まさに軍事力を行使して国際社会を揺さぶっていると解説されました。ロシアは国際社会で存在感が薄れているものの、軍事力を行使して、国際社会に脅威を与えることができていることに驚きました。
次に、ノハラ講師によって「中国の戦狼外交とツイッター外交」をテーマに解説が行われました。戦狼外交とは過激な外交官による中国の交戦的な外交手法のことです。特徴の1つとして、外交官らが中国で禁じられているTwitter等のS N Sを活用していることが挙げられます。中国外交部の報道官による新型コロナウイルス発生源の責任転換をする論説のツイートなどをツイッター外交の事例として挙げられました。
そして、戦狼外交の目的を複数観衆問題という概念を用いて分析されました。複数観衆問題とは、心理学から導入された概念で、異なる印象を与えたい観衆が2人以上同時に存在するとき、人はどの観衆に合わせた自己提示を行えば良いのかというジレンマに陥るというもので、同盟国、発展途上国や米国に反抗する国々、中国国民、外交部・政府機関及び共産党の4つの異なる観衆の観点から説明されました。また、戦狼外交は、中国の強い姿勢を見せつけること、新たな国際秩序の提供、核心的利益の防衛などたくさんの目的を持つことが学べました。
これまで国際関係学を学ぶ上で何度も登場し、影響力がある国の1つとしてのイメージが強いロシアの国際社会における存在感が薄れていること、そして私たちにとってとても身近なTwitterが外交において重要なツールとなっていることなど、今回のワークショップを通じてロシアと中国、国土も人口も大きい(多い)国が、国際社会の中で影響力を持つために行っている外交施策を大変興味深く感じました。
今回の2名の教員の解説を聞いて、我々自身も対〇〇という限定的な関係だけでなく、広い視野で動きを捉えて自らの動きを考える必要があると、改めて気づかされたワークショップでした。
ロシアの存在感が薄れていった要因を以下の3つのことを挙げながら解説されました。
1つ目はクリミア半島の併合です。ロシアは2014年3月、ウクライナのクリミア半島を力尽くで併合したことをきっかけにG8から追放され、欧米主要国によって経済制裁を行われました。この断行は、ロシアが主導的な国家という地位からずり落ちた1つの要因といえると解説されました。
2つ目は中国の台頭です。中国は一帯一路政策の中で、かつてはソ連の一部だった地域や中央アジアの国々などを中国の経済圏に取り込んでいき、ロシアは、中国の大構想の中に組み込まれていったと解説されました。
3つ目はロシアの強みである天然資源の国際社会における需要の変化です。石炭や石油・天然ガスなどの化石燃料の輸出がロシアの外貨収入の約半分を占めていましたが、気候変動や地球温暖化問題の深刻化に伴って国際社会のトレンドは化石燃料から離れていくものになっていったと解説されました。国際社会で進む、持続可能な社会に向けた脱化石燃料の動きが、ロシアにとってはマイナスな要素となっていることを初めて知ることができました。
このように世界の新しい流れについていけず埋没してしまっている状態のロシアが、自分たちの存在を示すことができるものが軍事力で、ウクライナに9万人規模のロシア軍を送ったり、北方領土で軍事演習を行ったりと、まさに軍事力を行使して国際社会を揺さぶっていると解説されました。ロシアは国際社会で存在感が薄れているものの、軍事力を行使して、国際社会に脅威を与えることができていることに驚きました。
次に、ノハラ講師によって「中国の戦狼外交とツイッター外交」をテーマに解説が行われました。戦狼外交とは過激な外交官による中国の交戦的な外交手法のことです。特徴の1つとして、外交官らが中国で禁じられているTwitter等のS N Sを活用していることが挙げられます。中国外交部の報道官による新型コロナウイルス発生源の責任転換をする論説のツイートなどをツイッター外交の事例として挙げられました。
そして、戦狼外交の目的を複数観衆問題という概念を用いて分析されました。複数観衆問題とは、心理学から導入された概念で、異なる印象を与えたい観衆が2人以上同時に存在するとき、人はどの観衆に合わせた自己提示を行えば良いのかというジレンマに陥るというもので、同盟国、発展途上国や米国に反抗する国々、中国国民、外交部・政府機関及び共産党の4つの異なる観衆の観点から説明されました。また、戦狼外交は、中国の強い姿勢を見せつけること、新たな国際秩序の提供、核心的利益の防衛などたくさんの目的を持つことが学べました。
これまで国際関係学を学ぶ上で何度も登場し、影響力がある国の1つとしてのイメージが強いロシアの国際社会における存在感が薄れていること、そして私たちにとってとても身近なTwitterが外交において重要なツールとなっていることなど、今回のワークショップを通じてロシアと中国、国土も人口も大きい(多い)国が、国際社会の中で影響力を持つために行っている外交施策を大変興味深く感じました。
今回の2名の教員の解説を聞いて、我々自身も対〇〇という限定的な関係だけでなく、広い視野で動きを捉えて自らの動きを考える必要があると、改めて気づかされたワークショップでした。