【文化学部】「異文化における言語使用」:西シドニー大学からのゲスト講師セミナーを開催しました
2024.10.22
オーストラリアの西シドニー大学で日本語の研究をしているDr. Xiangdong Liu(劉 向東 博士)によるセミナーが、10月17日に小川 知恵ゼミ主催で開催されました。中国出身の劉博士は、北京外国語大学で学士号を取得後、筑波大学で日本研究の修士号を、シドニー大学で日本語学の博士号を取得され、現在はオーストラリアで日本語教育をされている、ユニークな経歴をお持ちです。今回のセミナーでは、外国語教育と言語使用について日本語でお話ししてくださいました。
(文化学部 4年次 櫻井 百華)
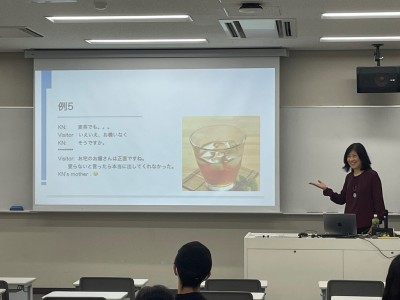
外国語教育と言語使用について、オーストラリアの日本語教育、語用論(ポライトネス)※1、日中韓の比較、文化的・社会的側面の言語使用をトピックに挙げ、劉博士がこれまでに経験された事例を交えて説明してくださいました。英語や日本語を使った何気ない日常会話や、ネットニュースのコメント欄に寄せられるコメントなどを例に挙げ、文法知識と語学力、社会規範・価値観との関連性、言語表現と語用論についての見解を述べられました。特に日本語の敬語・丁寧語について、私たちが無意識に会話の中で普通体と丁寧体とを使い分けていること、時と場合、文脈などによってどのような効果を及ぼしているのか、そして聞き手がその意味を正しく理解することの難しさについてなど、とても興味深いお話をしてくださいました。

セミナー後には参加した学生からのQ&Aの時間もあり、今回お話ししていただいたポライトネスや言語表現についての質問に加え、最近のオーストラリアの学生の様子や劉博士の今後の展望についてなどさまざまな質問が飛び交いました。
セミナー後の感想の一部を紹介します。
- とても興味深い講演でした。ポライトネスを研究するために、ネットのコメント欄や居酒屋での会話を活用するところが面白い視点であると感じました。また敬語は時と場合によってはポライトネスにならず、皮肉・批判の意味になると知り、確かにそうであると感じ、日本語の言い回しについて考えることができました。スピーチレベルのシフトでは普段無意識に使い分けている、アップシフト、ダウンシフトについてそれぞれ得られる効果を意識しながら使い分けていきたいと思いました。
- 正しい文法を使用できることが、言語能力が高いとは言えないとお聞きしてその通りだなと思いました。文化や性格の違いがあるため、正しい文法が使用できたとしても、伝えたいことが必ず相手に伝わるとは限らないということを学びました。
- 劉博士のセミナーを受けて、全ての敬語がポライトネスを表すわけではないことを知り、興味深く感じました。相手が年上でも褒めるときは「素敵」「可愛い」など敬語を使わないなと思い、あえて敬語を使わないこともあることに気付きました。私たちは相手や場面に応じてあまり意識せずに言語の形式を変えており、改めて言語は奥深いと感じました。
- コミュニケーションにおけるポライトネスの関係の深さを実感し、外国語学習においてこれを理解することが重要だと分かりました。
※1:語用論(ポライトネス)
人間関係を円滑にするための言語の使い分け・活用のこと。
