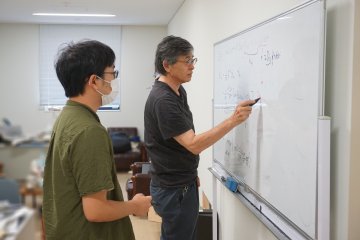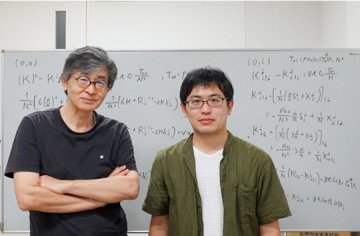京都産業大学理学部 二間瀬敏史教授と大学院理学研究科生がハッブル定数問題(※)を理論的に説明し現在宇宙論の課題を解決!
2021.10.26
京都産業大学理学部の二間瀬 敏史教授(専門:宇宙論)と大学院理学研究科物理学専攻博士前期課程1年次の朝永真法さんは、標準的な宇宙論において仮定されている「一様等方モデル」の妥当性に関する理論的基礎を確立しました。
なお、研究が急速に進む当該理論分野で、大学院生が新しい成果を得て筆頭著者として論文を出版することは非常に珍しいことです。
※ハッブル定数は、遠方の銀河までの距離と後退速度の間のある比例関係における比例定数であり、現在の宇宙の膨張率を示す、宇宙論の基本パラメータである。このハッブル定数が、宇宙マイクロ波背景放射(CMB)の観測から得られる(大域的な)値と、超新星の観測から得られる(局所的な)値とで10%程度の不一致があることを「ハッブル定数問題」と言い、現在の宇宙論における重要問題のひとつである。
論文情報
| 掲載誌 | 日本物理学会学術雑誌 「Progress of Theoretical and Experimental Physics(オンライン版)」 |
|---|---|
| 掲載日 | 2021年9月16日(木)(日本時間) |
| 論文名 | A comment on the averaging in an inhomogeneous cosmology and the Hubble constant problem 『不均一宇宙における平均化とハッブル定数問題に関する一考察』 |
| 著者 | Masanori Tomonaga、 Toshifumi Futamase |
| DOI | https://doi.org/10.1093/ptep/ptab117 |
概要
内容・成果
宇宙論の研究分野では、 ダークエネルギーと呼ばれる未知のエネルギーの存在などさまざまな仮説が提唱され活発な研究が続けられていますが、すべての情報をインプットしてコンピュータで計算するには膨大すぎるため、まずは大胆な仮定の下に宇宙全体の方程式を立てます。
標準的な宇宙論の理論モデルは、宇宙全体がどこでも同じという一様等方の仮定のもとに構築されていますが、現実の宇宙は様々なスケールで物質の濃度に疎密、つまり物質分布の非一様性が存在しており、「一様等方宇宙モデル」は非一様な時空を何らかの意味で平均化して得られるべきものです。そのため、従来平均化によって一様等方宇宙モデルを導くには、ある特定の座標系を仮定されていたため、その結果が仮定した座標に依存するかどうかが問題でした。
本研究では「時空の3+1分解」と呼ばれる方法を用いて従来とは異なる座標系においてアインシュタイン方程式を平均化しても、従来と同じ一様等方宇宙モデルが導かれることを示しました。
この結果によって現在宇宙論でハッブル定数問題として知られる大域的な膨張則と局所的膨張則の違いを、時空の非一様性から説明する理論的基礎を確立しました。
今後の展望
用語解説
アインシュタイン方程式
一様等方宇宙モデル