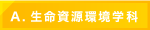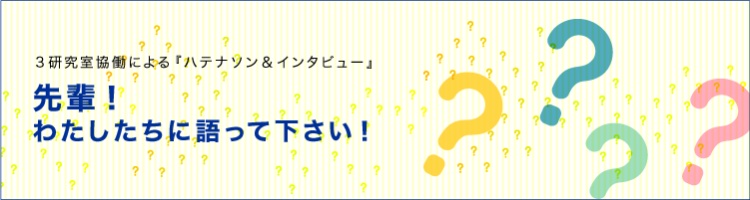
ハテナソン
ハテナソン(hatenathon)は、一人一人の発想を尊重し、かつ民主的な方法のもとで、質問や課題、問題等を発見し言語化する取組みを意味する、ハテナ(?)とマラソンをあわせたオリジナルの造語です※1。人がつどい、お互いに協力しながらなにかを学ぶとき、あるいはつくりあげていくとき、どのように学び、あるいはつくりあげていくのか。このお題に対して、ハテナソン、アイデアソン※2、ハッカソン※3 の順で学び、あるいはつくりあげていく、そうして得られた成果や気づきをもとにして新たな展開へ向けてハテナソン~アイデアソン~ハッカソンをおこなう、この流れを繰り返す、というイメージをもっています。
※1 クリエイティブ・コモンズ・ジャパン登録手続き中 https://creativecommons.jp/

※2 課題や問題に対する解決策やアイデアをつくりだす取組み(アイデア+マラソン)
※3 つくられたアイデアを世界・社会で応用したり実現・実装したりする取組み(ハック+マラソン)
※1 クリエイティブ・コモンズ・ジャパン登録手続き中 https://creativecommons.jp/

※2 課題や問題に対する解決策やアイデアをつくりだす取組み(アイデア+マラソン)
※3 つくられたアイデアを世界・社会で応用したり実現・実装したりする取組み(ハック+マラソン)
ハテナソン&インタビュー
ゼミ・研究室の先輩と後輩とで、むすんで、うみだす。
2016年3月初旬、総合生命科学部3学科の有志教員3名(末尾参照)がつどい、次のことを相談しました。「研究室でいままで頑張ってきた卒業間近の先輩(学部生や大学院生)と、同じ研究室でこれから4年生として研究活動や就職活動、そしてその先にある卒業にむけて頑張りはじめようとしている後輩(当時3年生)とのあいだに、なにかいいむすびつきが生まれる取組みを新たにつくることはできないだろうか?」そして次のことを構想しました。「3年生たちによる、卒業生へのインタビューを実施しよう」そして次のこともあわせて構想しました。「インタビュー項目を3年生たち自身がつくることにしよう」これがすなわち、ハテナソン&インタビュー構想です。
3月7日の夕方、計4つの研究室から3年生が11名集まり質問をつくるワークショップすなわちハテナソンを実施しました。実施時間は休憩時間10分をふくめて全体で約2時間、コーディネータ役の教員の主導のもと、学生たちは質問づくりに取り組みました。このときの質問づくりには、アメリカにある正問研究所(その名のとおり、正しい質問のつくりかたを研究する研究所)が提案しているユニークな方法(日本語翻訳図書:たった一つを変えるだけ、新評論・2015年刊)を使いました。当日にコーディネータが用いた説明資料(パワーポイント資料)、および質問づくりの方法の入手先情報はこちらにあります。
2016年3月初旬、総合生命科学部3学科の有志教員3名(末尾参照)がつどい、次のことを相談しました。「研究室でいままで頑張ってきた卒業間近の先輩(学部生や大学院生)と、同じ研究室でこれから4年生として研究活動や就職活動、そしてその先にある卒業にむけて頑張りはじめようとしている後輩(当時3年生)とのあいだに、なにかいいむすびつきが生まれる取組みを新たにつくることはできないだろうか?」そして次のことを構想しました。「3年生たちによる、卒業生へのインタビューを実施しよう」そして次のこともあわせて構想しました。「インタビュー項目を3年生たち自身がつくることにしよう」これがすなわち、ハテナソン&インタビュー構想です。
3月7日の夕方、計4つの研究室から3年生が11名集まり質問をつくるワークショップすなわちハテナソンを実施しました。実施時間は休憩時間10分をふくめて全体で約2時間、コーディネータ役の教員の主導のもと、学生たちは質問づくりに取り組みました。このときの質問づくりには、アメリカにある正問研究所(その名のとおり、正しい質問のつくりかたを研究する研究所)が提案しているユニークな方法(日本語翻訳図書:たった一つを変えるだけ、新評論・2015年刊)を使いました。当日にコーディネータが用いた説明資料(パワーポイント資料)、および質問づくりの方法の入手先情報はこちらにあります。
ハテナソン&インタビューの成果

期待どおり3年生たちはインタビューの質問項目をつくり、その項目を使ったインタビューを研究室の先輩に対しておこないました。その成果をご覧下さい。
12の共通する質問に対して3名の先輩/卒業生がそれぞれに後輩に対してしっかりと答えています。先輩の回答をもらったあとの3年生たちによる感想もあります。自分たちが4年生となって研究室の中心となって活動するうえで、なにをどのように取り組んでいけばいいのか、そのための貴重なアドバイスや気づきを手に入れることが出来たのではないかと期待しています。廣田さん、桃井さん、西川さん、忙しい3月にインタビューに協力いただき、ありがとうございました。
そしてもう一つ、ハテナソン直後におこなった3年生たちによる「振り返り」の ことばにも注目してください。にも注目してください。わたしたちは、ハテナソンそのものに高い教育効果があるのではないか、ハテナソンがよりよい教育の1アプローチといえるのではないか、ということを考え、大いに期待しています。そこで、この4月から始まった春学期の授業(初年次教育科目、実験科目、講義科目など)や課外学習、あるいは大学の外で(大学コンソーシアム京都FDフォーラム、高大接続授業、出前授業など)、その場に応じた方法によるハテナソンをはじめています(ホームページをはじめとして、ハテナソン情報の発信強化に着手します)。この記事をご覧頂いているみなさんにも、ぜひハテナソンを実施して頂きたいです。
そしてお互いの取組みを共有したり、見学したりしませんか?そしてハテナソンをぜひ一緒にしてみましょう!
12の共通する質問に対して3名の先輩/卒業生がそれぞれに後輩に対してしっかりと答えています。先輩の回答をもらったあとの3年生たちによる感想もあります。自分たちが4年生となって研究室の中心となって活動するうえで、なにをどのように取り組んでいけばいいのか、そのための貴重なアドバイスや気づきを手に入れることが出来たのではないかと期待しています。廣田さん、桃井さん、西川さん、忙しい3月にインタビューに協力いただき、ありがとうございました。
そしてもう一つ、ハテナソン直後におこなった3年生たちによる「振り返り」の ことばにも注目してください。にも注目してください。わたしたちは、ハテナソンそのものに高い教育効果があるのではないか、ハテナソンがよりよい教育の1アプローチといえるのではないか、ということを考え、大いに期待しています。そこで、この4月から始まった春学期の授業(初年次教育科目、実験科目、講義科目など)や課外学習、あるいは大学の外で(大学コンソーシアム京都FDフォーラム、高大接続授業、出前授業など)、その場に応じた方法によるハテナソンをはじめています(ホームページをはじめとして、ハテナソン情報の発信強化に着手します)。この記事をご覧頂いているみなさんにも、ぜひハテナソンを実施して頂きたいです。
そしてお互いの取組みを共有したり、見学したりしませんか?そしてハテナソンをぜひ一緒にしてみましょう!

質問項目
Q1.研究(室)で困ったことがあった時、解決するためにどのようなことをしましたか?(息抜き、やる気がない時など)
Q2.私達3年生は残り1年で何をすべきだと思いますか?
Q3.大学生活を振りかえり最後に言い残したい言葉は何ですか?
Q4.何かやり残したこと、後悔したことはありますか?また、それに対する3年生のアドバイスはありますか?
Q5.4回生1年を通して自分の中の変化(考え方、価値観、性格)はありましたか?
Q6.研究をしていて一番つらかったことは何ですか?
Q7.なぜ総生をえらび、今の研究室をえらんだのか?
Q8.研究室活動で大変だったことは?
Q9.この研究室に入ってよかったですか?
Q10.卒業研究において一番しんどかったことは何ですか?また、それをどのように乗りこえましたか?
Q11.うちの学科にいたことで就活or院試で有利に働いたことは何かありますか?
Q12.自分の研究室の強みは何ですか?
ハテナソンを振り返って
生命システム学科 佐藤 賢一研究室

卒業生:西川 裕貴さん
京都府立南陽高等学校(博士前期課程卒→就職)
在学生:4年生(インタビュー当時3年生)
- 小川 佳祐さん(私立京都学園高等学校)
- 小寺 辰弥さん(滋賀県立大津高等学校)
- 堀江 智裕さん(私立徳島文理高等学校)
- 松本 祐汰さん(京都府立鳥羽高等学校)
生命資源環境学科 木村 成介研究室

卒業生:桃井 理沙さん
大阪府立阪南高等学校(学部卒→大学院進学)
在学生:4年生(インタビュー当時3年生)
- 末廣 篤史さん(兵庫県立西脇高等学校)
- 初田 健さん(私立奈良大学付属高等学校)
- 山脇 由裕さん(滋賀県立甲西高等学校)
- 釘貫 晃弘さん(兵庫県立西宮今津高等学校)
動物生命医科学科 加藤 啓子研究室

卒業生:廣田 暖奈さん
東海大学附属仰星高等学校(博士前期課程卒→就職)
在学生:4年生(インタビュー当時3年生)
- 奥野 貴哉さん(兵庫県立加古川西高等学校)
- 青木 仁星さん(熊本県立鹿本高等学校)
- 太田 真菜美さん(大阪府立牧野高等学校)
- 中山 泰伸さん(大阪府立市岡高等学校)
- 窪田 裕樹さん:西野研究室(滋賀県立守山高等学校)
所感
生命システム学科 佐藤 賢一教授
よく学ぶためには、よく質問することが大事です。そしてよく質問するためにはどうすればいいのかを考え、実践することも。質問づくりに集まった3年生たち(当時)がつくっていた場は、この気づきに満ちていました。
生命資源環境学科 木村 成介教授
4年生の先輩が大学生活で学んだことや卒業研究で苦労したことを実際に聞いてみることで、質問している側の3年生たちの意識が変わったとように感じます。これまで以上に積極的に卒業研究や就職活動に取り組むようになりました。
動物生命医科学科 加藤 啓子教授
研究室活動について、修士課程2年の廣田さんに様々な角度から質問し、話を聞き、お話しをする機会を得ました。その結果、その後の5人の行動や研究への取り組みが、これまでにも増して前向きになり活発になりました。現在、うち4名は大学院進学を目指しています。