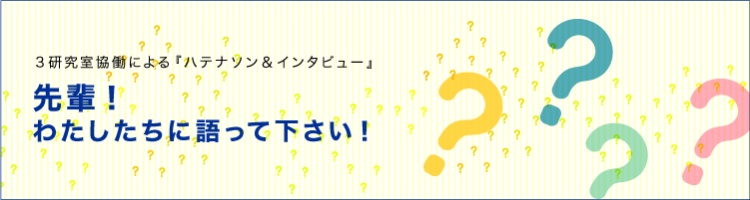
生命資源環境学科 回答一覧
Q1.研究(室)で困ったことがあった時、解決するためにどのようなことをしましたか?(息抜き、やる気がない時など)
A1.
私はよくいろんな人とコミュニケーションを取ることを意識していました。特に私は研究室にいる時に同期の人とは実験について話すことで実験に対するストレスを緩和しました。逆に誰も話さずに実験だけするとふさぎ込んでしまいモチベーションが下がるので気を付けてください。
インタビュワーのコメント
研究室内でのコミニケーションは精神面で必要と気づかされたので積極的にコミニケーションをとっていきたい。
Q2.私達3年生は残り1年で何をすべきだと思いますか?
A2.
まずゆとりのある計画を建てください。実験において失敗がたくさんあるので失敗を考慮して且つ実験過程を逆算した計画を建ててみてください。また大学にいる時間は限られているので友達としっかり遊んで思い出をたくさん作ってくださいね。
インタビュワーのコメント
先輩の体験談は自分を見つめ直すとても貴重な話なので今後に生かせるようにしたい。
Q3.大学生活を振りかえり最後に言い残したい言葉は何ですか?
A3.
この大学に入学して良かったと思います。やり残したことがありましたが大学生活はとても楽しく非常に満足しています。
インタビュワーのコメント
あと1年を通して満足した大学生活を送っていきたいと感じた。
Q4.何かやり残したこと、後悔したことはありますか?また、それに対する3年生へのアドバイスはありますか?
A4.
大学在学中に同じ学年や地元の友達と遊ぶことです。4年生になると就活の影響で気を使って遊びに誘えなかったことに後悔しています。だから3年生達には就活中でも食事を誘って会話する機会を作ると双方に良い影響を与えられると思います。
インタビュワーのコメント
就活であまり誘う機会がないのでなくそれを理由にして誘って無いと気づかされたので積極的に誘っていきたい。
Q5.4回生1年を通して自分の中の変化(考え方、価値観、性格)はありましたか?
A5.
4年生では自主性と計画性の考え方が変化したと思います。自主性では自分から先生や先輩に論文などの添削や、実験の相談を持ちかける様になりました。
また計画性では成功前提で研究計画を建てていましたが、実験の失敗を経験してからは実験が失敗しても対処できる様にゆとりを持てる計画を建てることができました。
また計画性では成功前提で研究計画を建てていましたが、実験の失敗を経験してからは実験が失敗しても対処できる様にゆとりを持てる計画を建てることができました。
インタビュワーのコメント
4年生が最も研究に勤しむ機会なのでしっかり研究活動を励んでいきたい。
Q6.研究をしていて一番つらかったことは何ですか?
A6.
実験に使用する植物体がうまく育成できていなかったことです。植物体が使えないと実験の計画が支障をきたしてしまうので枯れているととても落ち込みました。
インタビュワーのコメント
植物がうまく育たないことがよくあったので強く共感した。植物の栽培は気を付けていきたい。
Q7.なぜ総生をえらび、今の研究室をえらんだのか?
A7.
高校生の頃から生物の授業に興味持っていたので総合生命科学部に進学したいと思っていました。オープンキャンパスの説明から生命資源環境学科には解剖の授業がないと知ったので、解剖が苦手な私はこの学科が適任だと感じて選びました。また、授業で植物ホルモンによる植物の形態変化に興味を持ち、木村先生が同じ研究テーマを持っていると知りこの研究室を選びました。
インタビュワーのコメント
自分はオープンキャンパスで生命資源学科に興味を持ったので彼女の志望理由と違っていたのが驚きを隠せ無かったし、授業での教授の指導態度で研究室を選択したので研究室を選ぶ理由は多種多様だと思わされた。
Q9.この研究室に入ってよかったですか?
A9.
木村研究室に入ってよかったと強く思います。研究室のメンバーは研究に対する意識が高いことに刺激され私も研究に対して真摯に打ち込めたことに満足しています。
インタビュワーのコメント
自分も研究室の人たちの研究する姿でモチベーションを上げているので、これからも次の後輩の模範になるように研究を励んでいきたい。
Q10.卒業研究において一番しんどかったことは何ですか?また、それをどのように乗りこえましたか?
A10.
論文の添削してもらった際に訂正箇所が多数あったのを見て自分の文章力が無いと痛感したことです。その為私は科学に関する書籍や自分の研究に関する論文を読むことで自分の語彙力や専門知識を鍛えることでこの問題を解決できました。
インタビュワーのコメント
本を読む必要性を感じたので論文を読む際にはただ読むのではなく完全に理解して読んでいきたい。
Q11.うちの学科にいたことで就活or院試で有利に働いたことは何かありますか?
A11.
院試では自分の実験に対する知識が役に立ち解答が楽になりました。ゼミでスライドを使用して論文発表や卒論の発表をしたので就活では聞き手に分かりやすいプレゼンテーションができるようなると思います。
インタビュワーのコメント
ゼミの発表でプレゼン能力を鍛えられているので発表機会を大切にして就活や大学院試験を生かしていきたい。
Q 12.自分の研究室の強みは何ですか?
A12.
当研究室にはポスドクなど学生以外の研究生が多く所属していることです。また私たち学生を学生ではなく一研究者として扱ってくれるのでとても参考になる意見をくれる機会がたくさんありました。
インタビュワーのコメント
研究室にたくさん人がいることがいかに恵まれているか感じられた。今後もわからないことがあれば頼っていきたい。
全体を通しての感想
インタビューを終えて、これからためになることが多くあり、聞けて良かったと思いました。院に行かれる桃井さんにインタビューをしました。実験の進め方や遊びと研究のバランスなどを学びました。その中でも印象に残っていることは、実験は失敗した時のことまで考えておくこと、もっと遊べばと思っていることの2点です。実験はほとんどが失敗であるため、その時のために第2の矢や対策をしているとお伺いしました。実験を効率よく進める上で大切であると思いました。また、「後悔していることは、3回生は今何をしたらいいか」という質問で、桃井さんは「遊べばよかったかな」とおっしゃっていました。実験もっとこうすればよかったなどと答えられるかなと思っていたため、意外に感じました。このことから人生の中で大学生活では遊び私生活、交友関係も充実させないと後悔してしまうと感じました。
今私は就活していますが研究室のことを聞かれると、桃井さんから聞いたことを参考にして面接官に答えています。「この研究室は学生をいち研究者として接し、レベルの高いことができる」とおっしゃっていて、私もそう思い、そしてそれは自分のやりがいや挑戦、誇りとなると思いました。桃井さんのように研究も卒論発表も良いものにしたいです。
今回は聞けなかったことですが、個人的には就活と研究について、聞きたいと思いました。就活も実験も頑張りたいです。
今私は就活していますが研究室のことを聞かれると、桃井さんから聞いたことを参考にして面接官に答えています。「この研究室は学生をいち研究者として接し、レベルの高いことができる」とおっしゃっていて、私もそう思い、そしてそれは自分のやりがいや挑戦、誇りとなると思いました。桃井さんのように研究も卒論発表も良いものにしたいです。
今回は聞けなかったことですが、個人的には就活と研究について、聞きたいと思いました。就活も実験も頑張りたいです。
