MOC vol.16「環境との向き合い方~プレシャスプラスチックの取り組み、事例から考える~」開催報告
2025.03.03
京都市上京区の西陣地区にある学外拠点「町家 学びテラス・西陣」では、大学生から社会人まで幅広い世代がともに学び、地域とつながり、地域との関わりを通して多様な生き方や暮らし方、働き方の選択肢を増やすことを目的とした学びの場「町家オープンカレッジ(略:MOC)」を定期的に開催しています。
第16回目のMOCは、廃棄物を「ゴミ」でなく「素材」と定義し直し、アップサイクリングへの参加を身近な選択肢にする活動を展開されているPlaRialの代表 松本 恵里佳氏をゲストにお迎えして開催しました。

当日は、まず松本氏からの「皆さんが関心ある環境問題は?分野は?」という問いかけに、海洋ゴミ、森林、温暖化、公害…それぞれの答えを聞きながら、いろいろな環境問題や分野がある中でどこに向かうかを考える必要がありますね、というお話から始まりました。
そんな松本氏は学生時代、絶滅危惧種の問題に向き合ったことで、人間の手によって生物多様性が壊れてしまっている現状を知り、実際にその現場を見たいという想いからベトナムやメキシコ、南アフリカ、インドネシアなどの現地に出向いて、ウミガメの卵の保護活動やアフリカゾウの見回りのための道路整備、川や山に散乱したゴミの処理などのボランティアをされました。その後、環境教育に注力したいと考え、JICA海外協力隊に参加されました。
当初、海がある国を希望されたとのことでしたが、配属先は南米のボリビア。そこで見たのは綺麗な海ではなく、ゴミの海…そこは市の最終処分場で、ゴミの分別や処理がしっかりできておらず、家畜である豚や牛、動物達がゴミの上を行き来し、育てられ、生きているという現状。
そんな松本氏は学生時代、絶滅危惧種の問題に向き合ったことで、人間の手によって生物多様性が壊れてしまっている現状を知り、実際にその現場を見たいという想いからベトナムやメキシコ、南アフリカ、インドネシアなどの現地に出向いて、ウミガメの卵の保護活動やアフリカゾウの見回りのための道路整備、川や山に散乱したゴミの処理などのボランティアをされました。その後、環境教育に注力したいと考え、JICA海外協力隊に参加されました。
当初、海がある国を希望されたとのことでしたが、配属先は南米のボリビア。そこで見たのは綺麗な海ではなく、ゴミの海…そこは市の最終処分場で、ゴミの分別や処理がしっかりできておらず、家畜である豚や牛、動物達がゴミの上を行き来し、育てられ、生きているという現状。


その解決方法の1つとして出会ったのが、コミュニティ単位で「自分たちの出したゴミ」のリサイクルを可能にするオランダ発のオープンソースプロジェクト「PRECIOUS PLASTIC」でした。それを本来は現地で立ち上げたかったのですが、京都で立ち上げることになったのは偶然だったそうです。
現在、京都では「環境教育」「PRECIOUS PLASTIC」「地域連携」を組み合わせ、より良い選択を誰もができる世の中を目指して、学校や自治体でのワークショップやプログラムの実施、若者を対象とした展示や物販をされています。
本学の情報理工学部においても以前、トークセッションやワークショップを実施されました。
【情報理工学部】PRECIOUS PLASTIC KYOTOイベントDay1
【情報理工学部】PRECIOUS PLASTIC KYOTOイベントDay2
トークの最後にはアップサイクルの事例をいくつかご紹介いただき、その事例の1つとして松本氏も事業に参画されている株式会社colourloopの代表 内丸氏にもご登壇いただきました。大学で繊維リサイクルの研究をされ、廃棄繊維を色で分ける「カラーリサイクルシステム」を用いてできた素材から新しい商品づくりをされており、持参されたサンプルや素材には参加者の方々も興味を惹かれている様子でした。
現在、京都では「環境教育」「PRECIOUS PLASTIC」「地域連携」を組み合わせ、より良い選択を誰もができる世の中を目指して、学校や自治体でのワークショップやプログラムの実施、若者を対象とした展示や物販をされています。
本学の情報理工学部においても以前、トークセッションやワークショップを実施されました。
【情報理工学部】PRECIOUS PLASTIC KYOTOイベントDay1
【情報理工学部】PRECIOUS PLASTIC KYOTOイベントDay2
トークの最後にはアップサイクルの事例をいくつかご紹介いただき、その事例の1つとして松本氏も事業に参画されている株式会社colourloopの代表 内丸氏にもご登壇いただきました。大学で繊維リサイクルの研究をされ、廃棄繊維を色で分ける「カラーリサイクルシステム」を用いてできた素材から新しい商品づくりをされており、持参されたサンプルや素材には参加者の方々も興味を惹かれている様子でした。
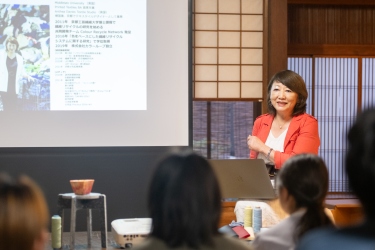

その後のトークセッションには内丸氏にも加わっていただき、お二人に日本と海外の違いや取り組みをしていく中での課題についてお聞きしました。
海外よりも日本の方が環境問題への意識が高く取り組みが進んでいること、それでもジェネレーションギャップや理解が進んでいないところがあること、今後さらに多くの人に知ってもらって仲間づくりやその価値を伝えていく必要性があることなどのお話をされました。
最後には、参加者同士でグループになって感想共有をして発表。発表では身近なところから環境問題に向けた動きをしてみる、興味を持ってみる、情報が集まる場所が欲しいなどの声がありました。
今後、町家でも継続的にできることを考え、向き合っていけたらと思います。
海外よりも日本の方が環境問題への意識が高く取り組みが進んでいること、それでもジェネレーションギャップや理解が進んでいないところがあること、今後さらに多くの人に知ってもらって仲間づくりやその価値を伝えていく必要性があることなどのお話をされました。
最後には、参加者同士でグループになって感想共有をして発表。発表では身近なところから環境問題に向けた動きをしてみる、興味を持ってみる、情報が集まる場所が欲しいなどの声がありました。
今後、町家でも継続的にできることを考え、向き合っていけたらと思います。


当日ご参加いただいた皆さん、ありがとうございました。
