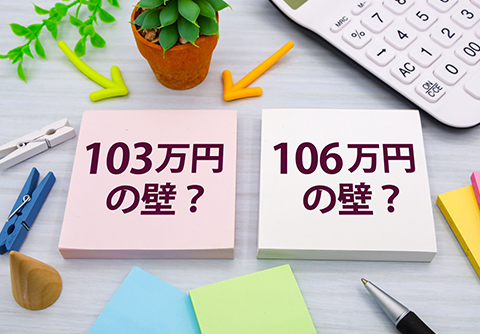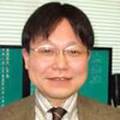「年収の壁」の争点化にみる日本社会: 中流意識とリベラリズム 2025.05.08
「103万円の壁」の引き上げ
2024年10月の衆議院議員選挙後、いわゆる「年収の壁」、とりわけ「103万円の壁」が関心を集めました。基礎控除48万円と、給与所得控除のうち低所得者(給与収入[以下では年収]162.5万円まで)を対象とした最低保障額55万円の合計は103万円であり、この額までの年収には所得税がかからないという仕組みです(住民税に関しては省略)。103万円ラインの引き上げを公約に掲げた国民民主党が議席を大きく伸ばしたことで、2025・26年度の基礎控除額は、合計所得金額2350万円以下(収入が年収のみのときは年収2545万円以下)の場合、その所得(年収)に応じて95万円から58万円の間に引き上げられました。また、給与所得控除の最低保障額(年収190万円まで)は65万円になりました。これにより103万円ラインは160万円になりました(年収160万円までは所得税がかからない)。
「壁」の意味
控除の増額は対象者すべてにとって恩恵ですが、特定の控除額が働き控えの壁になるかどうかは人によって異なります。例えば、多くの単身低所得者にとって、これは壁になりません。100万円程度の年収で働くことをやめるのはそもそも難しく、壁を乗り越えて働かざるを得ません。それによって課税所得が発生しても、その額に一定の税率を掛けた所得税を納めますので、課税所得から所得税を引いた後の金額は働くほど増えていきます(年収増加に伴う給与所得控除額算出式や適用税率の変更によって非連続的に生じる差額はうまく調整されています)。社会保険料負担が生じる106万円や130万円の壁というのもありますが、こうした状況にある単身者は、そこで労働を控えるよりもむしろさらに労働を増やすことで、収入と将来の年金を増やしていこうとするはずです。
これに対して、この仕組みが壁となってしまうのは複数人で構成される世帯であり、典型的には扶養者のほかに大学生や主夫(婦)がいる家族です。例えば、主婦(夫)の中には、103万円を超えることでわずかでも所得税を払うことに心理的に抵抗を感じる人もいるでしょう。また単身者とは異なり、106万円や130万円の社会保険料負担ラインも、将来の年金が増えると分かっていても、わずかに超えた時点では手取りが減るため、壁と感じる被扶養配偶者も多いでしょう。さらに扶養者の中には勤務先から103万円を基準として配偶者手当や家族手当を支給されている人もいます。
加えて、壁越えによって他の控除が受けられなくなり、扶養者の手取りが減ってしまう可能性があります。大学生(19歳以上23歳未満)のアルバイト年収が103万円を超えると、扶養者は特定扶養控除を受けられず課税所得が上がるため、手取りが減る可能性があります。さらに、配偶者の年収が150万円を超えると(2018年度以降は103万円ではなく150万円の壁)、配偶者特別控除は段階的に下がっていくため(201.6万円で控除なし)、扶養者の手取りは減るかもしれません。
選挙結果を受けた2025年度税制改正では、これら2つの控除に対する被扶養者の年収額も、それぞれ150万円(123万円超は特定親族特別控除)と160万円に引き上げられました。子(19歳以上23歳未満)に関しても配偶者と同様に、年収上限(150万円)で直ちに控除をなくすのではなく、188万円まで段階的に控除額の減額が行われる仕組みが作られました。(税制はさらに複雑ですが、ここでは大枠を記述しています。)
中流意識層の覚醒
このことから分かるように、壁の引き上げを前面に出した国民民主党の公約は、控除額引き上げの恩恵を受けるすべての人々の中でも、かつての日本社会でよく言われた「中流」家庭と自己認識している人々、さらには将来こうした家庭を築くことを期待している人々に、特にアピールするものでした。実際、私のゼミの学生に「103万円の壁に関心はありますか」と唐突に聞いてみたところ、複数の学生が「あります」と声を出して即座に手を挙げました。普段、政治的主張を語ることはあまりないイマドキの学生たちが、これほどはっきり意思表示したことでも、この公約のインパクトが分かります。
2024年選挙時の国民民主党と立憲民主党の政策パンフレットに示された経済公約を比較すると、前者が後者と異なり中流意識層をターゲットにしていたことがよく分かります(選挙公約の細目は概して総花的ですが、パンフレットの要点ページに政党の力点が表れます)。国民民主党は「手取りを増やす」をスローガンにして、「年収の壁対策」「年少扶養控除復活」「社会保険料軽減」などをキーワードに主張を展開しました。これに対して、立憲民主党は「分厚い中間層の復活」を掲げ、「最低賃金引上げ」「リスキリング」「正規雇用への転換」といった主張を前面に出していました。前者が中流意識層の存在を前提にそうした人々に訴えたのに対して、後者はその階層の再生を訴えるものでした。
この違いは、小選挙区よりも候補者個人の顔が見えにくく、政党が掲げる政策がより強く投票行動に影響を与える比例代表で明白に現れました。立憲民主党の比例代表議席増加が、前回選挙の39から44議席に過ぎなかったのに対して、国民民主党は5から17議席へと大きく伸ばしました。しかも同党の勢いは、名簿登載候補者が不足し3人分を他党に譲ってしまうほどでした。選挙前には立憲民主党に大差をつけられていた国民民主党の支持率は、選挙後に国民民主党を詳しく知った人々も加わって、立憲民主党を逆転しました(2025年4月の世論調査[日経・朝日・毎日・読売]で国民12-15%、立憲6-10%)。こうして「失われた30年」の間に忘れられかけていた中流意識層は、再び覚醒することになりました。
「失われた30年」の世相
上のような立憲民主党の経済公約は、「失われた30年」という時代を象徴しています。時代背景の中での中流意識層に対する関心低下は、「国民政党」を長年自負してきた自民党も例外ではありませんでした。この時期の同党の政策は、中流意識層に向けたものから次第に困窮対策という性格を強めていきます。1998年の橋本政権は山一證券破綻などの金融不安に対する景気対策として所得税と住民税の定額減税を実施し、続く1999年の小渕政権はこれら税の定「率」減税を実施しました。この定率減税は2007年まで続いていきます。これに対してリーマン・ショック以降、大規模な給付金政策が代わって目立ち始めます。2008-9年の麻生政権は、所得税を納めていない人々にも恩恵が行き渡るように減税ではなく住民基本台帳及び外国人登録原票にあるすべての人に定額給付金を実施しました。そうした政策とは対極のイメージがある安倍政権においても、2020年には紆余曲折を経て、コロナウィルス・パンデミック下という特殊な状況とはいえ、住民基本台帳に記録されているすべての人(外国人住民を含む)に対して特別定額給付金を最終的には決定しました。
経済的に困窮している人にとっては、減税よりも目先の現金確保が切実な問題です。また、定額の給付金であれば低所得者ほど所得に占める割合は大きくなるため、そうした人ほど、その価値は高まります。減税から大規模な現金給付へのシフトは、「失われた30年」を映し出す政策変化でした。
所得税・住民税減税(住民税の均等割分を除く)は個人の活動の結果に対する共同体の反応(個人が得た所得に対する減税措置の実施)であるのに対して、給付金は個人の活動とは無関係に共同体が一方的に実施する措置です。前者では個人が共同体に先立っているのに対して、後者では個人は共同体に対して受け身です。特に収入・所得制限がない給付金は、自律可能な個人に対しても共同体が関与して恩恵を施そうとする点で、個人に対する共同体の優位をより強く体現する措置です。「失われた何年」と特徴づけられ意気消沈した日本社会では、政治だけではなく、社会のメンタリティにおいても同様のシフトが起こります。この時期、バブル経済期までにみられたような、中流意識層に象徴される元気で自律した個人や家族がけん引する社会像よりも、無力な個人と家庭に対する共同体の優位と社会共助を重視する思想がもてはやされるようになっていきます。
特にリーマン・ショックとコロナウィルス・パンデミックという困難な時期には2つの共同体(コミュニティ)主義が関心を集めました。ひとつは1980年代にアメリカで隆盛したコミュニタリアニズムであり、四半世紀も経ったリーマン・ショック後に、その代表的論者であるマイケル・サンデルが日本のテレビにたびたび登場するようになりました。もうひとつは、斎藤幸平などによって現代版に焼き直されたカール・マルクスのコミュニズムであり、コロナウィルス・パンデミックの中で話題になりました。
こうして「失われた30年」では、政治経済社会全体において個人よりも共同体に重きを置く雰囲気が幅広く醸成されていきました。
日本における個人と社会
2つの共同体主義のような、個人に対して共同体を重視する思想に共感する人々が、日本社会に一定数存在することは間違いありません。しかしながら、それはなおも多数派とは言えません。実際のところ、リーマン・ショック後の「派遣村」が設置される状況下においてさえ、社会共助的な性格が強い定額給付金は支持されていません。報道各社の当時の世論調査では反対が60-70%台であり、賛成は10-20%台に過ぎませんでした。先月(2025年4月)もトランプ関税・物価高対策として現金給付が浮上しましたが、各社が行った調査で世論が冷たい視線を浴びせた結果、実施は見送られました。そもそも戦後日本において、自律した個人よりも社会の協働を重視する革新勢力に政権が託されることはほとんどありませんでした。
日本社会において多数派をなおも占めているのは、格差拡大が指摘される現在においても(見かけほど開いていないという分析もあります)、依然として自らを中流と認識している人々です。「一億総中流」という言葉の原点とも言われる内閣府「国民生活に関する世論調査」が示す国民の中流意識は、高度成長期から現在に至るまで一貫して回答者の85%を超えており、2024年の調査では89%でした(中の上14.2%、中の中46.7%、中の下28.1%)。この種の調査は質問の仕方や文脈によって回答が変わってきますが、内閣府調査の場合、前後の質問と内容的に切り離されていることで、この質問そのものに対する調査対象者の最も素朴な実感が表れています。
こうした中流意識層の多くは、共同体に対して自身や家族に重きを置く人々です。例えば、人材情報サービス会社マイナビの「主婦のアルバイト調査(2022年)」では、アルバイト(パート)の必須条件を複数回答で質問していますが、職場環境・待遇・シフト・エリアの各項目で最も多く挙げられた条件はそれぞれ、子育てへの理解があること32.9%、扶養の範囲で働けること39%、シフトの融通がきくこと59%、自宅から近いこと58.4%でした。同じくマイナビ「大学生のアルバイト調査(2024年)」では、最も当てはまるアルバイト目的として、自身の生活費・学費または家族のためと回答した学生の割合は22.8%であり、残りは貯蓄・趣味・交際費・社会経験などでほぼ占めます。苦学生が存在するのも事実であり、またボランディア活動に熱心な人もいるわけですが、善かれ悪しかれ、大半の大学生の関心は、切迫した生活や社会共助とは別の個人主義的な目的にあります。
日本社会とジョン・ロールズ
このような社会で受け入れられる考え方(社会理念)は、社会を個人の上に置くコミュニタリアニズムやコミュニズムではなく、個人の自由を重視する思想です。とはいえ、中流意識層は、苦しい立場の人々に対して無関心で無慈悲というわけではありません(そのような個人至上主義はリバタリアニズムと言います)。個人を優先しつつも社会に無関心でもない、そうした人々が日本の中流意識層の多数派です。この価値観にうまく合う思想を探すとすれば、「失われた30年」の時期に関心を集めた共同体主義よりも、ジョン・ロールズが唱えたような「リベラリズム」がふさわしい理念です。
ロールズは、(1)個人の自由、(2)公正な機会均等、(3)最も不利な人々の最大利益への寄与の3つをこの順序で重視します。つまり、個人の自由を犠牲にしてまで平等社会を目指すのではなく、個人の自由が保障された上で、社会で最も不利益を被っている人々を最大限支援しなければならないという考え方です。さらに「公正な機会均等」と「最も不利な人々の最大利益」が確保されるならば、多少の不平等は許容されます。「失われた30年」は、戦後日本で一貫して揺らいでこなかった中流意識層が抱くこうした価値観を見失った時代でした。国民民主党の洞察力がどの程度であったかはわかりませんが、賃上げなどで社会の雰囲気が変わりつつあることも手伝って、その公約は、少なくとも結果的には戦後社会の底流に流れ続けてきた価値観を再認識させました。
社会制度設計と政治の役割
それぞれの社会の基底にある価値観から遊離した制度を設計したとしても、民主主義社会においては、多くの場合うまく機能しません。日本においては、中流意識層の価値観を無視した制度は機能不全に陥る可能性が高いということです。1990年代の日本は、欧米のような二大政党制による循環的な政権交代を期待して、小選挙区制を導入しました。しかしながら、その理想は結局、実現しませんでした。階級社会型の制度を無理やり上から被せてみても、階級対立意識の希薄な日本社会において同じようには制度が働かないことは、今から思えば自明でした。近年では、日本の社会に合ったかつての中選挙区制に戻すべきという主張も見られるようになりました。
他方で、民意が判断を誤ることは珍しくありません。2025年参議院議員選挙を前にして、国民民主党ブームに乗った世論は今回消費税減税を求めています。それは果たして、中流意識層が長きにわたって望み続けてきた社会を今後も維持していくのに正しい選択でしょうか。確信を持てない政治家たちは、選挙を控えて揺れています。ここで世論に誤りがあると思うならば、それにおもねるのではなく、自らが正しいと信じる政策がなぜ正しいのかを有権者に説得し自身の支持を広げることが、民主主義政治家の本領です。
インターネット政治・選挙の普及によって、このような2つの側面を持つ民意に対するかじ取りは非常に難しい時代になりました。この政治状況の変化は、日本に限らず現在の民主主義政治の最大の課題になっています。政治家には、かつてないほどの才覚と大きな力量が要求されています。
文献案内として、ロールズのリベラリズムを分かりやすく現代に適用して論じているダニエル・チャンドラーの著作を挙げておきます。同書は、教養・英語・価格のどれにおいても大学生にぴったりです。
文献案内
Daniel Chandler 2024. Free and equal: what would a fair society look like? Penguin.
付記 このコラムは執筆者の論考であり、京都産業大学の見解ではありません。