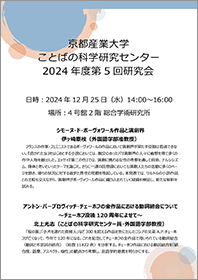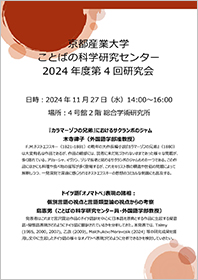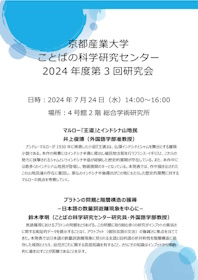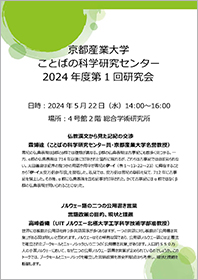2024(令和6)年度 過去の研究会詳細
2024年(令和6)年度 第5回研究会
| 日時 | 2024年12月25日(水) 14:00〜16:00 |
|---|---|
| 場所 | 4号館2階 総合学術研究所 |
発表者及びテーマ
伊ヶ崎 泰枝(外国語学部准教授)
シモーヌ・ド・ボーヴォワール作品と演劇界
北上 光志(ことばの科学研究センター員・外国語学部教授)
アントン・パーブロヴィッチ・チェーホフの全作品における動詞結合について
~チェーホフ没後120 周年によせて~
2024年(令和6)年度 第4回研究会
| 日時 | 2024年11月27日(水) 14:00〜16:00 |
|---|---|
| 場所 | 4号館2階 総合学術研究所 |
発表者及びテーマ
木寺 律子(外国語学部准教授)
『カラマーゾフの兄弟』におけるサクランボのジャム
島 憲男(ことばの科学研究センター員・外国語学部教授)
ドイツ語「オノマトペ」表現の諸相:個別言語の視点と言語類型論の視点からの考察
シンポジウム「ことばの歴史を復元する」
| 日時 | 2024年10月12日(土) 14:00〜17:00 |
|---|---|
| 場所 | 図書館ナレッジコモンズ |
発表者及びテーマ
14:00
開会の辞 吉田和彦(京都産業大学ことばの科学研究センター長)
14:05~ 15:00
梶茂樹(京都産業大学元客員教授、京都大学名誉教授)
フィールドからのアプローチ:
ウガンダ西部のバンツー系諸語の声調変化の研究
15:05~16:00
吉田和彦(京都産業大学客員教授)
文献からのアプローチ:
-ae-/-ai-という不規則な接尾辞を持つヒッタイト語動詞の起源
16:15~16:35
コメンテーター:小林正人(東京大学教授)
16:35~16:55
質疑応答
17:00
閉会
2024年(令和6)年度 第3回研究会
| 日時 | 2024年7月24日(水) 14:00〜16:00 |
|---|---|
| 場所 | 4号館2階 総合学術研究所 |
発表者及びテーマ
井上 俊博(外国語学部准教授)
「マルロー『王道』とインドシナ山地民」
鈴木 孝明(ことばの科学研究センター研究員・外国語学部教授)
「プラトンの問題と階層構造の獲得-日本語の数量詞遊離現象を中心に鈴-」
2024年(令和6)年度 第2回研究会
| 日時 | 2024(令和6)年6月22日(水) 14:00~16:00 |
|---|---|
| 場所 | 4号館2階 総合学術研究所 |
発表者及びテーマ
菱岡 憲司(山口県立大学国際文化学部教授)
「小津久足の文体—今古和漢雅俗一致—」
杉山 豐(ことばの科學硏究センター員・外國語學部准敎授)
「—『蒙山法語』諺解への檢討を通して—」
2024年(令和6)年度 第1回研究会
| 日時 | 2024(令和6)年5月22日(水) 14:00~16:00 |
|---|---|
| 場所 | 4号館2階 総合学術研究所 |