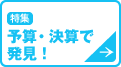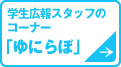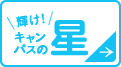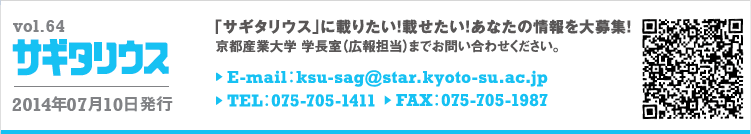- HOME
- 2014 Jul. Vol.64
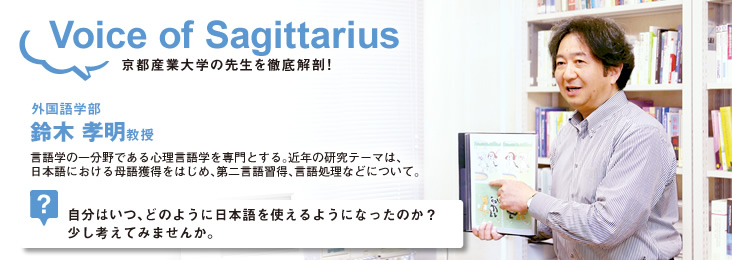
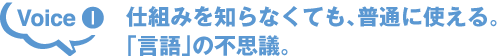
言葉について研究する言語学の分野の中でも、私が専門としているのは、言葉を使っている「ヒト」の方に注目した「心理言語学」 1の分野です。中でもヒトはどのようにして言語を獲得するのか、という言語獲得のメカニズムを解き明かしたいと考えています。大人が第二言語を獲得するメカニズムについては実用的な観点からも注目されやすいのですが、自然と身に付く母語の獲得は、子どもの能力を探る基礎研究の分野で、まだ多くの謎が残されています。
- 1
- 解説:人が言語を運用する際の心理・認知的な現象にも焦点を当てる、心理学と言語学の中間に位置する分野。
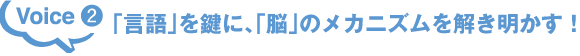
具体的な研究手法としては、母語を獲得している段階の幼児を対象に、ぬいぐるみや絵などを使って言語の発話や理解を確かめるという方法があります。例えば、「コアラがパンダを引っかいている絵」と、「パンダがコアラを引っかいている絵」を幼児に見せ、「コアラをパンダが引っかきました。それはどっちの絵?」と問いかけ、幼児が文の構造をもとに、その意味を理解しているかどうかを調べるなど、さまざまな実験を行っています。「ノベルワード」と呼ばれる造語を用いた最近の実験では、とても興味深い結果を出すことができました。その実験の内容を簡単に説明しましょう。まず、「ねける」というような子どもがこれまでに一度も耳にしたことのない単語を使って、「お姉さんが、お兄さんをねけっているよ」という文を聞かせます。それと同時に、二人の人が同じ動作をしている映像と、一人がもう一人に何かの動作を行っている映像 2を見せながら、それぞれの映像に対する子どもの注視時間を計ります。すると、まだほとんど話しができないような子どもでも、後者の映像を凝視することから、子どもは新しい動詞の意味を文の構造から推測し、学んでいる可能性が高いということがわかりました。英語については、こうした言語獲得の過程が以前から観察されていました。ですが、日本語においても、英語と同様の学習メカニズムが働いていることがわかったのです。その意味で、これは一つの大きな発見と言えるでしょう。
こうして一つ一つ実験を重ね、母語獲得のプロセスを研究しながら、私が最終的な目標としているのは、実は脳のメカニズムを解明することなのです。脳の研究 3と言うと、脳の活動部位などを観測する生理学のイメージを持たれる方が多いかもしれません。実際にそうした生理学的なアプローチによって、「文法を処理する際に使われる脳の部位」など、神経科学的な側面からの研究は随分進んできました。しかし、「ヒトがどのように文法を扱っているのか」という脳の「働き」については、生理学的なアプローチで解明することはできません。ですから私は、言語獲得の過程を明らかにすることで、「目には見えないルール」の謎に迫りたいと考えています。
こうして一つ一つ実験を重ね、母語獲得のプロセスを研究しながら、私が最終的な目標としているのは、実は脳のメカニズムを解明することなのです。脳の研究 3と言うと、脳の活動部位などを観測する生理学のイメージを持たれる方が多いかもしれません。実際にそうした生理学的なアプローチによって、「文法を処理する際に使われる脳の部位」など、神経科学的な側面からの研究は随分進んできました。しかし、「ヒトがどのように文法を扱っているのか」という脳の「働き」については、生理学的なアプローチで解明することはできません。ですから私は、言語獲得の過程を明らかにすることで、「目には見えないルール」の謎に迫りたいと考えています。
- 2
- 解説:状態変化を引き起こす動作を「使役」、そうではない動作を「非使役」と呼ぶ。
※写真提供:NTTコミュニケーション科学基礎研究所
- 3
- 解説:1861年、フランスの科学者ブローカによる「言語中枢」の発見以降、脳の役割についての研究は急速に進んでいる。
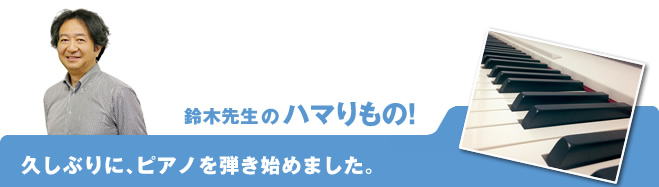
学生時代はプログレッシブ・ロックのバンドでキーボードを担当していましたが、教員になってしばらく音楽からは離れていました。久しぶりにピアノを弾くと、ブランクを埋めるのが大変ですね。
![]()
![]()
![]()
言葉使いは明確にと、徹底してご指導いただいています。「他人に説明できて初めて分かったことになる」という先生の言葉で、勉強の仕方が変わりました。
(外国語学部 4年次生 瀧元 陽太郎さん)
![]()