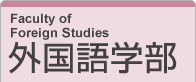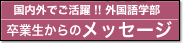- HOME
- 学部・大学院
- 外国語学部
- 国内外で活躍!! 外国語学部卒業生からのメッセージ
- 田口 純 さん
田口 純 さん

略歴
1980年 広島県立呉宮原高等学校卒業
1984年 外国語学部言語学科言語学専修英米語専攻卒業
1986年 鳴門教育大学大学院学校教育研究科修了(教育学修士)
大学院修了後、徳島市立高等学校で1年間の常勤講師を経たあと、
徳島県立池田高等学校で4年間教諭として勤務する。
1991年 筑紫女学園短期大学英文科講師
1998年 筑紫女学園大学文学部英語学科助教授
現在は筑紫女学園大学文学部英語メディア学科教授、入試部長
(2008年6月現在)

「先生、京産大の言語学科へ行くことにしました。ここを出たら、将来何になれるでしょうか?」「そうだなあ、先生かな。」
高校時代、こんなのんきな会話をしていた自分が今大学の教員になっていることの不思議さと、先生方をはじめ、みなさまとのご縁を改めて感じております。
現在私は「遠の都」福岡県太宰府市にある筑紫女学園大学で大学教員として、また、入試部長として、勤めております。筑女(筑紫女学園大学を略してこう呼びます)は大学文学部6学科の単科大学、それに短期大学部を併せて、学生数3千人あまりの大学です。京都産業大学(産大)に比べると、ずっと規模の小さな大学です。産大とは違い、女子ばかりの大学、また、仏教系の大学ですので、赴任した当初は戸惑うこともありましたが、早18年、すっかり福岡の人間となっております。教員としては、英語学、英語教育を中心に教えており、とくにここ数年は、中学・高校の教職に必修の「英語科教育法」や「英語教育研究セミナー」、e-Learning関連の授業を担当しております。e-Learningについては、関係する学会にも所属し、教材開発などにも関わってきました。入試部長は今年で3年目、少子化に伴う受験生の減少という問題を抱えながら、いかに入学者を増やすか、研鑽の毎日です。
現在の研究テーマは英語学史、とくに後期近代期における英文法の発達を当時の教育や社会情勢との関連から考察する社会言語学的研究を行っております。また、e-Learningを活用した効果的な英語学習、とくにメンタリングについて関心があります。さらに、産大の学生の頃から恩師の岩本忠先生からの宿題となっている「心的与格」についても、ずっと暖めてきております。
産大では今はなき「言・言」(外国語学部言語学科言語学専修)に4年間席を置きました。本当に楽しい4年間でした。言語学の「ゲ」の字も知らないで入学しましたので、岩本先生の「言語学概論」の授業に出てびっくり!最初の授業から何を講義されているのかさっぱりわかりません。「これは大変なことになったぞ」と入学前ののんきさから一転、専攻の英語の勉強ととともに、専門の言語学の勉強に勤しまざるを得ないことになりました。まずは概論書を何冊も読んで、その大枠をつかみ取ろうとし、また、専門用語を理解していくということから始めました。また、友人たちと自主的に読書会や講読会をして、お互いに助け合っていきました。(こういう人間関係を構築できたのが一番の収穫です。)学年が進むとともに、少しずつ言語学に興味を深めていくことが出来、それとともに自分の興味ある分野も見えてきました。岩本先生からは「少なくとも3つ以上の言語を修得すると、言語の本質が見えてくる」と言われ、第2外国語のドイツ語のほか、いくつかの言語を勉強しました。とくに伝統的な言語学では必須とされた希羅梵(ギリシャ語、ラテン語、サンスクリット)は仲間内でもどれかは勉強しなくてはということになり、ラテン語は小林標先生、サンスクリットは矢野道雄先生にそれぞれ手ほどきを受けました。とても修得したとは申せませんが、それぞれの言語を学んでいくと、それぞれの言語の持つ特徴が見えてきて、その成果が教育の面にも非常に有効であることがわかってきました。現在の仕事にも大いに役立っております。また、言語にとって重要な文字については、矢島文夫先生から習う機会を得、それまで当然のごとく考えてきた文字について、改めて考えることが出来ました。この文字学は現在の研究テーマにも関わっており、大学時代のおかげと感謝しております。
当時は日本語ブーム、とくに日本語の起源や系統のブームがあり、私も日本語に興味を持ち、専攻が英米語であるにもかかわらず、日本語学の授業を熱心に受け、卒論も日本語の方言について書き、将来は日本語教員になれればと思っておりました。大学院に進学しようと思ったのも日本語学をもっと勉強したかったからですが、周囲のいろいろな状況から教育を専門とする大学院へ進学することとなりました。(結果的にはそれが自分には合っていたと思います。)産大にいるときには大阪の日本語教師養成講座に通ったり、国立国語研究所の養成講座に参加したりしました。大学院でも英語や教育の専門科目だけではなく、日本語の専門科目も受講して、修士論文では日本語と英語の文構造の対照言語学的研究を行いました。残念ながら日本語教育の仕事に関わることは出来ませんでしたが、大学院修了後は高校の教員を5年間勤めました。その後、縁あって、短大へ異動し、現在に至っております。
現在、産大には言・言はなくなり、言語学を専門とする学科はございませんが、各学科において専門とする言語を学ぶとともに、ぜひ日本語をもう一度見直してもらえればと思います。自分の母語としての日本語を客観的な視点から見直すことにより、みなさんが学んでいる各言語がもっとわかってくると思います。
また、教育に関わりたい、教職に就きたいと思っている人は、ぜひいい友人関係を構築するようにしてください。勉強も遊びも含め、お互い切磋琢磨できる友人を持つこと、そういう人間関係を築くことが教員として必要なことと思います。産大の自由な雰囲気ではそれが十分に可能かと思います。
最後にとりわけ重要なのは、先生との出会いです。私には幸いにも入学当初から恩師の岩本忠先生の研究室に出入りさせていただける機会をいただき、4年間本当に充実した学生生活を送ることが出来ました。励まされたり、また、お叱りを受けたりしながら、研究する者の心構えや社会人としての生き方などを教えていただきました。高校や大学の教員として何とかやってこられたのも岩本先生のおかげと感謝しております。このような先生とのいい出会いをぜひみなさんにもしてもらいたいと思います。
人と人との出会いは不思議なものです。すべて縁だと思っております。産大に入ったのも縁、そこで出会った先生方や友人たちとも縁で結ばれ、その後の進路もすべて縁です。みなさんもどのような人と出会うのか、どのような将来が待っているのか、ワクワクドキドキしながら楽しい学生生活を送って下さい。積極的に行動することにより、さらにその可能性は広がっていきます。産大生にはそれが出来ると思っております。みなさんのこれからのご活躍に大いに期待しております。ありがとうございました。