
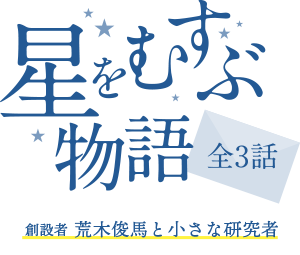
朝日新聞掲載 第1話 2019年8月31日 第2話 2019年9月15日 第3話2019年9月28日

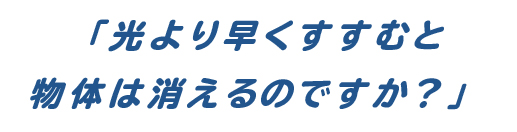

今から40数年前のある日、京都産業大学創設者・荒木俊馬のもとに一通の手紙が届いた。
「突然お手紙してすみません。私は今、中学二年生です。」
大学教授に中学二年生の少女が手紙を送ってくるとは、珍しいことだ。
荒木は宇宙物理学者であり、当時すでに多くの学術書を出版する天文学の権威だった。
少女は荒木の著書である『大宇宙の旅』を読み、質問の手紙を送ってきたのだった。
『大宇宙の旅』は天文学の専門知識を子どもでも読みやすいよう、工夫して編まれた本だ。「宙一くん」という一人の少年の冒険物語の形をとっている。
少女の手紙にはいくつかの質問が並んでいた。
「光速より速く進んだら時間は逆戻りするとは本当なのですか?光速を超えると過去が見えるというけれど、その過去を見ている間の時間はどうなるのでしょう。時間とは、いったいなんなのですか?」
「『宇宙の広さに限りがあるけど、はてはないかもしれない』というのは、どういった意味なのですか?」
少女の質問は、宇宙の成り立ちの不思議さをとらえたものだった。自分がわからないと思うことを言葉にするのは、大人でも難しいことだ。きっと何度も本のページをめくり、自分なりに考えをめぐらせたのだろう。
疑問は、研究の出発点だ。だから疑問は科学を進歩させる。
小さな研究者に返事を書こうと、荒木はペンを執るのだった。
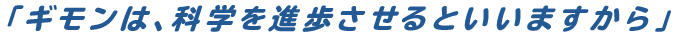
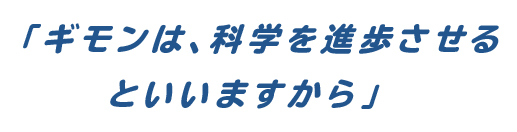
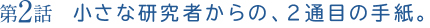
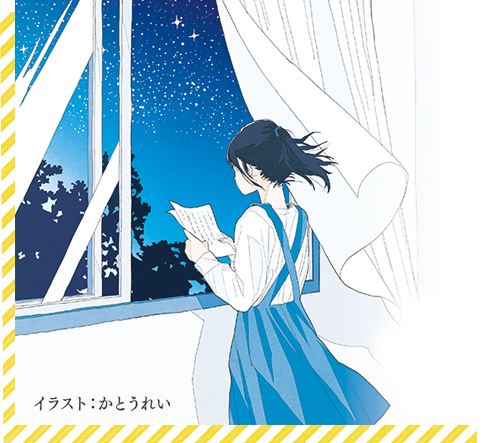

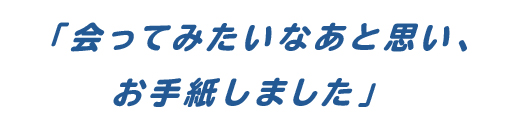
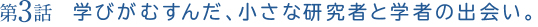

荒木が少女と交わした手紙のうち、残されているのは、ここまでだ。荒木自身は多忙のため少女に会うことができなかったが、荒木の妻が宿を訪れ、少女と語りあうことができたという。
少女の“新しいことを知りたい”という思いが、学者である荒木との縁をむすび、彼女の成長をうみだした。そんな「むすんで、うみだす。」精神は、今も京都産業大学に生きている。
神山天文台の研究者が参加して提案した世界初の彗星探査方法が、欧州宇宙機関(ESA)の新しい探査計画として唯一採択されるなど、画期的な研究を推進し成果をあげている。
それら先端の研究もすべて、学生や研究者たちの“知りたい”という強い思いから生まれたものだ。
次に新しい何かをうみだすのは、そんな好奇心を持って学ぶ、あなたかもしれない。


