東日本大震災における復興の歩みを学ぶスタディツアー「復興の未来~気仙沼から始まった物語」実施報告
2025.03.31

日本財団ボランティアセンターとの共催により、気仙沼市唐桑(からくわ)の旅館「唐桑御殿つなかん」に宿泊し、震災遺構を巡り、被災した経験を持つ方々との交流を通じ、災害と復興について学ぶ機会となりました。
「気仙沼スタディツアー」実施概要
| 日程 | 2025年2月17日(月)~2月20日(木) |
|---|---|
| 訪問先 | 宮城県気仙沼市 |
| 参加者数 | 学生8人+引率スタッフ1人 |
1日目:2月17日
日が暮れたタイミングで気仙沼に入り、無事に「唐桑御殿つなかん」に到着しました。つなかんは、東日本大震災の津波で大きな被害を受けた家屋を改修し、全国から訪れるボランティアの拠点でした。現在は、旅館として営業されており、その様子はドキュメンタリー映画「ただいま、つなかん」にも描かれています。
つなかんに到着すると、映画にも登場した女将の菅野 一代さんに盛大に出迎えていただきました。夕食を取りながら、一代さんにそれぞれ自己紹介し、また、このスタディツアーへの期待を分かち合いました。


2日目:2月18日
市場では、さまざまな海産物が競売にかけられている様子の見学のほか、ガイドの案内のもと、遠洋漁業で栄えてきた気仙沼のまちの歴史や特徴について知る機会となりました。古くから遠洋漁業の拠点として世界の海を渡ってきた海洋民としての考え方がどのように生まれたのかということに強い関心を示していました。
また、震災の日に気仙沼を襲った津波がやってきたときのこと、港に与えた被害の大きさは計り知れないものでした。その被害を乗り越え、技術革新のもとで復活してきた水産業の発展についてお話を聞くことができました。


午後からは、気仙沼の「まちあるき」を行いました。津波の被害が大きかったエリアは、土地のかさ上げや防潮堤の設置など、安心・安全のまちづくりが進められ、新しい商業施設が立ち並ぶ活気のあるまちになっていました。そのまちを歩きながら、時間とコストをかけてでも、海のそばで暮らすことを選んだ市民の気持ちに思いを馳せました。そして、復興記念公園では、気仙沼で亡くなった1,300名を超える方々の名前と年齢が刻まれた銘板を見つめ、高台から海を眺めました。見渡すかぎりのまちがかつて津波に飲まれたこと、そして、公園に設置された像や祈りのためのスペースに、震災の被害の大きさを感じていました。


ふりかえりでの学生の「語り」
- 今回、気仙沼の内湾のまちあるきをして、まだ防潮堤ができていないところもあるという話を聞き、復興にかかる途方もない時間を感じました。昔と違うまちになることを、地域の人はどう感じているのか、復興とは何か、わからないくなってきました。震災から14年が経ってもまだ復興は終わらないということに、復興とは何だろうかと改めて考える機会になりました。
- 丘の上になる復興祈念公園で、亡くなった方の名前と年齢を見ていると、100歳の人と0歳の子どもが並んでいました。それを見て、人は誰でも被災するということを考えました。公園に設置されているオブジェはみな海のほうを向いていて、自分たちで育んできた海と、傷つけた海という2つの相容れない思いを抱えているように感じました。
- このまちの人の地元に対する愛の深さ、仕事に対する熱意を感じました。一代さん、ガイドの方々から、誇りを持つことの意味を学んだように思います。祈念公園のオブジェを見て、1つ1つの意味を考えました。私はそこに、「悲しみの中にも希望がある」というメッセージを感じ取りました。それは、亡くなった人へのメッセージでありながら、今を生きている人への願いでもあると感じたからです。気仙沼の市場やミュージアムで、このまちの人は「海と生きる」ことを選んでいるのだと思いました。もし、自分が被災したとしたら、それでも海を見ることができるでしょうか?
3日目:2月19日
伝承館では、展示に加え、さまざまな映像資料を上映しています。津波で家族を亡くした方の語りを映像で見たことは、学生たちに大きなインパクトを与えていました。家族を亡くすことのつらさ、その傷つきは、10年以上経っても決して癒えるものではないということが、復興という言葉では語りきれない、失われた生命とやりきれない思いを巡る「重み」となって学生たちの心に届いたように感じます。






ふりかえりでの学生の「語り」
- 伝承館の動画の中で、奥さんを亡くした人の語りを見ました。土地がかさ上げされ、安心・安全なまちに生まれ変わることは大事だと私たちは思っていましたが、実はそうした変化に複雑な感情を抱く人がいることに気づきました。それは、私にとって衝撃的なことでした。復興は一直線に進むものではなく、さまざまな人の葛藤を飲み込みながら蛇行していくものかもしれないと考えました。
- 被災した人から、「何とかなる」という言葉をたくさん聞きました実際は地獄のようで、もうどうにもならないこともいっぱいあったと思います。震災が終わっても、自然の変化で不漁になったりするという話を聞きました。それでも、しぼりだすように「何とかなる」という言葉を出すこと、空元気であっても前を向くことでしか、この14年を生き抜いてこられなかったのかもしれないと考えたら、震災の傷の大きさを感じることができました。
- 昔ながらのまちに戻れないということは切ないが、できないことを嘆くのではなく、災害によってできるようになったことを考える、プラスで考えることは本当に大事だと思いました。新しい道、新しい家、新しいお店、防潮堤あ整備された「災害に強いまち」から、新しい魅力が生まれています。そこに、震災前からある自然豊かな港まちという魅力が組み合わされ、パワーアップしていると思いました。復興は元に戻すということではなく、新しい人たちや考え方を仲間に、新しいまちをつくっていくということだと思いました。
- 気仙沼がきれいなまちに生まれ変わったと単純に喜ぶことはできなかったと知りました。復興という言葉の陰で、複雑な思いを抱えている人たちに、どう向き合ったらいいのでしょうか。伝承館では、中庭に積みあがった車がさびてきていて、ガイドの方は、遺構が老朽化すること、人々の記憶が風化していくことへの懸念が示されていました。私たちは、震災の記憶を受け継ぐために、こうしてここに来ているのだ、今日のことを忘れてはいけないと思いました。
4日目:2月20日


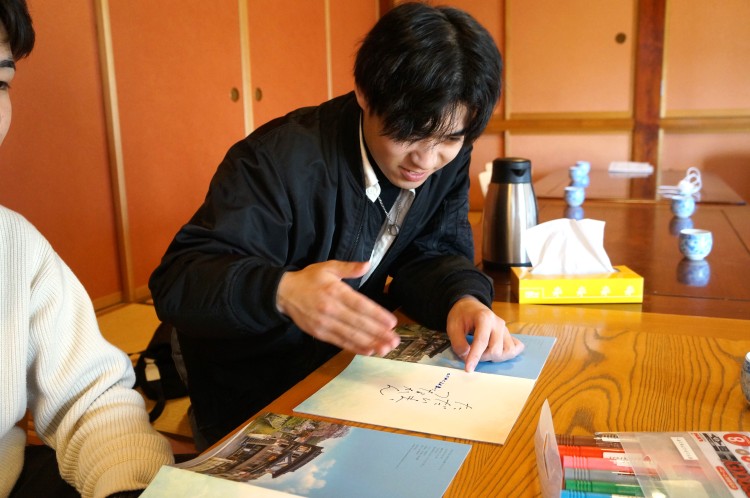

今回のスタディツアーは、過去の災害から学ぶことを通じて、これからの災害との向き合い方、復興とは何かを考えるきっかけとなることを目的として実施しました。東日本大震災から14年が経ち、気仙沼のまちでは、新しい建物が立ち並び、住民によるさまざまな取り組みが生まれています。そして、環境の変化と向き合いながら、それでも牡蠣の養殖に取り組む姿を通じて、人の「強さ」や海とともに生きる決意を感じることができました。それらは、再生の物語として学生たちに大きなインパクトを与えていました。
その一方で、学生たちは人々の葛藤とも出会いました。ガイドの語りや復興祈念公園での体験は、大切な人を亡くした気持ちや感情は、14年という月日で癒えるものではないということを感じさせるものでした。そして、災害で失ってしまったものの大きさは計り知れないものであり、それらが忘れ去られていくことを危惧する気持ちがさまざまな場面で語られました。それは、学生たちにより多角的な視点から気仙沼のまちを見る視座を与えることになりました。
このスタディツアーに参加した学生には、能登半島地震における現地活動に継続的に携わっている学生も含まれていました。今回のスタディツアーで、紆余曲折はありながらも、着実に復興への道を歩む気仙沼の姿は、大きな被害を受けた奥能登にも希望があるということを学生たちに感じさせるものでした。この経験をもとに、学生たちは引き続き被災地に関わり、復興の先にある未来を想像することができるようになったと感じています。
ツアー開催のきっかけとなった映画「ただいま、つなかん」の上映会および、スタディツアーの実施において共催いただきました、日本財団ボランティアセンターに深く感謝申し上げます。そして、宿泊・食事だけでなく、多くの学びをいただいた「唐桑御殿つなかん」の菅野 一代さまにお礼を申し上げます。
また、現地活動のコーディネートとして、一般社団法人「気仙沼地域戦略」の小柳 朋子さまに多大なるご尽力をいただきました。この場を借りて、改めて感謝申し上げます。ありがとうございました。
- お問い合わせ先
-
京都産業大学 ボランティアセンター 13号館B1階
〒603‐8555 京都市北区上賀茂本山
Tel.075-705-1530
Fax.075-705-3191
開室時間
平日:9:00~16:30(13:00~14:00を除く)
土曜:9:00~11:45※不定期に閉室することがありますので、事前にお問い合わせください。
日曜・祝日:閉室
volunteer-support@star.kyoto-su.ac.jp
