京都府綾部市で行った本学教員・学生による地域連携の取り組みについて報告会を開催
2025.02.21
2025(令和7)年2月11日(火・祝)、綾部市ものづくり交流館において、「令和6年度 京都産業大学むすびわざプロジェクトinあやべ」事業報告会を開催しました。
本学では、経済学部、経営学部、現代社会学部の3人の教員とそのゼミ生が、京都府綾部市でのフィールドワークを通じて、地域住民、地域団体、企業等との連携・交流を図り、大学生を主体に地域課題の解決や振興に寄与する取り組みを行っています。
綾部市の市民の皆さまをはじめ、活動で交流、連携した団体等の皆さまにも参加いただき、90人の参加がありました。
また、この日、事業報告会の前に綾部市主催のあやべ市民大学が開催され、本学の山田 啓二理事長が、地方創生の今後について講演しました。
開会のご挨拶をされた山崎 善也市長からは、あやべ市民大学に続き事業報告会が開催されること、これまでの本学との取り組みについてお話しいただきました。
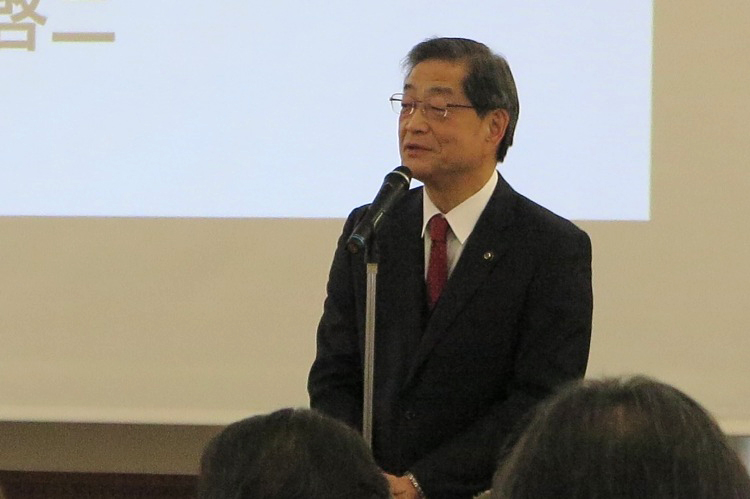

事業報告会では、初めに、本学の在間 敬子学長から、本学と綾部市との連携において協力いただいた、綾部市民の皆さま、団体、企業、市役所の皆さまにお礼が述べられました。

経営学部の松本 和明教授のゼミでは、綾部市役所、綾部市図書館、グンゼ、日東精工への調査や文献調査から見えた地域振興の取り組みについて、綾部市をベッドタウンとする提案や綾部市に道の駅「あやミュージアム」をつくる提案がなされました。ベットタウンの成功例の紹介や、具体的な取り組みとして、京都市内からの交通費補助や住宅手当などの政策を提案しました。

道の駅「あやミュージアム」の提案では、特産品の販売やイベント開催のほか、綾部市が1950(昭和25)年10月14日に「世界連邦都市宣言」を全国に先駆けて行った自治体であることから、平和モニュメントを整備し世界連邦都市としてアピールすることなどが提案されました。松本教授からは、頻繁に綾部市を訪れグンゼおよび日東精工の経営史に関する調査を継続していること、新たに注目している高倉 平兵衛、村上 義信および村上 頼太郎、小雲 嘉一郎についても調査を進めていることが紹介されました

現代社会学部の滋野 浩毅教授のゼミは、「地域との協働事業の成果と課題-『綾部こども探偵』と『小さな谷の小さな暮らし』の事例を中心に」と題して、始めに滋野教授から、取り組みの紹介がありました。今年度の事業は、必ず綾部市の地域の方、組織と協働で行うことを課題としたと説明があり、綾部の子どもたちが探偵で、学生が助手となり、綾部の魅力を発見し報告書にまとめる「綾部こども探偵」や、昨年12月に開催した、ゼミの学生が地域の子どもたちへダンスを教えるイベント、学生と地域住民との走らないサッカー「ウォーキングサッカー」実施の報告がされました。

学生の発表では、綾部市志賀郷町藤谷を拠点とした、自然と共に生きるための“暮らし仕事”の実践プログラム「ちいたに」での、農作業など里山環境での暮らしの体験と、ヒアリング調査の結果を踏まえ、今後のプログラムの取り組みの課題や解決策について発表しました。参加した子どもが、作業に飽きることを防ぐため、作業と遊びを交互に実施することや、地元の子どもたちの参加を増やすため、「ちいたに」に興味をもってもらう取り組みとして、受験や勉強、部活動など子どもたちの関心が高い物事を大学生と話し合えるイベント企画の提案がありました
経済学部の寺崎 友芳教授のゼミは、「綾部市の魅力を伝えるPR動画の製作と発信」と題して、はじめに寺崎教授から活動の概要説明を行い、その後、学生が活動報告を行いました。

寺崎ゼミでは、SNSでの情報発信を昨年度から実施しており、今年度は合計33本の動画(日本語・英語)をYouTube、インスタグラム、TikTokで発信しました。1班では、発信媒体それぞれの再生状況やユーザー層の調査、他の自治体の動向調査を行い考察も交えて、検証結果をまとめました。
SNSの浸透により、地域活性化の成功事例が増えていること、「どの発信媒体をどんな目的で利用しているのか」などがわかると、より目的にコミットした情報発信ができると感じたなど、報告がありました。

2班は食育を通じた綾部の特産品のPRをテーマに、Googleマップへの口コミ投稿を行った閲覧状況の調査結果と、食料市内自給率改善の経済分析を行い、綾部市産業連関表を用いた食料市内自給率が5%ポイント上昇した場合の経済波及効果に加え、地域の子供たちを対象とした地域食堂による食育のイベント結果、動画の視聴解析について説明しました。
参加者からは、「学生目線で観察し、参考になった。継続して研究をして欲しい」「更なる深堀りを期待します」など感想が寄せられました。
