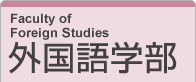ジャワ島中部地震被災地へ義援金
−インドネシア語専修学生有志の訪問レポート
外国語学部言語学科インドネシア語専修4年次生 大柿亮祐・森本洪太
インドネシア訪問に至る経緯

「前回のスマトラ島沖大地震の際には実現しなかった、現地への訪問を今回は実現したかった。」
現地への訪問には大きな意味があると私たちは考えていました。理由として、(1)募金を持参するとともに、現地の人々を激励する。(2)被害の現状を視察する、事ができるからです。前回は特に被害のひどかったアチェについては渡航延期勧告が外務省から発令されていたため、インドネシア訪問には至りませんでした。
今回、地震の被害がひどかったジャワ島・ジョグジャカルタにあるガジャマダ大学は、京都産業大学と提携を結ぶ大学であり、インドネシア語専修から留学している学生もいます。
ガジャマダ大学の学生の中には、今回の地震で被災し通学が困難になっている学生も多数いる事を聞いていました。そこで私たちは、今回の地震で被災した学生のために給付される奨学金として今回の募金を使ってほしいと考えました。
インドネシア領事館、インドネシア語専修の先生方にも協力を依頼し、今回の訪問という結果に繋がったのですが、募金の運搬・保管手段、ガジャマダ大学とのスケジュール調整など、様々な苦労もありました。
8月27日に現地の被害の状況を視察、28日に募金の引渡しを行いました。
現地の状況・感想

8月27日特に被害のひどかったバントゥル県を視察しました。
建物の倒壊は見るも無残で、3ヶ月経った今でも尚地震の爪あとを感じました。
そこに暮らす人々の生活は様々で、幸いにして倒壊を免れた建物で生活する人、建物が倒壊した跡地に簡素な家を建てて生活する人、支給されたテントで生活している人、何もせずに倒壊した建物をボーッと眺めている人、いずれにしても完全に復興したとはいえない状況が続いていました。
現地の人々が暮らす家はほとんどがレンガ造りの簡単な仕組みの家で、日本で現在何かと話題になっている「耐震」のそれとは大違いでした。地震の規模が大きかったことも被害が広がった要因の一つに挙げられますが、このように簡素な造りでは地震の規模が小さかったとしても、建物の大半が倒壊を余儀なくされていたと思いました。
政府も復興に大金をつぎ込めるほど経済的に余裕が無いような状況にあるとは思いますが、この地震に対する復興支援はインドネシアの最優先課題ではないかと感じました。


これからの活動の予定
“今回の訪問で視察した現地の状況を日本の人々に伝える活動”をしていきたいと思っています。方法としては、以前から専修ホームページで行っている現地新聞記事の翻訳活動、現地新聞社に提供してもらった写真と今回の訪問で撮影した写真を使った写真展等、活動の方法は様々あると思いますが、日本では報道されていないような生々しい現地の状況を絶えず伝えていく事によって、この地震に対する記憶を風化させないように努力していきたいと思っています。
- キャンパスフラッシュ:
外国語学部言語学科インドネシア語専修学生有志がジャワ島中部地震被災地へ義援金
―ジョグジャカルタ ガジャマダ大学を訪問― - インドネシア語専修Webサイト:
ガジャマダ大学へ募金贈呈、被災学生対象の奨学金に