ネットが幅を利かせる今も、テレビの影響力は相変わらず大きい。そして企 業が制作するテレビCMには、地域や文化や世代の価値観が巧妙に(あるいは無意識のうちに)織り込まれている。「メディアの社会学」を研究するポンサピタックサンティ・ピヤ教授は、アジア各国で日々放送される膨大な量のテレビCMを素材に、メディアが映し出す「期待」と、社会の「現実」との差異を紐解いてゆく。
広告代理店勤務から研究者に転身
——— 日本の大学院で学ぼうと考えたきっかけは何ですか?
日本に来る前は、広告代理店に勤めていました。広告は社会・文化や人びとの考え方に影響を与えますよね。制作側として携わってきた広告を、今度は研究の対象にしてみたいと思ったのです。
留学先に日本を選んだのは、英語とタイ語以外の言語も修得したいと思ったからです。その頃、日本のアニメがタイでも放映されていたので、日本に対して親近感を抱いていました。
日本語がほとんど話せないまま来日したので、最初はとても大変でした。コミュニケーションを取れなかったのが、一番つらかったですね。研究の資料も論文も発表も全て日本語です。必死で勉強して、何とかここまでやってきました。
——— 研究対象にテレビCMを選んだのは、広告代理店に勤務されていた影響なんですね。
そうですね。大学の学部でも広告やマーケティングを専攻していましたし、メディアに強い関心があります。さまざまな媒体がある中で、テレビCMを選んだ理由は2つあります。
1つは、テレビが人々に大きな影響を与えるメディアであること。昨今、ネットの台頭でテレビを見る人は減ってきていますが、それでもなお大きな影響力をもっています。もう1つは、今回テーマにしているジェンダーについて、テレビCMを分析したものが少なかったことです。メディアにおけるジェンダー観の研究の対象は、約8割が印刷媒体です。CMは影響力が大きいのに、あまり研究が進んでいないのです。
——— なぜ、テレビCMの研究は少ないのでしょうか?
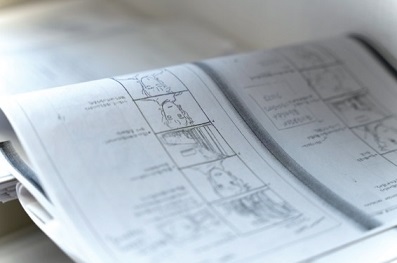
印刷媒体に比べて、データの収集が難しいからです。紙やネットなら図書館やウェブ上に過去のデータの蓄積がありますが、テレビCMはそういうわけにはいきません。
私たちの研究では、曜日と時間を決めて、視聴率の高いテレビ局に絞り、9週間にわたって録画をしました。その後、録画に出てくるCMを1つ1つ見て、あらかじめ決めた複数の指標に沿って評価します。たとえば、CMのナレーションが男声か女声か、主人公が男性か女性か、働いているか、働いていないか、どんな役職なのか、などです。さらに、ジェンダーのほか、家族像や外国イメージ、文化的差異という観点からも分析しています。
分析したのは日本だけではなく、タイ、中国、台湾、韓国、シンガポールの計6か国/地域のCMです。それぞれの国の社会背景や言語がわからないと分析はできないため、タイと日本以外は、現地の研究者にお願いしました。1か国につき、400〜500本のCMを分析しています。僕は日本とタイを担当したので、800本以上見ました。分析を終えたときには、もう当分、CMは見たくないと思いました。
CМに現れた、実態と異なる社会の期待

タイと日本の結果を比較して興味深いことがわかりました。日本もタイも、公共の場で働く女性がCMに登場する割合が極めて低いという点で共通しています。実際のタイ社会では女性の労働力率は日本に比べて非常に高く経済活動への参加の機会も多い。一般的に広告には社会のジェンダー構造が反映されていると考えられがちですが、客観的に分析してみると、タイでは社会とCMの描きだす像が異なっていたのです。
——— CMではよく人々の理想の姿が描かれます。タイの女性は本当は専業主婦になりたいのでしょうか。
生活が都会化し、専業主婦を良いと思う人が増えているというデータはあります。でも、それだけではなく、この結果は、タイの社会が、外で働く女性にも家事や子育てを期待していることを反映しているのではないかと僕は考えています。妻の方が夫より長時間働き、夫より稼いでいても、家事や子育ては女性の役割。そんなジェンダー観がタイにはまだあるのではないか。今は仮説段階ですが、インタビュー調査なども行って確かめているところです。
社会学は無意識をあぶり出す
面白いのは、制作者たちは自分たちの作ったCMが、このようなジェンダー観を反映していることに気づいていないことです。インタビュー調査をしましたが、彼らは意図して、働く女性の登場を少なくしたわけではなかったのです。
——— 分析して初めて見えてきたんですね。無意識にジェンダー観が表れるから、意図しない「炎上」につながるわけですね。
はい。制作側も見る人に嫌われたくて作っているわけではないですからね。SNSのおかげで、CMを受け取る側の意見が発信側にも届くようになりました。それはとても良いことだと僕は考えています。メディアが変われば、社会にも影響を与えます。最近では、LGBTQ+ 、同性カップルなど、社会的なマイノリティの人たちの普通の姿がテレビCMにも登場するようになってきました。また、「男性は仕事/女性は家事」というステレオタイプのジェンダー・イメージに代わって、「家事する男性/働く女性」という男女平等のイメージが強調されるようになるなど、新しい「非性ステレオタイプ描写」が徐々に増えてきています。「当たり前」はどんどん変化していきます。若い学生と話していると、ジェンダーに対する意識が多様になっていることが実感できます。
——— 先生の研究テーマも多様ですね。研究一覧の中に「タイBL」を見つけました。
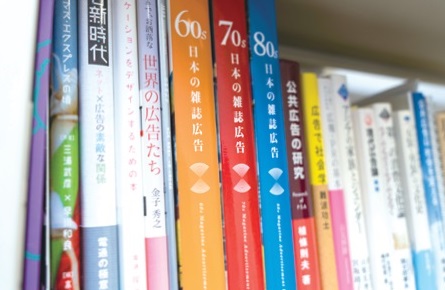
大きなくくりでいえば「メディアの社会学研究」です。社会に大きな影響のあるメディアを対象にしています。ある日、日本でテレビをつけたらタイ語が聞こえてきて、とても驚きました。それが、タイで作られた男性同士の恋愛ドラマ、つまりタイBLドラマでした。日本の地上波でタイのドラマが放送されたのは、初めてじゃないでしょうか。タイBLの影響で、何人かの日本人にタイ語を教えてほしいと言われました。その影響力の大きさに興味を持ちました。今、タイの人々のジェンダー観の変化を調べるアンケート調査を計画しています。
他にもタイからの技能実習生や、アジア観光に関する研究も行っています。研究室の大学院生は、広告とジェンダーを中心に研究しています。学部生は、アイドルや、SNSなどのネットメディアを研究対象に選ぶ人が多いですね。学生には、自分の好きなテーマを見つけて追究してほしいと思っています。


