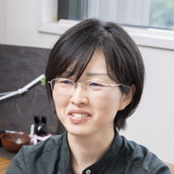伝統工芸を研究する京都文化学科の成田智恵子助教の手法は非常にユニークだ。職人の気持ちから、社会の移り変わり、材料の化学的性質まで、文系理系の垣根を超えた多角的な研究で、私たちが知らない伝統工芸の姿を浮かび上がらせていく。なぜ、今、伝統工芸を研究するのか。成田助教に話を聞いた。
工芸品は常に私たちの側にある
——— 工芸品の魅力はどういうところにあるのでしょうか。
ひとくちに工芸品といっても、時代や場所によってさまざまな捉え方があって、はっきりと定義することは難しいのですが、天然の材料を使い、昔からの伝統的な方法を受け継いで手仕事で作られたものが主に工芸品と呼ばれています。
伝統や工芸という言葉は、私たちの生活から縁遠い印象を受けるかもしれませんが、工芸品は身近なところにも存在しています。たとえば、漆器や陶磁器、ガラス工芸、着物、和紙、畳など、家庭の中でもさまざまな工芸品が使われています。
天然の材料ですから、作られる土地によって使う素材も違います。また、材料の違いに応じて加工技術も変わります。どのような工芸品が作られ使われていくのかは、文化にも大きく影響され、時代とともに移り変わっていきます。
このように、工芸品は物としての魅力だけでなく、作られた背景も興味深いのです。さらに、工芸品を知ることで、現代の生活を見直すきっかけにもなります。漆のように植物から得られる材料は、地球の気候と深く関わっています。植物の生活と人間の生活のバランスを考えて作り続けていくことは、人にも地球にも優しい形の社会を考えることになります。現代は大量生産・大量消費の時代ですが、手仕事で作られた道具を大切に使い続けていく生活の良さも感じてもらえたら、持続可能な生活の実現に近づいていくのではないかと考えています。
——— 現在、どのような研究をされているのでしょうか。

今は、京仏壇・京仏具の職人の方々にインタビューをして、技能継承がどのように行われているのかを調べています。京仏壇は金や漆をふんだんにつかった豪華な仏壇で、主に寺院などに納められています。京仏壇・京仏具は単に見た目がきらびやかなだけでなく、木工芸や漆塗り、金属粉と漆で仕上げる蒔絵、金属工芸や箔押など、多くの職人たちの技が結集して完成する総合工芸です。宗教観が変わって仏壇・仏具の需要が減ってきている今、分業制で細かく分かれた技能をどうやって残していけばいいのかが課題になっています。解決策を考えるためにも、まずは現状を知ることから始めようと思い、ひとりひとり話を聞かせてもらっています。
また、工芸の材料を研究して、現代の生活にも取り入れやすい工芸品の開発も行っています。たとえば、漆というと黒か朱の工芸品が多いのですが、実はピンクや緑のようなカラフルな漆の工芸品もありますので、そのことを若い人をはじめとして、もっといろいろな人に知ってもらい、興味をもってもらえますと、漆の用途も大きく広がっていくと思います。これまで進めてきた漆の力学特性や熱特性、外観特性などの研究成果を踏まえて、現在は色漆の色を従来よりも色鮮やかに発色させる方法を研究しています。
——— 和菓子屋さんとのコラボレーションも行っていましたね。

はい。京菓子司の亀屋良長さんの和菓子を、漆を塗った葉でできたお皿に盛りつけて展示しました。葉っぱは乾燥すると崩れ、濡れたままだと腐ってしまいますが、漆を塗ると半永久的に保存できます。
今はいわゆる紙胎漆器と呼ばれる和紙に漆を塗って漆器をつくる方法の活用・展開にも力を入れています。和紙は木や陶器などと違って簡単に成型できるので、たとえば子どもたちに和紙でお皿を作ってもらって、職人が漆を塗って仕上げるといった体験イベントを行って、工芸品を身近に感じてもらうこともできると考えています。
蒔絵職人を目指したはずが、研究の道に
——— なぜ、工芸の研究を始めたのでしょうか。
実は研究者になる前は、蒔絵の職人になろうとしていました。蒔絵というのは漆工芸の技法のひとつで、漆で絵を描いて、それが固まらないうちに金や銀などの粉を蒔いて表面に付着させる装飾技法です。美術の道へ進みたいと思い始めたのは、大学三年生のときでした。しかも機械で作るのではなく手仕事をしたいと考えたのです。いろいろ調べてたどり着いたのが、蒔絵でした。それまで特に工芸品に興味があったわけでもないのに、なぜ蒔絵を選んだのか、今でも不思議です。小学生のときに社会の便覧で見た写真の印象が残っていたのかもしれません。漆といえば黒だと思っていたのに、金色で絵が描かれていたのが意外で惹かれたのだと思います。
——— 最初は、職人になろうと思っていたのですか?
そうです。大学卒業後に、京都にある伝統工芸の専門学校へ行き、漆塗りや蒔絵を学びました。しかし、続けていくうちに自分の才能の限界が見えてきました。周りの同級生と比べても自分はそれほど上手くなく、職人になるのは無理だと悟ったのです。そこでまったく違う仕事を選ぶこともできたのですが、作る人になれなくても何らかの形で工芸に関わっていきたいと考えて、大学院へ進学し、研究の道に入りました。
大学院では漆の性質を調べる化学的な研究と、職人たちの社会的な状況を調べる心理学的な研究を行いました。大学院で理系と文系の両方の手法で研究に取り組めたことは、非常に良かったと思っています。工芸品は作る人がいないと成り立ちません。物としての側面だけでなく、人の気持ちや社会の在り方も同時に研究していくことが重要だと考えています。
——— 理系と文系のハイブリッドの研究だからこそできることがあるのですね。
研究手法に囚われず、工芸のことをもっと知ってもらえるような研究を行っていきたいです。もっといえば、新しい方法を研究していくことも大切ですし、伝統的な方法を続けていくことも重要です。
伝統を無条件に肯定するのではなく、疑ってみることも必要かもしれません。若い学生さんたちの感性も取り入れながら、多角的に工芸をとらえ、硬直させない。また、工芸品を科学的な観点から説明することでも、産業の発展につなげられるのではないかと考えています。
工芸に限定した話ではありませんが、今は何事においても続けるということが非常に厳しくなっていています。何百年も受け継がれてきたものでも、一度消えてしまったらもう元には戻りません。工芸とはどういうものかをみんなが知った上で必要ないと判断されているのなら仕方がないかもしれませんが、知らないがゆえに、工芸は要らないと思われてはもったいないですよね。
どういう形であれ、これからも工芸という手仕事の営みが私たちの生活の中にあって続いてほしいです。研究という面から、工芸の継承に少しでも貢献できれば嬉しいですね。