Vol.051 出版研究会 インタビュー
今回は本学文化団体連盟所属クラブの中でも
活動の幅が広く、精力的に活動している
出版研究会の5人にお話を伺いました。
出版研究会とは具体的にどういった活動を行っていますか?またその魅力は何でしょうか?

副主幹:中村 仁さん(前列右)
小坂 皓詳さん(後列右)
吉澤 慧さん(後列中央)
末松 嵩弘さん(後列左)
白鳥)出版研究会では、本学の学生にとって興味深い内容をまとめて、『PALET』という機関誌にして発行しています。内容については、学生の方々が読んでも勿論楽しめるものに仕上げていますし、実際に取り上げている内容を体験しても楽しめる物になっています。クラブとしては、我々クラブ員がやりたいことを実際に体験することができる上に、その思い出を1冊の機関誌として形にし、手元に残すことができます。また、本学には公認団体としての文芸部が無いので、本学において書き物ができる数少ない団体であるということも出版研究会の魅力です。
このような本誌『PALET』の他にも、シエスタ・神山祭で『小説PALET』を発行しているので、小説も書くことができます。
中村)例えば昨年は青春18きっぷで、西は長崎・東は仙台の2班に分かれて全国を回りました。長崎・仙台までは飛行機で向かい、青春18きっぷを使って京都まで戻る過程で取材したグルメを『PALET』にまとめました。このような青春18きっぷを使った旅は、大学生のうちに1度はやってみたいと思うが、実際なかなか実現しないことが多いと思います。このような実現困難なことでも、やりたいと言えば大体の事なら「公認団体」という大義名分のうえで行うことができます。雑誌にするうえでも、文章構成やレイアウト力は向上します。これは能力というより、「この配置だと読みづらい・気色悪い」といったような感覚が養われます。
小坂)WordやPhotoshopなどのプログラムの基礎的な部分は使いこなせるようになります。小説に関しては、やはり自分の思っていることを具現化できるのは魅力だと思います。
末松)新入部員だった昨年のゴールデンウィークでのこぎりやドリルを使って棚を作ったり、調味料の取材をしたりと、とにかく自分ひとりの大学生活では絶対にやらなかったようなことができます。
『PALET』新入生歓迎号について教えてください。

ではその『PALET春号』・『小説PALET』の見どころを教えてください。
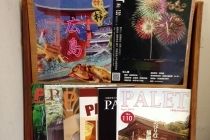
今回『PALET春号』にて編集長を務めた末松さん、編集長という立場に就いての感想や反省はありますか?
末松)OB・OGから意見をいただいて、やはり厳しい意見も多く、落ち込むこともありました。しかし、そんなOB・OGの意見は大変参考になりますし、我々現役部員の意見の両方を取り入れて、更に出版研究会は進化していけると思いました。
中村)編集長は後輩育成という面でも大きな意味を成しています。これは全員に共通することですが、私自身もやはり最初は勝手がわからず締め切りに追われることもありました。文章構成に関しても、どのような構成にすれば先輩からのお墨付きがいただけるのかといった思いや、Wordを使う上での苦労も多々ありました。しかしこれらは回数を重ねるうちに慣れていきます。
『小説PALET』について教えてください。

白鳥)始まりは本誌『PALET』神山祭増刊号の個人記事でしたが、いっそのこと小説でまとめて出してみようということで、『小説PALET』として独立させました。
吉澤)『小説PALET』にテーマはなく、1人ひとりの個性があふれる短編の集まりです。小説に普段馴染みのない学生にも、親しみやすい内容になっています。
小坂)私は連載小説を書く予定なので、今後の『小説PALET』をお楽しみに!
最後に一言お願いします。
一同)これからも多くの人と価値観を共有したいので、入部希望者を随時募集しています!『PALET』の製作は四季ごとなので、入部時期によって部内で差が出ることはありませんよ!
※本誌『PALET』は春夏秋冬に各1回と新入生歓迎号1回を含めた年間計5回発行。
『小説PALET』はシエスタ・神山祭の年間計2回発行。
今回の取材で、出版研究会の活動の幅の広さと発想の豊かさに改めて驚かされました。それは大学生活の理想形といえるものでした。出版研究会の今後の活躍に大いに期待したいです。
(2014.04.09)
【記事・写真:文化団体連盟本部 近持 恒平さん(経済・3年次)】
