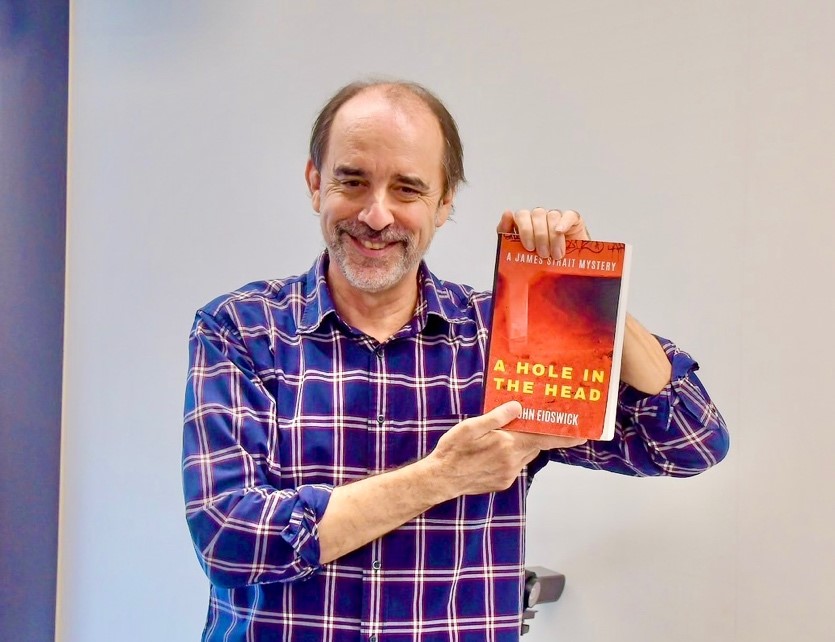2021.01.15
特集日本の大学でTOP3に入る「神山天文台」 設備と研究力、そして広報力が際立っていた!

新型コロナウイルスの影響で、人が集まるイベントを開催することが難しい時期が続いています。そこで注目を集めたのが、神山天文台がYouTubeで配信した「WEB天体観望会」や「WEB天文学講座」といった積極的な情報発信です。いったい、どんなねらいで始まったのでしょうか? その背景には神山天文台台長であり、理学部長でもある河北秀世(かわきた・ひでよ)教授の卓越したプロデュース力がありました。
創始者・荒木俊馬先生による「両立する」思想をそのままに
京都産業大学のシンボル、神山天文台。2010年に運用を開始し、今年10周年を迎えました。神山天文台は、1965年に創立した京都産業大学の50周年(2015年)に向けて、「京都産業大学らしいなにかを作ろう」と考えたときに、いくつも出た案のひとつだったそう。
「京都産業大学創設者の荒木俊馬先生は宇宙物理学の専門家で、京都産業大学は理学部と経済学部の2学部で始まりました。京都産業大学が、創立50周年の記念事業をきっかけに、天文台を設置することになったのは自然な流れでした。」
大学にとって、天文台を設置するのは一大事業です。河北先生はかつて県立ぐんま天文台を立ち上げた経験が評価されて、教員として採用されたそうです。しかし、河北先生が京都産業大学に来ようと思った理由はそれだけではありませんでした。
「この京都産業大学を立ち上げようと考えた荒木俊馬先生の思想に、私は強く共感したんです。『大学は研究だけをするような、象牙の塔であってはいけない。将来の社会を担って立つ人材を育成する場であるべきだ』。これは京都産業大学が始まったとき以来の血脈であり、それをきちんと受け継いでいきたいと思いました。」

自作の機械で、オリジナリティのある研究力を
結果、神山天文台はレンズ、電気、機械の研究室からクリーンルームまでを擁する、地上3階地下1階の施設となりました。

河北先生は、天文学の研究をレストランに例えて説明してくれました。
「言うなれば、望遠鏡は宇宙からの『光』という素材を集めてくる道具。でもどんなに稀少で高価でも、素材を集めただけでは、いいレストランとは言えませんよね?素材を上手に料理して初めて、おいしく食べられるわけです。すなわち、いいレストランにはいい腕のある料理人や、よく切れる包丁や圧力鍋といった専用の調理器具が必要です。それと同様に、いい天文学の研究所には光という素材集めだけではなくて、素材の特性を知ってきちんと『料理』できる研究者と、光を分析するための高度な装置が必要なんです」。
河北先生は、神山天文台の強みは「装置を自作できる」点にあると話します。
「先ほどの望遠鏡の話と同様に、装置の新しさを競うことになってしまったら、どこかの施設がもっと新しい装置を購入した時点で負けてしまう。技術は日進月歩ですから、機械は10年も経てば時代のトップではなくなってしまいます。
神山天文台は自分たちでその機械を設計改良できるのが強みです。望遠鏡で集めた光を分析する観測装置や実験・開発機器を自作することで、世界トップレベルのオリジナリティのある研究が続けられるようにカスタマイズしているのです。たとえば、赤外線を虹のように細かく分ける技術は、神山天文台は日本トップクラスですね」。
ちなみに、国内の大学が擁する装置開発拠点としての天文台としては、長野にある歴史の古い東京大学木曽観測所、直径1.5メートルある望遠鏡をもつ広島大学の宇宙科学センターと並んで、神山天文台は日本のTOP3に入る技術力を持つ施設とのこと。神山天文台にある直径1.3mの光を集める鏡をもつ荒木望遠鏡は、私立大学では最も大きいそうです。
社会との接点として、力を入れるべきは「広報」
京都産業大学神山天文台チャンネルより。彗星と小惑星をテーマに、講演と宇宙探査についてのトークセッションが行われた。
「天文教育は天文台の重要な役割のひとつです。大学がなにを研究しているのか、きちんと情報発信していかないと社会には理解されません。市民や一般企業の方々にも、神山天文台がどんな研究をしているのかを理解してもらわないと、その研究が経済につながり、どうやってお金を生み出し得るのか、活用する側にもアイデアの湧きようがない。研究者だけがその知見を知って独占していればいいわけではないのです。きちんと情報発信をして、一般の方々に知っていただき、社会に大学の知恵を伝えたい。経済と理学を両立するための一つの施策がこのWEB配信なのです。もともとWEB配信は天文教育とは相性がよくて、インターネットがはやりだした15年以上前から『地球の裏側から星空を実況中継しよう』という企画があったほど。Withコロナ以降、WEB配信に力を入れるのは、私たちからすると自然な流れでした。」
しかし、方法は見直したそうです。従来のプラネタリムの説明のやり方では「スローテンポすぎる」と気付き、人気Youtuberの映像を見て、「テンポが悪いと2、3分で離脱してしまう。退屈にならないようなコンテンツ」になるように考えたそうです。
WEB配信のひとつの成果として、今年10月に、京都産業大学神山天文台開設10周年記念シンポジウム「彗星×小惑星」をオンラインで開催。国立天文台教授・副台長の渡部潤一先生と、東京大学大学院教授の杉田精司先生、京都産業大学神山天文台客員研究員の池田優二さんと河北先生によるパネルディスカッションは、この12月にカプセルがオーストラリアの砂漠に着地して話題を呼んだ、探査機「はやぶさ2」の裏話をはじめ、聞きどころ満載でした。
「私は、広報は組織の要だと思っていますので、注力しています。たとえば国内最高性能を誇る天体観測装置の開発に成功したり、京セラやキャノンと共同研究をして世界トップクラスの知見を得たり、学生さんたちが海外で学会発表をしたり。そういった神山天文台に在籍する研究者の成果をきちんと伝えていくことも、天文台長の大事な責務だと思っています。」
教育と研究、社会をつなぐ「プロデューサー」としての天文台長
「理学部の教授としての仕事は、学生への教育が主ですね。現在、神山天文台ではポスドク(博士号)をもった研究者が7名います。学部生たちにとって、優秀な研究者たちと一緒に研究を進める経験は、大きな財産になることでしょう。実際、学生が育っていく様子を見るのはうれしいものです。また私は理学部の学部長でもありますから、全体を見ることもしています。」

「あとは、私自身の研究ですが、土日や帰宅後の時間を使って、論文を書いています。それは今に始まったことじゃなくて、もともとシャープの会社員で私の社会人としての人生は始まったので、『研究は、自分の時間をうまく見つけて、こつこつ行うもの』というスタイルが身についているんです。」
河北先生の専門は彗星科学。もともとは、1996年に地球に近づいた「百武彗星(ひゃくたけすいせい)」の美しさに魅了されたことがきっかけなのだそうです。当時の河北先生はシャープで会社員をしていた時期ですが、その見た目の美しさと同時に、物理学としての美しさ、彗星には2つの美が備わっていた、と河北先生は話してくれました。
「百武彗星の光を分析したところ、きれいに虹のパターンをつくっていた。『なんて美しいんだ』と感動したんです。宇宙は神秘です。人類は永遠に宇宙を理解できないかもしれないけれど、物理学という道具を使えばすこしはその謎解きができる。研究そのもの、謎解きの過程がおもしろいと思いました。」

教育者として、研究者として。さらに神山天文台に集まる人々を総合的に束ねる天文台長としての仕事は、プロデューサーに近いものがある、と河北先生は話します。
「学生たちの教育と成長も大切にしていますし、一般市民への情報発信も欠かせません。神山天文台に所属する研究者たちの研究環境を整えて、彼らが成果を出すことも私の仕事でもある。天文台に優れた研究者と設備があれば、『一緒に共同研究をしませんか』と企業からも声がかかります。こういった動きを通じて、天文台での学びの成果を社会に還元していきたいのです。研究だけでも経済だけでもなく、その両立をする、これまでになかった天文台にしていきたいと思っています。」
あらためて驚いたのは、河北先生の卓越したプロデュース力です。学生と研究者と市民と企業をつなげる場として、神山天文台が機能して、社会の役に立っていく。こうして書くと簡単に見えるかもしれませんが、さまざまな人を巻き込んで、一緒に実行していくのは本当に難しいことです。
神山天文台が、まさに京都産業大学のスローガン「(さまざまな人々を)むすんで、(新しい価値を)うみだす。」現場となっていることに感動しました。