2022.06.30
カルチャー3年ぶりに山鉾巡行が復活! 祇園祭へ行こう!

京都の祭りといえば祇園祭ですが、7月1日から1カ月間行われているのは知っていますか。その中でもハイライトは7月17日と24日。八坂神社の神輿渡御(みこしとぎょ)と34基の山鉾巡行(やまほこじゅんこう)です。その様子は「動く美術館」ともいわれ、ユネスコ無形文化遺産にも登録されています。今年は3年ぶりに山鉾巡行が復活します。絢爛豪華な祇園祭を見に、ぜひ出かけてみませんか。
祇園祭は「疫病退散」の祭り
千百年の伝統をもつ祇園祭。869年に日本各地に疫病が流行したときに66基の矛(ほこ)を立てて災厄の除去を祈ったことが由来とされています。
7月1日から1カ月間にわたって行われますが、その中でも山場となるのは7月17日と24日に行われる八坂神社の神輿渡御と計34基の山鉾巡行です。
山鉾巡行とは、御神輿の通る道を祓い清めて回る役割があり、17日には山鉾23基、24日には同11基がいずれも朝9時から巡行します。
その後、17日夕方は神幸祭(しんこうさい)、24日夕方には還幸祭(かんこうさい)が行われます。17日の神幸祭では、神様を乗せた3基の御神輿が八坂神社から市内を回り、四条御旅所(しじょうおたびしょ)へ渡御され、その後24日の還幸祭で、八坂神社へお戻りになります。また、それぞれ巡行の前々日と前日は、宵々山・宵山と呼ばれ、京都の街中各所に山鉾が立ちます。うち15日、16日は、露店が多く出るので、浴衣を着て散策するのもおすすめです。
祇園祭・巡行の日程
前祭(さきまつり)
宵々山:7月15日、宵山:7月16日、巡行:7月17日
後祭(あとまつり)
宵々山:7月22日、宵山:7月23日、巡行:7月24日
函谷鉾の運営に携わる、小林ゼミにインタビュー
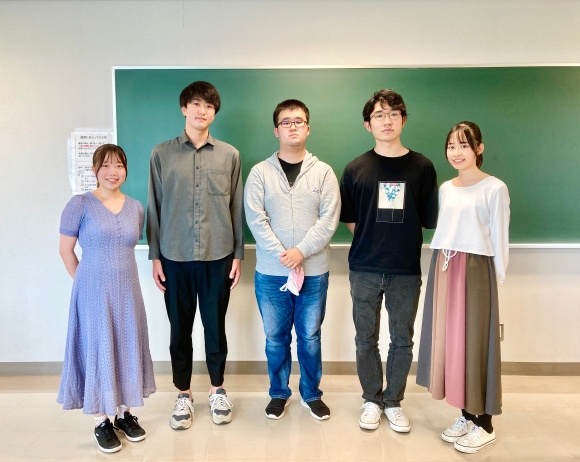
——函谷鉾の運営参加について教えてください。
齊喜さん:祇園祭の函谷鉾の活動を手伝うのですが、まずは例年5月上旬のゼミ合宿最終日にゼミ生全員が函谷鉾保存会の会所※に挨拶へ伺います。その後も打ち合わせを重ね、粽※(ちまき)づくりや鉾の曳き初めなどを経て、祭り本番に臨みます。7月17日には3、4年次生の男子学生も鉾を曳きます。
平松さん:祇園祭の山鉾巡行は女人禁制なので女性が曳くことはできませんが、代わりに16日の「提灯落し※」は3年次生の女子学生がお手伝いしています。
衣笠さん:13日〜16日の宵山期間には、ゼミ生が交代で、観光客の案内誘導や会所2階での懸装品解説、鉾内見学の案内、テントでの授与品授与(販売)のお手伝いをします。

福永さん:祇園祭には全国から大勢の人がお越しになります。鉾や懸装品について尋ねられることも多いので、責任は重大です。ゼミでも勉強し、6月に「函谷鉾検定」を受けました。テストは3級〜1級までの3種類。祇園祭実習に参加するために、必死に勉強をしました。
※会所とは、各山鉾町の寄合所のこと。
※提灯落しとは、16日の夜9時半頃、駒形提灯(こまがたちょうちん)を鉾上での最後のお囃子の終了と同時に消灯、一斉に落とす函谷鉾の名物行事。提灯落しの様子はこちら
※粽とは、笹の葉でできた厄除け。

祇園祭の取組みを通じて伝統を受け継ぐ
——橋本さんは1年次に巡行を経験されたのですね
橋本さん:はい。鉾の後ろを行くお供車を曳かせてもらいました。朝7時に集合し、太陽が照り付ける中、汗を流しながらの巡行は大変でしたが、達成感は格別でした。

齊喜さん:昨年と一昨年は山鉾巡行が中止されたので、今年の復活が楽しみです。
平松さん:コロナ禍でも、テントでの粽授与はありましたが、感染症対策のため学生が関われたのは1人1時間半でした。今年は空いている全ての時間を祇園祭でご奉仕できるので楽しみです!
衣笠さん;小林ゼミの合言葉は「先輩の背中を見ろ」。祭りへの臨み方、動き方や細かい作業を保存会の方や先輩たちから学び、それを後輩へとつないでいきたいです。
福永さん:私は大阪出身。最初は「保存会の人たちは厳しそう」と身構えていましたが、皆さんとても優しくて、祇園祭の歴史や役割、展示されている懸装品などどんなことも丁寧に教えてくださいます。そんなところに、皆さんの祇園祭への愛と情熱を感じます。
——祇園祭の見どころを教えてください。
福永さん:10、11日に鉾建て(ほこたて)が行われます。釘を一切使わない伝統技が素晴らしいです。16日夜は「提灯落し」の後に「日和神楽※(ひよりかぐら)」があり、祇園囃子を奏でながら歩く様子も見られるそうです。

平松さん:この時期の京都は、家のしつらい、掛軸や、食べ物など、普段の暮らしも「祇園祭」一色になります。生活と祭りが結びついている京都らしさをぜひ見つけてください。
衣笠さん:私は兵庫出身ですが、京都の方々の祭りにかける熱量が本当にスゴイと驚かされます。この熱さを感じてほしいです。
齊喜さん:私は大阪出身で、祭りといえば「だんじり」。でも祇園祭は全く雰囲気が違います。初めて見たとき、「これは神事や。文化は祭りを基盤に広がっていくんや!」と感動しました。
橋本さん:山鉾巡行前日までのムードから一転、巡行当日朝のピリッとした空気感に衝撃を受けました。これこそが町衆が積み上げ、長い歴史を誇ってきた京都の神事・伝統文化の姿だと感じました。宵山の華やかさと巡行の気迫。その両方を、ぜひ味わってください。
※日和神楽とは、山鉾巡行の晴天を祈り、御旅所からさらに旧巡行路や寄り町を次々に回る行事。
私の地元では規模の小さな祭りしかなかったので、祭りといえば露店のイメージでした。今回の取材を通して、私と年齢が変わらない学生たちの祇園祭にかける強い思いを知りました。小林ゼミ生以外にも、本学ボランティアセンターも祇園祭ごみゼロプロジェクトに参加しているそうです。祇園祭は、たくさんの人たちの思いが集まって成り立っている伝統的な祭りなのだと思いました。また、多くの人々が求めているからこそ千年以上続いてきたのだと感じました。
皆さんもぜひ3年ぶりに山鉾巡行が復活する祇園祭を見て体感してください。













