

先日京セラ美術館で開催されたカルティエのイベントで西陣織のドレスが着用されるなど、近年話題になっている西陣織。そんな西陣織で仕立てた洋服のブランド『N’s1182』を、本学法学部4年次生の前田 雄亮さんが立ち上げました。若者に西陣織を広めるとともに、いずれ海外進出も目標にしていると話す、チャレンジ精神旺盛な前田さんに話を聞きました。
ブランド立ち上げのきっかけはビジネスコンテストへの参加
西陣織とは京都・西陣の高級絹織物で、国の伝統工芸品にも指定されています。友禅のように織ってから柄をつけるのではなく、先に染めた糸(先染め)を使用して模様を織り出す紋織(もんおり)という方法で生産されます。
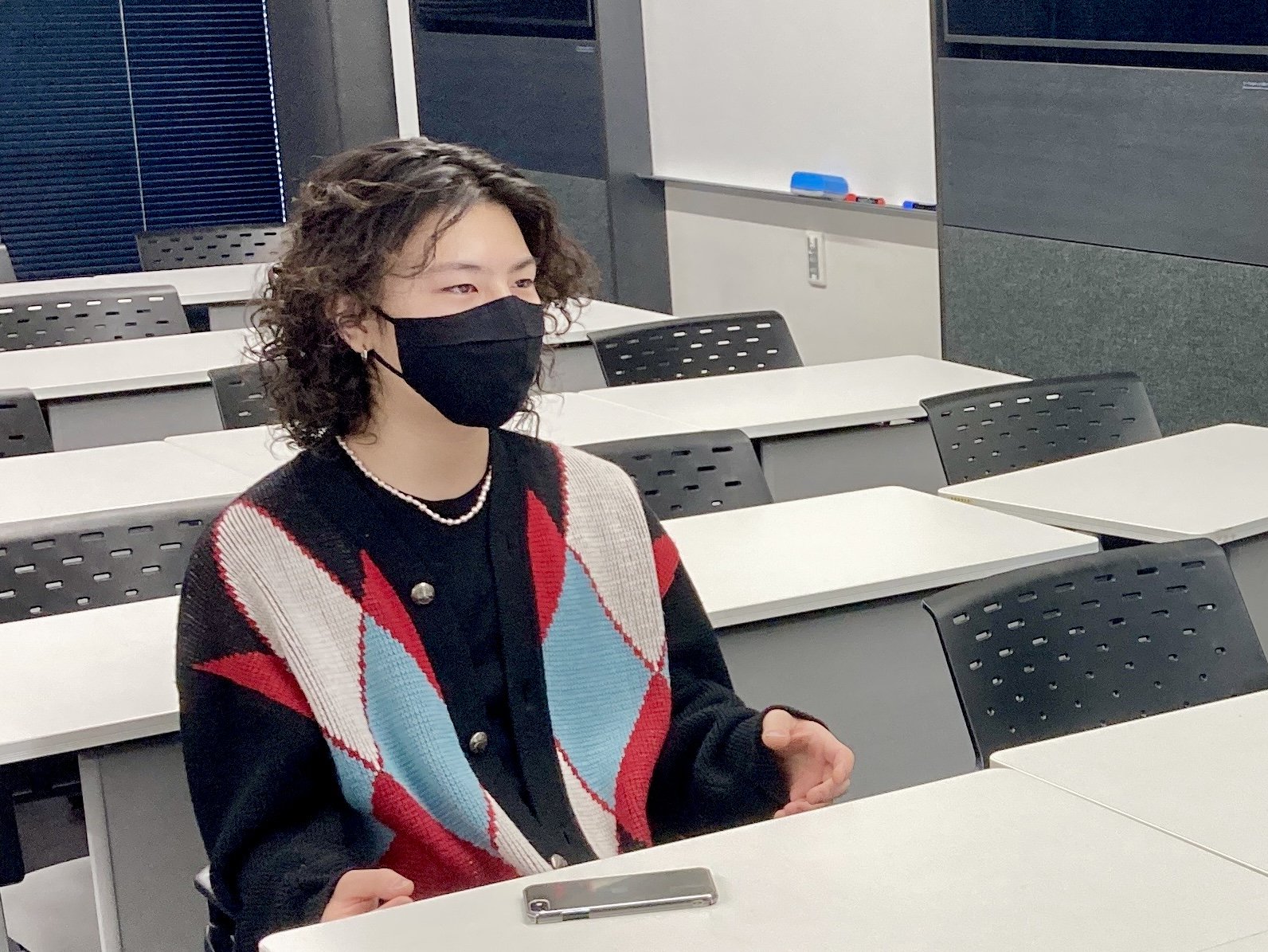
前田さんは西陣織を製造する家庭に生まれましたが、小さい頃は伝統産業に全く興味がなかったそうです。一方で、昔から衣服には興味があり、古着を自分でリメイクするのが好きでした。西陣織を使った初めての作品は、コロナ禍で自宅にいる間に帯地に既存のデニムを型取りして作ったパンツ。そこから2020年11月に開催された京都信用金庫主催のビジネスコンテストで西陣織を使ったアパレル事業についてのアイデアを発表し、2位に入賞します。それをきっかけに、「作品を世の中に出し、衰退しつつある西陣織文化に新しい形を広めたい」という思いが強まりました。
ブランド立ち上げには、コンテストを通じて知り合った人々や西陣織の職人さん、クラウドファンディングのサポーターなど、多くの人が関わっています。地域共生・連携を促す本学の「町家学びテラス・西陣」にも足を運んだこともあったそう。モデル探しも前田さん自身が行い、人とのつながりを支えにして商品を完成させました。
「町家学びテラス・西陣」についての記事はこちら
学内外のさまざまな人とつながる町家。京都産業大学の「町家 学びテラス・西陣」に行ってみた!
職人と直接交渉してつくられる『N’s1182』のアイテム
ブランド名である『N’s1182』のN’sは西陣で作られていることを表現しており、1182は西陣織の帯の長さと幅が1丈1尺8寸2分であることに由来しています。
制作にあたってはさまざまな苦労があったそうです。西陣織の帯生地が幅約38センチ長さ約5メートルであるのに対して、洋服の生地は幅1メートルが基本。洋服にするには普段の製法とは違う方法で織ってもらう必要があるため、職人さんを説得するのに苦労したそうです。パターン(服を作るための設計図)を起こす際にも生地規格の違いを考慮しているとのことです。また、耐久性を確認する生地のテストも1種類につき15回ほど行っています。これらの苦労を経て最初に完成したのが、絹製のパンツとマスクでした。

職人の高度な技術が結集した西陣織は、主に着物の帯に使用されています。その技術を次世代に繋ぐため、『N’s1182』では “日常でも着られる着物スタイル” をコンセプトとしました。西陣織の技術を活かし、現代にも馴染むオシャレな服を目指します。「この『No. NS-003』というパンツにはベルトループをつけず、腰に付いている紐でウエストの部分を縛って着用します。着物に帯を巻くことからインスピレーションを受けたデザインです。伝統繊維を使って現代の人にも着やすいものを作りたいです」と前田さん。

また、マスクは表地に西陣織、肌に触れる部分は兵庫県西脇市の播州織で作られたガーゼを使用しています。播州織は元をたどると西陣織から派生したものだそうで、抗菌加工もしっかりしており、機能性も優れています。
これからの展望について、「コートやセットアップなど、一着だけで様になるものを作りたいです。また、車に西陣織デザインの外装をほどこした作品など、アパレルだけにとどまらず、伝統繊維がもっと他のところで活用されるように認知度を上げていきたいです。いずれは海外へ進出することも目標にしています!」と語ってくださいました。
起業して商品を作り上げるうちに、西陣織についての理解だけでなく、歴史があるゆえになかなか変えづらい業界構造や、職人さんを取り巻く環境への洞察も深まっていったと話す前田さん。アイテム作りに加えて、衰退しつつある西陣織の現状を打破できるシステムを作りたいという情熱も高まっています。「業界が行き止まっているからこそ開拓できる余地がたくさんあります」と語る前田さんの言葉には、西陣織への思いが溢れていました。
新しいことにチャレンジしたい学生へのメッセージ
「実際ブランドを立ち上げてみて、今はやりたいことはなんでもできるなと思いました。学生起業が注目されつつありますし、服飾の専門学校に行っていない自分でも、インターネットで学んで服を作れる環境があります」と前田さん。
しかし、試作を通して、一人で全てをこなすには限界があることも学んだと話します。コミュニティー作りも大切な要素であり、「洋服を制作する上で沢山の人の支えがあった」と繰り返し話す姿が印象的でした。
今回の取材を通して、私と年齢が変わらない京都産業大学の学生が、伝統を守っていくために新しいことへチャレンジする姿勢に勇気をもらいました!たとえ周囲から無理だと言われたり、一人では難しそうなことでも、やりたいと思ったことは、ためらわずにやってみることが大切だと感じました。
コロナ禍でつくりにくかった学生・教授とのつながり、学外の人とのつながりは、徐々にではありますが環境が戻りつつあります。学生起業を実践している先輩もいるので、在学中にやりたいことがある人はぜひ挑戦してみましょう!
『N’s1182』の最新情報・詳細は、InstagramまたはTwitterをチェック!
Writer
取材をした人

現代社会学部3年次











