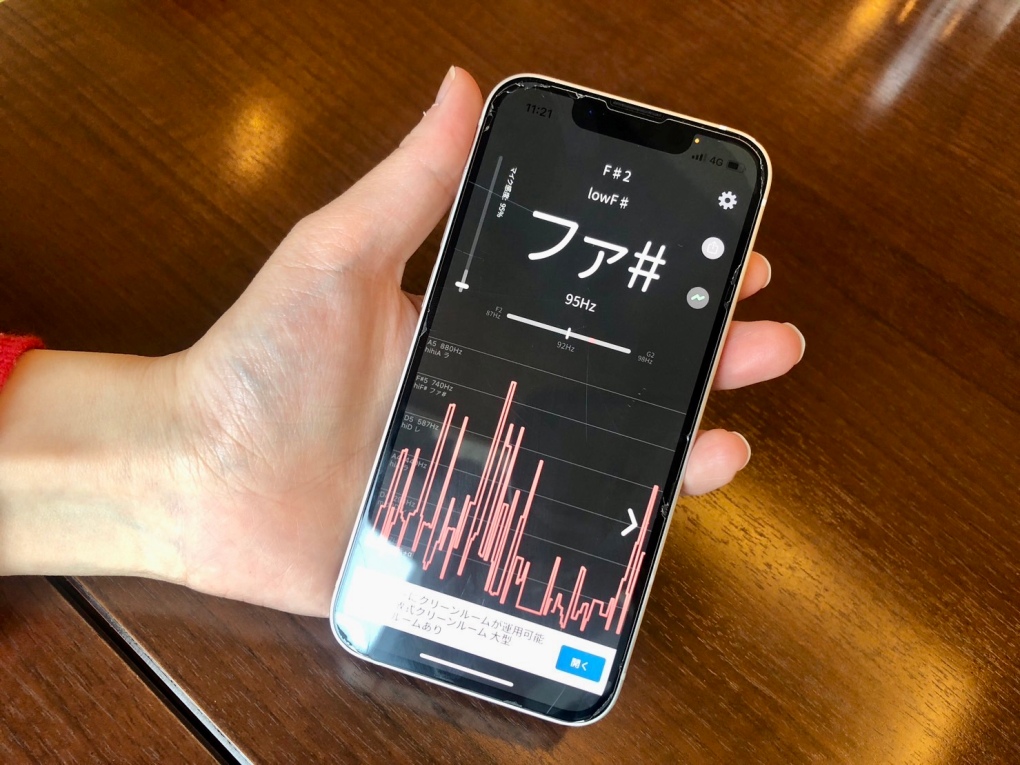2021.02.10
キャンパスライフ歴史を誇る馬術部!その強さの秘密に迫る

京都産業大学の課外活動のなかで、体育会第一号として創立当時からの歴史をもつ馬術部。全日本学生馬術大会や関西学生馬術選手権大会で好成績をおさめるその強さの秘密に迫りました。
そもそも馬術ってどういう競技なの?
馬術には3種類の競技があります。1つ目は、障害物を馬と一緒に越えて減点をタイムで競う「障害馬術」。人間でいえば、ハードル走のような競技です。
2つ目は、馬をいかに正確かつ美しく決められた運動をさせることができるかを競う「馬場馬術」。これを例えるなら、フィギュアスケートと似ています。
3つ目は「総合馬術」。例えるなら、トライアスロンのような3種目の複合競技です。前述した障害馬術、馬場馬術に加えて、クロスカントリー(野外走行)を組み合わせた競技となっています。クロスカントリーでは、山の中で障害があるコースを人馬一体で走り、スムーズに障害を越えて制限時間内にゴールすることを競います。総合馬術は、総合力が問われる難易度の高い競技です。
「馬が8割、人が2割」好成績の理由とは?


馬術の馬は、野生の馬と違い本能が弱いそうです。たとえば、野生の馬はいつでも逃げられるように立って寝ます。しかし厩舎にいる馬は倒れて寝るそうです。つまり、人間に世話をされて、飼育されることが前提なのです。
野生ではない馬術の馬は、人間の言うことを聞ける馬であることが重要です。つまり人間に調教されている必要があります。もし、人間に調教をされることを拒む馬がいたら、馬術の馬としては不適合となってしまいます。「馬への調教」とは、馬術競技に出場するために大前提となる、不可欠な条件なのです。菊地さんは、才能がありながらも調教がうまくいかず、競技で失敗した馬もたくさん見てきたからこそ、調教の大切さを知っているのでしょう。そして、上手に調教された馬には、馬術競技で好成績を収める道が開けています。

とはいえ、すべてを馬に任せるだけでは勝てません。馬の健康と精神の状態をつねに確認し、人がきちんとケアすることで馬と人とのあいだに絆が芽生えるのだそうです。
「馬だけでも、人だけでもなく、馬と人が一心同体になることで勝利をつかみ取ることができます。そのときこそ、馬術をやっていてよかったと思える瞬間ですね」(原田さん)
さらに、「馬術部員はみんなそれを熟知していますから、馬への愛であふれています。馬への愛については、自信をもって断言できます」と前主将の森田さん。本学の馬術部員が好成績を収める秘密は、まさにそこにあるといえるのではないでしょうか。
馬とともに生きる馬術部員と、これから
エサやりから調教、そして手入れまで。馬が大好きな部員の皆さんにとって「馬は生活の一部」なのだそう。「練習時間でなくとも、馬と一緒にいるのが当たり前」と、小仲さんは言います。
そして4人が口を揃えて「馬と一緒にいるその生活が、なにより楽しい!」というのが印象的でした。
歴史を振り返ると、京都産業大学の創設者である荒木俊馬先生の長男で、京都産業大学名誉教授の荒木雄豪先生は、馬術でオリンピックに出場したほどの実力の持ち主でした。馬と共に生きる馬術部が、これまで、そしてこれからも継承されていくでしょう。


創立当初から今まで、馬術部が京都産業大学に残した功績は計り知れません。それは一日二日で得られるものではなく、部員の皆さん全員が、時間をかけて、馬との絆を培ってできた結晶です。そしてそれはこれからも続いていくことでしょう。
馬術は確かに難しいような思い込みがありますが、大学から始める部員もたくさんいるそうです。大学では馬術の授業があり、それがきっかけで、入部した人もいるそうです。主将の菊地さんは、「馬への愛があれば大歓迎」とのこと。
馬好きの人は、これを機に、歴史ある馬術部に注目してみませんか?たくさんのかわいい馬と、愛に満ちあふれた部員の皆さんが待っています。