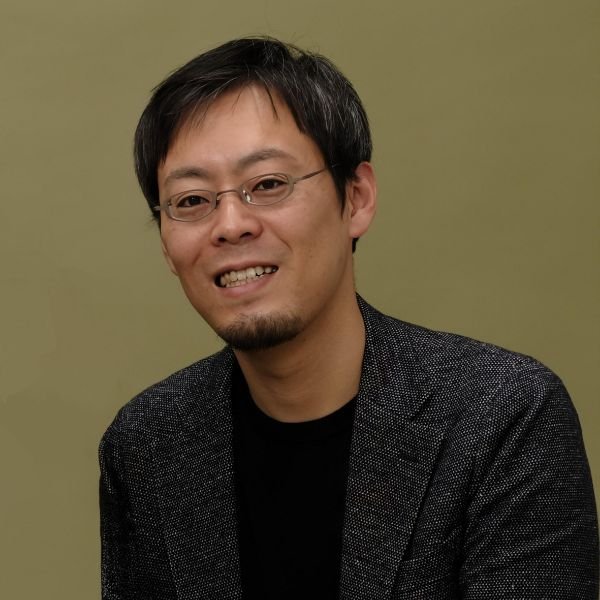クールジャパン2.0×地域研究-越境と摩擦の時代に-
2026.0202
この頃、世界に流行るもの
日本発の多様な文化が世界で広く人気を博している――という話を、この数年で耳にすることが増えた。もともと漫画やアニメの人気は高かったが、加えて食や音楽、デザインなども注目されている。2025年には、この現象を扱ったNHKシリーズ「新ジャポニズム」が放送を開始しており、同年5月からは日経クロストレンドも「JAPANエンタメ世界進出分析」と題した特集を組んで、日本発ポップカルチャーの世界的流行を論じている。慣れ親しんだ文化が、よその国でも人気だと聞くのは正直悪い気はしない。同時に、「本当にそうなのか?」と、これを訝しがる私がいることも確かである。特定の文化の優秀性を説く言説は、とかくナショナリズムをくすぐりがちである。そのため、これを過大に評価してしまったり、冷静な分析が妨げられてしまったりすることがあるので、気を付けなければいけない。
「敗北感」の払拭?
日本文化の広がりは、以前から繰り返し言われてきたことである。しかし、最近の動きがこれまでとは少し違って見えるのは気のせいだろうか。2000年代に入り、世界的にソフト・パワーの重要性が叫ばれるようになった。すると、日本でもこれを高めようとする機運が高まった。イギリスのクールブリタニアをもじったクールジャパン政策が立案され、文化を海外へと積極的に輸出・発信しようとする動きが進んだ。とはいえ、その後はK-POPを中心とした韓国文化(いわゆる韓流)が世界を席捲するなかで、日本は韓国の後塵を拝したという印象が強い。実際、関連する文献を見てみても、韓国の「成功」を紹介・分析したものが多いのに対して、日本のソフト・パワー政策を好意的に評した研究というのは少ない。それが、コロナ禍を挟んでからは、以前感じた「敗北感」のようなものが薄れてきたように思われるのである。
クールジャパン政策の「リブート(再起動)」
背景には、コロナ禍後に起きた経済の「回復」が少なからず関係している。2023年10月以降は、訪日外国人がコロナ禍前を上回る水準となり、またエンタメ・コンテンツ産業の成長も顕著である。2023年には海外のアニメ市場が、国内を上回る約1兆7,200億円規模に達し、翌年にはそこからさらに年率26%もの成長を記録した。すると、2024年6月には内閣府知的財産戦略推進事務局が、クールジャパン政策の「リブート(再起動)」を掲げ、2033年までに関連産業の海外展開規模を50兆円まで増やすことを宣言した。さらに、2025年6月に経済産業省も「エンタメ・クリエイティブ産業戦略-コンテンツ産業の海外売上高20兆円に向けた5ヵ年アクションプラン-」を発表し、日本を世界一の「エンタメ大国」に押し上げるという目標を掲げた。つまり、コロナ禍後に言われるようになった「クールジャパン2.0」は経済的な裏打ちがあり、それが自信につながっているのだと言える。
コンテンツ発信の舞台裏で
もっとも、日本と他国との垣根が低下するなかで、問題も起きやすくなっている。とくにエンタメ・コンテンツ分野を考えてみた場合、作り手側が意図せぬ摩擦や炎上を気にしながら制作を進めなくてはいけないという状況が生じた。よく引き合いに出されるのは人気漫画『ジョジョの奇妙な冒険』のアニメ版で起きた炎上である。作中、悪役が主人公の抹殺を部下に命じる場面で、イスラームの聖典クルアーンを手にしていることが問題視された。海外輸出を前提につくられたものではなかったが、海賊版が海外で出回るなかでこれが「発見」されて炎上した。アニメ化の際に、スタッフがアラビア語の本を見本にしようと、クルアーンを転写してしまったことで起きたようだ。とまれ炎上の結果、制作側は謝罪に追い込まれ、作品の自主回収を余儀なくされた。似たようなケースは、日本のみならず世界各地でしばしば起きている。
逆もある。例えば、2025年2月にはフランスのゲーム会社Ubisoftが制作した『アサシン クリード シャドウズ』の作中、主人公が実在の神社を破壊するシーンが問題となり、翌月にはこの話題が国会答弁にまで及んだ。作品の回収がなされることはなかったが、御神体の破壊ができないように一部修正が加えられた。国同士の垣根が下がることで、大きなビジネスチャンスが生まれる。同時に、意図せぬ炎上や摩擦も起きやすくなっている。そのため、作り手側は防げる炎上・摩擦ならば、できるだけ避けたいと思う一方で、行き過ぎた忖度は、作品自体を台無しにしてしまうという難題を抱える。では、こうした問題をどのように解決していけるのだろうか。具体的に、どのような対策がとられているのであろうか。
ローカル化戦略とその限界
処方箋として提示されることが多いのは、ローカル化戦略である――あるいは、社会学者ローランド・ロバートソンの言葉を借りればグローカリゼーションと呼ぶほうが適当かもしれない。製品やサービス、コンテンツ等を現地の宗教、文化、習俗、嗜好に合わせる現地化戦略のことで、例えばマクドナルドの月見バーガーや、スターバックスのほうじ茶ラテなどが分かりやすい。こうした戦略は、単に嗜好の問題にとどまらない。筆者が専門としているイスラーム地域の場合、食分野で「ハラール認証」を取得することは企業にとって必須である。もっとも、これは食に限らず、エンタメ・コンテンツの分野にも当てはまる。すでに多くの企業は、作品輸出にあたってローカル化戦略をとり、現地の事情に合わせて内容を一部修正したり、削除したりしている。また最近では、そうしたことを専門に扱う現地の企業も育っている。原作を大事にしつつも、できるところは修正するという姿勢が欠かせないように思う。
しかし、ローカル化をすれば解決するかと言えば、そうではない。先の『ジョジョ』のケースを取り上げてみると、問題の背後には製作者側(とくにアニメ化した際のスタッフ)の知識不足がある。そして、それが国内では気づかれず、海外で見つかり炎上してしまった。またローカル化の過程で問題が起きてしまったケースも過去に見られる。具体的には、2014年にマレーシア政府が『ウルトラマン』のマレー語版コミックを発禁処分にした事件であるが、これは翻訳の過程でウルトラマンが神(アッラー)になぞらえられてしまったことで起きてしまった――翻訳側の分かりやすくしようとする配慮が裏目に出てしまったかたちだ。国同士の垣根が低くなるなかで、作品が輸出されるか否かにかかわらず、作り手側がますます注意を求められる時代になっている。当然、作り手にとっては難しい時代になったと言わざるを得ないが、状況が単純に好転していくとは考えにくい。
地域研究者にできること?
こうした状況に対して、地域研究の知見というのは案外役に立つのではないか、ということを最近考えるようになった。例えば、私の専門であるメディアとイスラームとの関係を考えてみた場合、地域研究の視点から見えてくることは少なくない。例えば、筆者は以前、メタバースとイスラームについての論考(こちら)を著したが、そのなかでアバターについて触れた。アバターという言葉は、もともと神仏の化身を表すサンスクリット語のアバターラ(avatāra)に由来している。では、イスラーム地域でアバターが「偶像崇拝」とみなされるかと言えば、そうではない。むしろアバターやアバターという用語自体が、ほとんど摩擦なく使われていることが分かる。スクリーンに描かれる図像自体が、映画やテレビ時代の到来とともに、すでに当たり前のものとなっているため、特段アバターだけが問題視されることはない。また、何が禁止され、どこまでが許容されるかの境界も、時代によって少なからず変わる。つまり、何が、どこまでが現地で問題視/許容されるかの見極めは、これを集中的に見ていかなければ判断がなかなか難しい。だが専門家としては、聞かれたことに対しては、ある程度は答えることができる。基礎研究を進めることが、結果的に社会の摩擦回避につながるならば、それは望ましいことに違いない。クールジャパン2.0が進むなかで、地域研究者にできることは案外多いのではないかと考えている。

千葉 悠志 准教授
中東地域研究、メディア研究、国際関係論