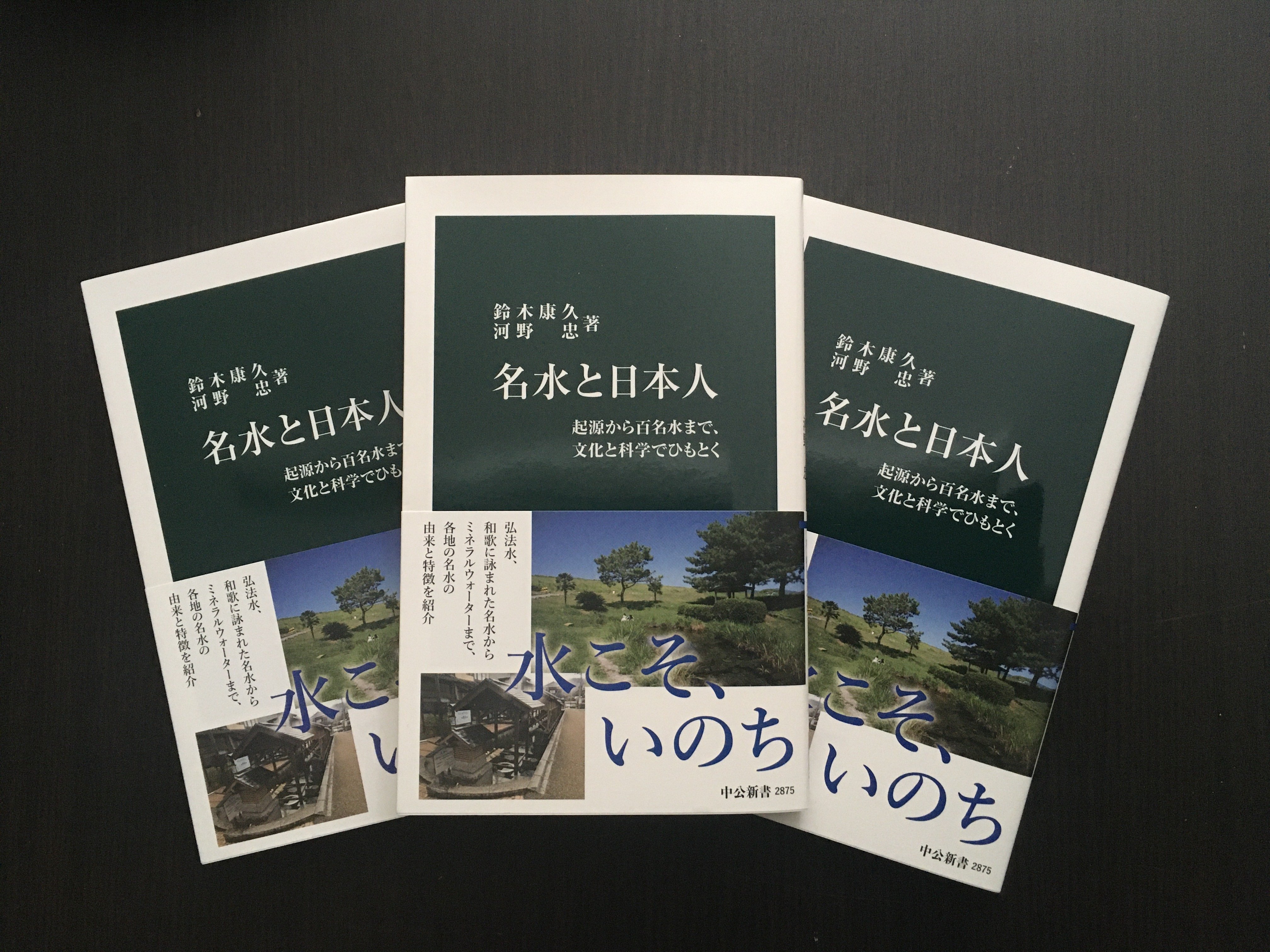
2025年9月19日、現代社会学部の鈴木康久 教授が執筆した『名水と日本人』(中公新書)が刊行されました。
本著は、名水が生まれた奈良時代から現代までの約300ヶ所の名水について、文化と科学の視点から紐解いています。本学部の鈴木教授が「序章 名水の変遷」「和歌の名水」「茶事の水」「民衆の水」「終章 名水の名付けの『謎をひもとく』」と「はじめに・あとがき」を、立正大学の河野忠教授(現在 本学客員研究員)が「古事記等が伝える水」「人物ゆかり・宗教の水」「生業の水」「水質が生みだした名水」「自然環境と共存する巧みな水利用」を執筆しています。
裏面の添え書きに「水が日本の社会と文化、産業を育んだ」とあるように、日本人と縁が深い水について、「名水」をキーワードに日本人と水との関わりを説明しています。その内容は、弘法大師の水伝承が全国に広がった理由や、歌枕になった名水、茶の名水、酒造りの水など、それぞれの時代における社会変化の中で生まれてきた名水について解説しています。
さらには、美人水や害虫駆除の泉など水質と関係する名水の他、「まいまいず井戸」などの巧みな水利用についても紹介しています。
日本各地の名水を訊ねてみたい、名水の名付けの理由を知りたい思う方々だけなく、日本人と水との関わりについて興味のある方々も読んでみたいと思う一冊になっています。




