今春学期に「国際キャリア開発リサーチ(CDR)C-1」を履修し、マレーシアでの企業実習に参加しました。本科目は、事前授業・現地実習・事後授業の3つのステップを通じて、国際ビジネスの現場を学ぶことを目的としています。事前に国内で企業や公的機関を訪問して基礎的な理解を深め、現地での実習を経験し、その後に学びを整理・発表する流れで進められました。 (国際関係学部 3年 山崎由良、橋本菜々聖)

事前学習では、受け入れ企業であるナベルの京都本社での研修やマレーシア投資開発庁(MIDA)大阪の訪問を行いました。これらの経験は、現地での学びを深めるための基盤となり、企業活動や国際展開を多角的に理解する貴重な機会となりました。
ナベル本社では、事業説明や工場見学を通じて洗卵・選別・包装といった同社の機械が提供する工程を学びました。高度な技術や徹底した品質管理に触れたことで、単に優れた機械を製造するだけでなく、感染症対策や国ごとの衛生基準への対応、迅速なメンテナンス体制といった製造工程以外での工夫が、顧客からの「信頼」を得ているということを理解しました。
また、営業部の方々からは、海外営業の流れや顧客ニーズに合わせたオーダーメイド対応の重要性について学びました。製品の訴求ポイントを整理するワークショップを通じて営業の戦略的思考や柔軟な対応力を体感できたことも大きな学びとなりました。
MIDA大阪では、アズィッズ副所長からマレーシアの投資環境や産業構造について伺いました。日本からの直接投資額が近年増加し、多くの日系企業が進出している実態に驚かされました。さらに、税制優遇やインセンティブが外国企業の進出を後押ししている一方で、賃金格差や文化の違いといった課題もマレーシア国内にあることを知り、国際展開には多角的な視点が不可欠であると考えました。MIDA大阪の訪問を通じて、マレーシアの産業構造や制度への理解を深めると同時に、日本企業が海外進出する際に必要となる視点について改めて考えるきっかけになりました。

このように、事前授業を通じて企業活動の現場とマレーシアの産業環境を理解し、現地実習に向けて「日本企業の強みをどのように国際的に展開できるか」という課題意識を持つことができました。
マレーシアでの実習は、1週目は営業部、2週目は製造部の作業を中心に体験させて頂きました。営業部門では、ユーザーの元へ実際にお話をしに行き、同社製品への改善点や意見などを伺う営業に同行をさせて頂きました。私たちが伺った農場では競合他社の製品も同時に扱っている農場で、自社製品の強みを比較しやすい環境で学ぶことが出来ました。ユーザーの方や社員の方々と昼食を一緒にとらせていただき、マレーシアの文化や生活についてのお話も伺いました。また、見積書作成などの事務的な作業も体験させて頂き、製品が受注されるまでの流れを理解することが出来ました。製造部門では、現地のスタッフの方々のサポートのもとで、実際にフレームの組み立てを体験させて頂きました。製品の構造を簡潔に知ることが出来るため、販売戦略を立てる上で必要な強みや弱みを適切に理解することに繋がりました。

週末にはクアラルンプールに移動し、JETROクアラルンプール事務所訪問や、クアラルンプール市内での日本ビジネスの市場調査を行いました。JETRO訪問では、マレーシアの基本情報を始めとする経済の特徴やビジネスの最新動向を教えて頂きました。1週間マレーシアに滞在したうえで発見した疑問にも答えていただき、2週目の活動に活かすことが出来ました。クアラルンプール市内の市場調査では、現地にローカライズされた日本食を実際に食べてみたり、日系のスーパーマーケットやユニクロ、無印良品などを訪れ、現地と日本での人気商品の違いや価格帯、生産地の違いなどについて調査しました。調査結果から、ASEAN経済域内での日系ビジネスの強みを実感しました。

事後学習では再びナベル本社を訪問し、最終プレゼンテーションを行いました。履修者の二人で協力し、事前学習やマレーシアでの実習を振り返りながら「東南アジア市場における今後の販売戦略の立案」をテーマに、ナベルと競合他社を分析し、比較優位を生み出す施策を提案しました。発表後には、南部副社長をはじめ社員の方々から具体的なフィードバックをいただき、意見交換を通じて実践的な視点を学ぶことができました。この経験は、学びを深めるだけでなく、今後の研究やキャリア形成に生かせる貴重な機会となりました。

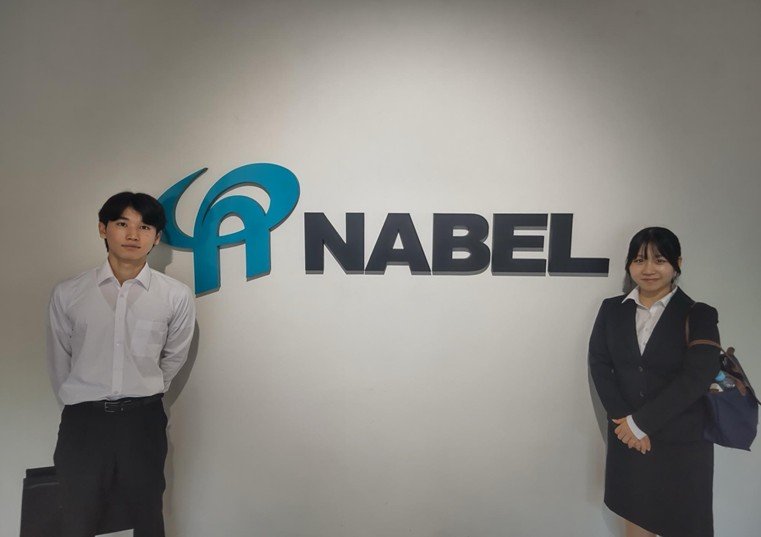
最後になりましたが、貴重な実習経験を提供してくれましたナベルの皆さまにこの場を借りて厚くお礼申し上げます。
ナベルのHP
https://nabel.co.jp/




