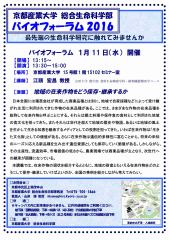総合生命科学部 バイオフォーラム2016開催(2017年1月11日)
2016.12.19
最先端の生命科学研究に触れてみませんか
江頭 宏昌 教授(山形大学 農学部 食料生命環境学科・植物機能開発学コース)
「地域の在来作物をどう保存・継承するか」
日本全国には種苗会社が育成した商業品種とは別に、地域で自家採種などによって受け継がれ生活に利用されてきた作物の在来品種がある。ここでは、さまざまな作物の在来品種を総称して在来作物と呼ぶことにする。それらは郷土料理や保存食の食材として利用され地域の食文化を担ってきた。またそれらは世代を超えて地域の歴史や物語、あるいは地域の風土を生かして生きる知恵を継承するメディアとしての役割を担ってきた。いわば在来作物は「生きた文化財」としての価値がある。さらに在来作物は遺伝的多様性に富むことから、将来の未知のニーズに応える新品種を生み出す遺伝資源としても保存していく価値がある。しかしながら、その生産性、流通効率、市場価値の低さから、農業現場では商業品種が主となり、次世代への継承が困難になっている。
本講義では、在来作物の現状を紹介するとともに、地域の財産ともいえる在来作物をどのようにして保存・継承していけばよいのか、全国の事例を紹介しながら考えてみたい。
| 日時 | 2017年1月11日(水) 13:30~15:00(13:15開場) |
|---|---|
| 場所 | 京都産業大学 15号館1階15102セミナー室 |
| 交通 | ※キャンパス内に駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。 交通アクセス |
| 備考 | 事前申込不要・入場無料・一般の方の参加歓迎 |
| 主催 | 京都産業大学 総合生命科学部 |
講師プロフィール

江頭 宏昌 教授(山形大学 農学部 食料生命環境学科・植物機能開発学コース)
1964年福岡県北九州市生まれ。1990年京都大学大学院農学研究科修了。同年に山形大学農学部助手。2001年より助教授、2015年より現職。農学博士。専門は植物遺伝資源学。「野菜の在来品種は生きた文化財であり、その保存が急務である」という故・青葉高博士の考えに共鳴し、山形県内外の在来作物の研究や保存活動などに積極的に取組んでいる。山形在来作物研究会会長、エダマメ研究会代表。
1964年福岡県北九州市生まれ。1990年京都大学大学院農学研究科修了。同年に山形大学農学部助手。2001年より助教授、2015年より現職。農学博士。専門は植物遺伝資源学。「野菜の在来品種は生きた文化財であり、その保存が急務である」という故・青葉高博士の考えに共鳴し、山形県内外の在来作物の研究や保存活動などに積極的に取組んでいる。山形在来作物研究会会長、エダマメ研究会代表。
<主な著書など>
「どこかの畑の片すみで」(共著、山形大学出版会、2007)
「伝統食の未来」(共著、ドメス出版、2009)
「おしゃべりな畑」(共著、山形大学出版会、2010)
「ユーラシア農耕史第5巻 農耕の変遷と環境問題」
(共著、臨川書店、2010)
「焼畑の環境学」(共著、思文閣、2011)
「火と食」(共著、ドメス出版、2012)
「種から種へつなぐ」(共著、創森社、2013)など。
「人間と作物」(編著、ドメス出版、2016)
山形在来作物研究会HP :zaisakuken.jp
山形在来作物研究会は2010年に第1回辻静雄食文化賞をいただきました。
また同研究会は2015年には鶴岡市教育・文化功労部門で特別表彰されました。
「どこかの畑の片すみで」(共著、山形大学出版会、2007)
「伝統食の未来」(共著、ドメス出版、2009)
「おしゃべりな畑」(共著、山形大学出版会、2010)
「ユーラシア農耕史第5巻 農耕の変遷と環境問題」
(共著、臨川書店、2010)
「焼畑の環境学」(共著、思文閣、2011)
「火と食」(共著、ドメス出版、2012)
「種から種へつなぐ」(共著、創森社、2013)など。
「人間と作物」(編著、ドメス出版、2016)
山形在来作物研究会HP :zaisakuken.jp
山形在来作物研究会は2010年に第1回辻静雄食文化賞をいただきました。
また同研究会は2015年には鶴岡市教育・文化功労部門で特別表彰されました。