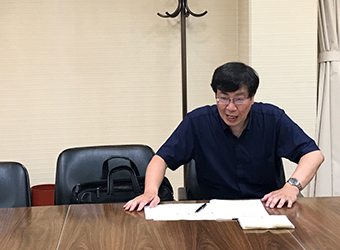ロシアの市民像と日本への影響
| 報告者 | 河原地英武(本学外国語学部教授) |
|---|---|
| 開催場所 | 京都産業大学 第二研究室棟 会議室 |
| 開催日時 | 2017年6月28日(水)15:00~16:30 |
発表概要
はじめに
本報告では、ロシアにおける市民像および思想と、その反映としての文学に焦点を当てることで、それらが明治から大正にかけて日本においてどのように受容され、どのような行動として表出されたのかを考察する。
ロシアの市民像
ロシアのミール(農村共同体)には、農地の共同所有形態を資本主義に対する防壁として積極的に評価する保守性(スラブ派)と、ミールの存在ゆえに資本主義の経過を経ずして直接的に社会主義への移行が可能であったと積極的に評価する革命性(左翼ナロードニキ)という二面性があった。
1840年代には、正教を文明の基礎とし、呪われた西欧の模倣は根絶すべしというスラブ派と、ロシアの後進性を克服し、西欧諸国の列に伍さなければならないと主張する西欧派へと分かれる。1860年以降にはツルゲーネフの『父と子』(1862)で用いられた「ニヒリスト」が流行し、貴族階級に対する父親世代を否定し、行動する若者の理想となった。1870年以降には、ナロードニキ(人民主義者)がミールを通した社会主義運動を展開するが、厳しい取り締まりにより、一部がテロリズムへ進むこととなる。
1840年代には、正教を文明の基礎とし、呪われた西欧の模倣は根絶すべしというスラブ派と、ロシアの後進性を克服し、西欧諸国の列に伍さなければならないと主張する西欧派へと分かれる。1860年以降にはツルゲーネフの『父と子』(1862)で用いられた「ニヒリスト」が流行し、貴族階級に対する父親世代を否定し、行動する若者の理想となった。1870年以降には、ナロードニキ(人民主義者)がミールを通した社会主義運動を展開するが、厳しい取り締まりにより、一部がテロリズムへ進むこととなる。
革命思想
ロシアの革命思想は、いわばマルクス主義に対する形で、アナーキズム(無政府主義)、サンジカリズム(労働組合主義)、ボリシェヴィズム(多数派主義)、ニヒリズム(虚無主義)が生まれてきた。特に、ニヒリズムに関しては、『父と子』以降、その意味が変質し、ニヒリストはしばしばテロリストと同義で用いられることとなった。
これらの思想が、ロープシン『蒼ざめた馬』『テロリスト群像』、ドストエフスキー『悪霊』といった文学作品の題材となっている。
これらの思想が、ロープシン『蒼ざめた馬』『テロリスト群像』、ドストエフスキー『悪霊』といった文学作品の題材となっている。
日本における受容
日本においては、武者小路実篤のトルストイへの傾倒、幸徳秋水・大杉栄によるクロポトキンの研究などが見られる。1910年以降では、大逆事件、原敬暗殺事件、安田善次郎暗殺事件、二重橋爆弾事件、虎ノ門事件、朴烈事件、福田大将狙撃事件、「ギロチン社」事件など、ニヒリズムの表れとしてのテロリズムが起こっている。
テロリズムの考察
日本の文学においては、秋山清『ニヒルとテロル』、石川啄木『ココアのひと匙』(われは知る、テロリストのかなしき心を)、梶井基次郎『檸檬』(丸善の棚へ黄金色に輝く恐ろしい爆弾・・・大爆発をするのだつたらどんない面白いだらう。)など、テロリズムの美化、あるいはシンパシーがしばしば見られる。
今後の課題
しかし、幕末・維新のテロリスト(佐久間象山、大村益次郎、本間清一郎、坂本龍馬、中岡慎太郎など)と大正のテロリストを一続きとしてみれば、ロシアとは別の日本独自のテロリズムの系譜があると思われ、その点についての考察が必要になってくる。