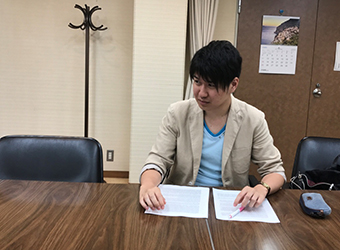開発史と抽象化される開発の行方-ユネスコの役割
| 報告者 | 中岡大記(本学法学研究科博士後期課程・世界問題研究所研究補助員) |
|---|---|
| 開催場所 | 京都産業大学 第二研究室棟 会議室 |
| 開催日時 | 2017年5月24日(水)16:30~18:00 |
発表概要
はじめに
ユネスコは主として教育を領域とする活動を行う国連の専門機関であるが、日本では世界遺産など文化面に対する注目度が高い。それでは、教育分野を専門とする機関としてのユネスコは国連の中でどのような役割を担っているのか。これまでの開発の歴史を振り返ることで現在の開発がどのような状況にあるのかを説明し、その中で、ユネスコが置かれている立場を同定し、求められている役割を考察する。
開発援助の歴史
第二次世界大戦後の援助は、1947年のマーシャルプランに代表されるように、戦争で疲弊したヨーロッパに対して、アメリカが支援を行ったことから始まった。その後、1949年には国連で途上国の支援を目的とする拡大技術援助計画が設置された。1960年代に入ると、世界銀行の国際開発協会やOECDのDAC、アメリカ開発庁、日本の国際協力機構、イギリス海外開発省、国連開発計画(UNDP)など、現在にまで続く援助機関が次々と設立された。
これまで「近代化論」「成長段階論」「ビッグ・プッシュ」「トリクルダウン」といった、量的な援助によって国家の経済成長を押し上げるという見解が支配的であった。確かにある程度の経済成長は達成されたものの、途上国内での貧富の格差は拡大し、1970年代に入っても、それは改善されなかった。そこで「ベーシック・ヒューマン・ニーズ(BHN)」「新路線(New Directions)」「成長に伴う再分配」といった、貧困層を重視した考え方が各機関から提唱されるようになった。
ところが、ニクソンショックやオイルショックなどが起こったことによって、途上国の経済状況は悪化した。そこで世界銀行および国際通貨基金は構造調整融資によって切り抜けようとするが、途上国において成果を残すことは出来なかった。90年代に入ると国家中心の開発からより個人に焦点を当てた「人間開発」という概念が登場するとともに、途上国が発展しない原因を政治的要因に求め「ガバナンス指標」や「良い統治」といった概念が提唱され、現在にいたるまで支配的な考えを成している。2000年にはミレニアム開発目標(MDGs)や2015年には持続可能な開発目標(SDGs)が国連で合意された。
これまで「近代化論」「成長段階論」「ビッグ・プッシュ」「トリクルダウン」といった、量的な援助によって国家の経済成長を押し上げるという見解が支配的であった。確かにある程度の経済成長は達成されたものの、途上国内での貧富の格差は拡大し、1970年代に入っても、それは改善されなかった。そこで「ベーシック・ヒューマン・ニーズ(BHN)」「新路線(New Directions)」「成長に伴う再分配」といった、貧困層を重視した考え方が各機関から提唱されるようになった。
ところが、ニクソンショックやオイルショックなどが起こったことによって、途上国の経済状況は悪化した。そこで世界銀行および国際通貨基金は構造調整融資によって切り抜けようとするが、途上国において成果を残すことは出来なかった。90年代に入ると国家中心の開発からより個人に焦点を当てた「人間開発」という概念が登場するとともに、途上国が発展しない原因を政治的要因に求め「ガバナンス指標」や「良い統治」といった概念が提唱され、現在にいたるまで支配的な考えを成している。2000年にはミレニアム開発目標(MDGs)や2015年には持続可能な開発目標(SDGs)が国連で合意された。
開発における教育
これまで教育は開発のための手段すなわち「人的資本」として、あるいは、教育それ自体が人間の権利であるとして考えられてきた。前者の考え方が無くなったわけではないが、1990年に「万人のための教育(Education for All)」が国際的なコンセンサスを得て、教育は万人にとっての基本的な権利であることが再確認された。その後、2000年、2015年にも教育に関する世界会議が開催され、その目標がMDGsやSDGsにも反映されるなど、教育という独立した分野であると同時に、様々な分野のひとつとして学際的な取組が求められている。
考察と今後の課題
途上国の教育に関しては、ユネスコが専門的に行っているが、UNDP、世界銀行、ユニセフも取り組んでいる。「万人のための教育」が合意に至って以降、MDGsにもみられるように基礎教育への関心が高まっている。
その中で、UNDPは教育への予算拠出規模を減少させており、相対的に残りの3機関の役割は高まっている。一方で、ユネスコは、4つの機関の中で最も予算が少なく、近年では、アメリカとパレスチナ、日本と中国の政治問題によって、予算の拠出自体がスムーズに行われていない、非常に小規模な機関である。ユニセフは教育分野へ進出して以来、子供への教育政策を行っており、世界銀行も基礎教育への融資の割合を高めてきている。すなわちユネスコは、専門機関としての独自性の相対的低下がみられるとともに、政治問題にも対処していかなければならない状態にある。しかし、2009年以降、ユネスコの役割(mandate)を見極める一環として「包括的、戦略的かつ将来志向の」独立外部評価制度を取り入れ、自らの役割に対するチェックシステムを強化している。
今後は、より具体的な政策から、ユネスコに求められる独自性を検証していくことが求められる。
その中で、UNDPは教育への予算拠出規模を減少させており、相対的に残りの3機関の役割は高まっている。一方で、ユネスコは、4つの機関の中で最も予算が少なく、近年では、アメリカとパレスチナ、日本と中国の政治問題によって、予算の拠出自体がスムーズに行われていない、非常に小規模な機関である。ユニセフは教育分野へ進出して以来、子供への教育政策を行っており、世界銀行も基礎教育への融資の割合を高めてきている。すなわちユネスコは、専門機関としての独自性の相対的低下がみられるとともに、政治問題にも対処していかなければならない状態にある。しかし、2009年以降、ユネスコの役割(mandate)を見極める一環として「包括的、戦略的かつ将来志向の」独立外部評価制度を取り入れ、自らの役割に対するチェックシステムを強化している。
今後は、より具体的な政策から、ユネスコに求められる独自性を検証していくことが求められる。