2025年度春学期人権教育啓発講演会 河野 美江氏(島根大学 松江保健管理センター センター長/副学長(SDGs、ダイバーシティー担当)がオンラインで講演
京都産業大学では、人権教育の取り組みや人権啓発を目的に、人権問題に関わる様々な事柄について、知り考える機会として、「人権教育啓発講演会」を年2回開催しています。
6月25日(水)は、島根大学 松江保健管理センター センター長/副学長(SDGs、ダイバーシティー担当)である河野 美江氏を講師に迎え、「大学における性暴力への対応~被害者支援から予防まで~」と題して講演会が開催されました。
講師は、島根大学で教鞭を執られ、副学長としてSDGsやダイバーシティ推進に取り組まれています。また、性暴力被害者支援にも長年携わり、地域社会への貢献も続けておられるなど、幅広い分野で活躍されています。
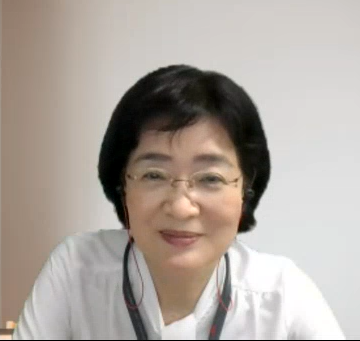
講演では、性暴力に関する基礎知識や大学における現状、被害者支援や予防教育について豊富な知見と実践に基づきお話しいただきました。
性暴力とは
河野氏は、性暴力とは、「本人が望まない性的な行為はすべて性暴力」であると定義し、そのうち、刑法において性犯罪とされるものは、「不同意性交罪」や「不同意わいせつ罪」など、法的な構成要件を満たす行為であると説明されました。
悪いのは同意なく強要する加害者であって、「被害を受けた人は、何も悪くない」と強調されました。
性的同意とレイプ神話の誤解
性的同意とは単に「嫌と言わなかった」ことではなく、自由で対等な関係の中で、恐怖や圧力なく、自分の意思で選択できる状況での合意であり、同意は一度得られたからといって継続的に有効なものではなく、毎回確認されるべきものであるとされます。
性暴力は、被害者の意思に反して行われる深刻な人権侵害であり、身体的・精神的に大きな影響を及ぼします。しかし、こうした被害に対して、社会にはいまだに誤った認識や偏見が根強く残っています。
その代表的なものが「レイプ神話」と呼ばれる考え方です。実際には顔見知りの間で起こっているにも関わらず「加害者は見知らぬ人」「被害者の服装が原因」といった誤った認識が広く信じられています。
性暴力被害を受けた学生への支援
大学生の性暴力被害の実態について、日本と欧米の調査結果をもとに紹介されました。
米国の研究では、被害者が大学の公式機関に支援を求めることは少なく、友人や家族など非公式に相談先を選ぶ傾向があることが報告されています。
その背景には、「それほど重要ではない」と被害を最小化する心理や、他の人に知られたくないという心理、二次被害への不安、アルコールの使用、知識の不足など、さまざまな要因があるとされます。
性暴力の被害を受けた人は、自分の選択権を奪われ、深く傷つき、様々な感情に苦しみます。被害者が「自分で選び、決めること」が回復の第一歩です。支援者は被害者に対して選択肢を提示し、本人が自分の意思で対応を決められるよう支援することの重要性が説明されました。
具体的な支援内容としては、以下のような対応が挙げられました。
1.産婦人科での対応 2.精神面への対応 3.警察への連絡 4.家族・友人への対応 5.法的支援
また、ワンストップ支援センターの紹介がありました。
※ワンストップ支援センターでは、産婦人科診察や弁護士対応、カウンセリングなどが受けられ、警察や病院などへの付き添い支援なども行っています。
◆学生支援機関でできること
教職員やカウンセラーは、被害を受けた学生の心身のケアを行うとともに、必要に応じて専門機関へつなぐコーディネーターの役割が求められます。
1.安全の確認と再被害の防止:学生が安全な環境にいるかを確認し、再被害の危険があれば、警察への相談を勧めるなど
2.生活状況の把握:睡眠や食事がとれているのか、身近に支えてくれる人がいるのかを確認する
3.情報提供:性被害を受けたときにできることについて、学生にわかりやすい言葉で丁寧に説明する
◆学生対応における留意事項
被害を受けた学生に対応する際には、安心で安全な場所を提供します。
1.安心・安全な空間の提供:できるだけ他の学生や教職員と顔を合わせないように配慮し、個室で話を聞く
2.支援者の性別への配慮:被害者が女性の場合、対応はできるだけ女性支援者が行うことが望ましいが、男性支援者の場合は女性支援者が同席する
3.同行者の同席確認:同行者がいる場合は、その人が同席したほうがいいかを必ず本人に確認し、決めてもらう。特にパートナーからDV被害が疑われる場合は、被害者のみから話を聞くようにする
◆困ったときは
被害にあった際に、まず何をすべきか、どこに相談すればよいかについても具体的なアドバイスがありました。「被害にあったあなたは悪くありません」というメッセージが繰り返し伝えられました。
1.安全な場所に移動する
2.できるだけ早くワンストップ支援センターや警察に相談する
3.医療機関を受診する
性暴力に対する予防教育
性暴力を未然に防ぐためには学生自身が正しい知識を持ち、危険な状況に気づき、適切に対応できる力を身につけることが重要です。大学で行える啓発活動として、性暴力に関する基礎知識の提供、危険な状況への注意喚起、第三者の介入方法の教育が紹介されました。
特に予防のポイントの一つとして、飲み物への薬物混入などの事例を紹介し、飲み物から目を離さない、信頼できない相手から渡された飲食物は口にしないなどの行動が紹介されました。
最後に
「私たちみんなで、性暴力のない、社会にしていきましょう」と締めくくられました。
性暴力は、被害者が心身ともに深く傷つき、加害者も今後の人生を大きく狂わせることになるため、被害が起こらないよう事前に予防していく必要があります。この講演会では、その為の知識や対応をわかりやすく解説いただき、その理解を深める貴重な機会となりました。
その他
講演では、性暴力に関する支援情報として、以下のリソースが紹介されました。
大学生のための性暴力救援サイト
https://nosvva.net/forStaff/
性暴力に関する基礎知識や相談窓口など、学生・教職員向けの情報が掲載されています。
大学における性暴力被害学生支援マニュアル(PDF)
https://nosvva.net/forStaff/book2.pdf
支援の具体的な方法や対応の流れが詳しく解説されています。
河野氏からは、これらの資料を積極的に活用してほしいとの呼びかけがありました。
人権センターでは、これからも人権教育啓発活動の一つとして講演会の取り組みを実施します。




