
ミクロな世界に広がる“無限の可能性”を求めて。
むすぶ人
理学部 4年次 老田 将大さん 理学部 4年次 小宮 良介さん 理学部 4年次 細野 翔大さん 理学研究科 1年次 深尾 一広さん 理学研究科 2年次 加納 慶流さん
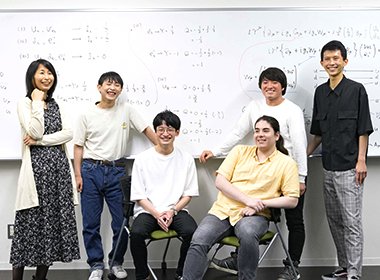
そもそも物理科学科とは何を学ぶ学科なのでしょうか?
老田さん:分子や原子など、目に見えないミクロな世界を探究していく学科です。例えば「水」は「水素原子」と「酸素原子」で構成されていますが、原子の中には「原子核」、原子核の中には「陽子」と「中性子」が存在し、さらにそれらはもっと小さな「素粒子」で構成されています。物質を構成する小さな単位に着目して、そのメカニズムを追究していく。それが今、私たちが研究室でやっていることです。
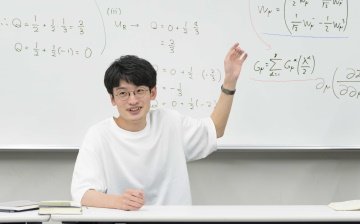
老田 将大さん
みなさんが所属する山縣淳子研究室のテーマは「ハドロンおよびハドロン多体系に関する理論研究」ですが、具体的にどんな内容ですか?
加納さん: 「ハドロン」は陽子や中性子の仲間。ハドロンが原子核に飛び込んだ時、原子核とハドロンの間にどんな力が働いているのか。これを理論的に調べるのが山縣先生の研究内容です。私たちもそれを軸に、各々が興味を持った現象について研究に取り組んでいます。
小宮さん: とはいえ、いきなり研究はハードルが高いので、まずは方程式を理解するところから。
細野さん: 授業で扱う本の内容も一度で理解するのは難しいから、1つずつ数式を解いていくしかないよね。研究室でも「場の量子論」という教科書の中から各々が問題を解いて、それぞれの考えを皆の前で解説して。
小宮さん: 例えば、私が解説したのはクォークとレプトンの方程式について。
細野さん: ハドロンを研究する上で基本となる素粒子ですね。レプトンくらいミクロだと普通の方程式では対応できないから、それこそ「場の量子論」を応用して頭が痛くなるような数式をひたすら解いていく感じかな。
深尾さん: それに対して全員で「ああでもない」「こうでもない」と言い合う。このディベート形式の授業は山縣研究室の特徴の1つだと思います。
老田さん: 90分の授業の間に4~5問しか進まないこともあれば、10問進むこともある。難易度によってペースも全然違いますよね。
小宮さん: 解説後に「そこちょっとおかしくない?」とつっこまれるとドキッとする(笑)。でもそうやって皆で考えながら、研究に必要なツールへの理解を深めています。
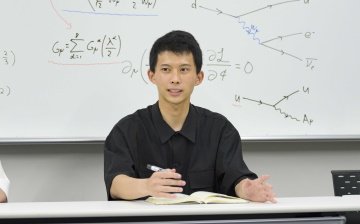
小宮 良介さん

深尾 一広さん

加納 慶流さん

細野 翔大さん
各自で取り組んでいる研究もあると思いますが、例えばどんなテーマですか?
加納さん: 原子核に「中間子」という別のハドロンをくっつけたら何が起こるのかを研究しています。
深尾さん: 超高密度天体である「中性子星」で起こっているかもしれない現象を再現してみるということですよね。
加納さん: そうそう。物理の世界では、結果を予想してから実験に移すのがセオリーなので、まずはそこから。数式を立てて、パソコンで計算して…という地道な作業を繰り返しています。
小宮さん: 理系ってトライアル&エラーが当たり前のイメージが強いけど、素粒子や原子核などの小さいものを対象にした分野は、実験にめちゃくちゃお金がかかりますもんね。
加納さん: 「ミスっちゃった」じゃシャレにならない。だから理論がとても重要なんです。

この分野を追究する醍醐味は?
小宮さん: 昔から計算が好きだったので、計算尽くしのこの分野はシンプルに楽しい。数学だと問題を解くことが目的ですが、物理だと計算の先に物理的な意味を見いだせるところが魅力ですね。
老田さん: 私にとっては「知りたい」という欲望を満たしてくれる学問です。身の回りのささいな現象に対して「なんで?」という疑問が芽生えたら、その根源にあるものを知りたくなるので。そういう話をしている時は、目が輝いていると言われます(笑)。
細野さん: ミクロな世界は、目に見えないからこそ未解明の謎が多く残されています。それを1つずつ紐解きながら、世界を構成する根源に迫っていく。小さな世界に膨大なロマンが詰まった興味深い分野だと思います。
※掲載内容は取材当時のものです。








