教員研究テーマ
すべての研究活動や研究成果に関する論文・著書・活動記録等については、「京都産業大学研究者データベース」を、参照してください。
(五十音順/2025年度在職者)
| 指導 教員 |
教員名 | 領域科目名 | 研究テーマ |
|---|---|---|---|
| ※ | 石川 登志雄 | 文化財 | 京都の社寺・文化財に関する研究 |
| ※ | 雲岡 梓 | 日本文学 | 日本の古典文学(近世文学)の研究 |
| ※ | 小林 一彦 | 日本文学 (リサーチプロファイル) |
日本の古典文学(和歌文学・中世文学)の研究 |
| ※ | 笹部 昌利 | 日本史学 | 幕末維新政治史の研究、日本近世・近代地域史の研究 |
| 高橋 早紀子 | 美術史学 | 仏教美術史(平安時代を中心とする日本彫刻史・密教美術史)の研究 | |
| ※ | 灘本 昌久 | 日本史学 | 日本近現代史、同和問題の歴史的研究 |
| 成田 智恵子 | 伝統工芸 | 京都の伝統工芸に関する研究 | |
| ※ | ペレッキア ディエゴ | 伝統芸能 | 伝統芸能に関する研究(演出、伝承、国際化などの諸相) |
| ※ | マレス エマニュエル | 庭園学 | 日本庭園の歴史的・比較研究/文化と自然の相互作用に関する研究 |
| ※ | 村上 忠喜 | 日本民俗学・文化財 | 祭礼文化を中心とした都市民俗研究/文化遺産研究 |
| ※ | 山本 雅和 | 日本考古学 | 平安京・京都の遺跡・歴史の研究 |
| ※ | 吉野 秋二 | 日本史学 | 日本古代都市(平安京)の研究、出土文字資料の研究 |
| ※ | 若松 正志 | 日本史学 | 近世の京都に関する研究、日本近世対外関係史研究 |
※印は研究指導教員を示します。
研究紹介
- 石川 登志雄 教授
- 雲岡 梓 准教授
- 小林 一彦 教授
- 笹部 昌利 准教授
- 下出 祐太郎 教授
- 灘本 昌久 教授
- ペレッキア ディエゴ 准教授
- マレス エマニュエル 准教授
- 村上 忠喜 教授
- 山本 雅和 教授
- 吉野 秋二 教授
- 若松 正志 教授
石川 登志雄 教授
京都の寺院文化財の調査及び管理と活用に関する研究
京都の寺院文化財の調査及び管理と活用に関する研究をしています。歴史的な史料は文化財として単に物理的に保存するだけではなく、詳細に調査し目録化しながら個々の史料を分析していくことで、歴史研究や文化研究の対象化することが重要です。 もう一つのテーマは、上記のようにして調査された古文書はもちろん、絵画・彫刻・工芸品・建造物など、質量ともに日本で断トツに膨大なボリュームを誇る京都の寺社資料(文化財)群について、いかにして総合的に管理するデジタルアーカイブシステムを構築するかの研究です。 現在は、おもに禅宗寺院東福寺・天橋立智恩寺、天台宗の門跡寺院妙法院・大原寂光院、真言宗門跡寺院大覚寺・六波羅蜜寺、浄土宗寺院檀王法林寺などの京都に所在する寺院の文化財を対象とした調査を行っています。2023年度は活動の成果をもとに東京・京都両国立博物館の特別展「東福寺」の開催に関わりました。絵画・彫刻・書跡・古文書・工芸品・建造物・石造物など、国宝・重要文化財を始めとするあらゆるジャンルの文化財を豊富に伝える京都の寺院の調査と管理は、歴史研究や諸種の活用の観点からではなく、将来きっと来るであろう大規模な災害に備えた文化財情報の保存と管理にとっても重要であろう思っています。
キーワード
- 京都の寺社文化史
- 文化財調査
- 文化財データベース
- 展覧会
- 東福寺
雲岡 梓 准教授
江戸時代の散文・連歌・女性作者の研究
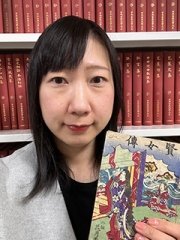
キーワード
- 江戸文学
- 荒木田麗女
- 連歌
- 女性作者
小林 一彦 教授
日本古典文学の文献学的書誌学研究
藤原道長にさかのぼる近衞家陽明文庫、藤原俊成・定家父子に発する歌の家・冷泉家時雨亭文庫などの貴重な典籍類の調査を通じて、信頼すべきテキストの有り様について、日夜、研究を深めています。『新編私家集大成CD-ROM版』や『冷泉家時雨亭叢書』などの大きな企画で編集委員をつとめるなど、日本の和歌研究のよりどころとなるテキストの整備と公開に、長らく携わってきました。
このほか、古典文学の注釈書や解説書の執筆にも取り組んでいます。日本人は何を美しいと感じ、自然に順応し日々の暮らしに取り入れてきたのか。日本人の美意識の形成に、古典作品を通して肉迫できないか、研究しています。

キーワード
- 書誌学
- 文献学
- 古典籍
- テキスト研究
- 古典文学研究
笹部 昌利 准教授
幕末維新政治史の研究

キーワード
- 幕末維新
- 明治維新
- 政治意思決定
- 歴史観
- 近代ナショナリズム
下出 祐太郎 教授
伝統工芸と近代産業ーものづくりの根幹と工業生産
伝統工芸は、生活に供する必需品を製造してきた歴史的経緯があります。現代の伝統工芸産業が担うべき生活に即した必需品について、調査を通して考察します。また、京都ならではの特殊性もその範疇に入れます。伝統工芸産業の特徴として、挙げることが出来るのは以下のとおりです。
- 天然材料を用い道具を使って手仕事で作っていくものづくりである
- 土地の環境や気候風土に依存し、環境を前提とした循環型産業である
- 長い伝統を有している
- つくり方には膨大な知恵や自然観・哲学に根ざした美意識が内包されている
- 作り手・使い手の文化でもあり、文化的な側面が強い
減衰し続ける伝統工芸がもつ技術と文化の重要性を、多方面から明らかにします。 伝統工芸産業の現代社会における立ち位置を明らかにします。その上での貢献を模索します。 近代産業との協働をさらに推し進めます。 京都ならではの特殊性については人も研究の対象とします。

キーワード
- 伝統工芸
- 漆芸
- 文化財
- 美意識
- 持続可能性
灘本 昌久 教授
日本近現代史、同和問題の歴史的研究

キーワード
- 日本史
- 現代史
- 同和問題
- 部落問題
- 人権
ペレッキア ディエゴ 准教授
京都の伝統芸能に関する研究(演出、伝承、国際化などの諸相)

キーワード
- 能楽
- 芸能
- 上演
- 演出
- パフォーマンス
マレス・エマニュエル 准教授
日本庭園の歴史的・比較研究
1,000年以上の長い歴史の中で培われた京の庭はいわゆる日本庭園の基盤となり、そして今となっては日本に限らず海外でも多くつくられています。しかし、違う環境と文化でつくっても日本庭園と言えるのでしょうか。日本庭園とは元々定義しにくい実体ではありましたが、グロバール化はその本質について再考するきっかけを与えてくれています。整形式の西洋庭園に対して、日本庭園は自然風景式だと簡単に片付けることが本当にできるのでしょうか。それぞれの歴史と文化を単純化せずに、相互理解を深めていく必要があります。
京都の庭を出発点に、自然と文化、生活と芸術、都市と地方、過去と現在、そして未来の地球のあり方にまで思いを巡らせて研究することができます。

キーワード
- 庭園
- 自然
- 文化
- 歴史
- 比較研究
村上 忠喜 教授
祭礼文化を中心とした都市民俗研究/文化遺産研究
私の専門領域は、日本民俗学です。日本民俗学といっても内容は多岐にわたりますが、私の場合は、「祭礼文化を中心とした都市民俗研究と文化遺産研究」です。なかでも最近は特に、京都祇園祭の山鉾行事の主催団体や伝承組織の研究を手掛けております。同時に、無形文化遺産の保護制度と実際との間の乖離や課題、また無形文化遺産の記録保存の手法の検討について共同研究などを通して、国内外の研究者や文化遺産担当者と意見交換をしています。また全国の山・鉾・屋台を伴う祭礼行事も視野に入れ、大型都市祭礼の伝承組織の現在についての研究を手掛けています。
民俗学の研究は、フィールドワークで得られた知識や感覚を大事にします。そういう意味では、もっぱら郵送によるレポートのやり取りが主であったこれまでの通信制による教育では、なかなか難しいものがありました。しかしながら、オンラインによる対話が可能になった現在、遠隔地であっても、否、遠隔地であるからゆえの異なる実情を紹介しあう、実感を伴った比較研究も可能になりました。便利な世になったものです。さまざまなツールを使って、実感の伴った民俗学の学びを経験してください。
キーワード
- 都市民俗
- 祭礼文化
- 無形文化遺産
- 映像記録の手法
- 文化財保護制度
山本 雅和 教授
平安京・京都の遺跡・歴史の研究
さて、「千年の都」と称される京都のイメージとして、まず、平安時代の貴族の雅やかな暮らし、あるいは桃山時代に花開いた豪華絢爛な文化を思い浮かべる皆さんが多いのではないでしょうか? 考古学は文字の記録がない旧石器・縄文時代から近代までが研究の対象です。そして遺跡や出土遺物から文献や絵画にはのこされていない人々の営みを明らかにすることができ、時には一般的なイメージを書き換える発見もある感動が多い学問です。そのためには緻密な調査・観察、詳細な記録、資料の集成、それらから導き出すことができる「ひらめき」が必要です。平安京・京都についての興味・関心は尽きることがありません。

キーワード
- 日本考古学
- 平安京
- 京都
- 都市史
吉野 秋二 教授
日本古代都市(平安京)の研究、出土文字資料の研究
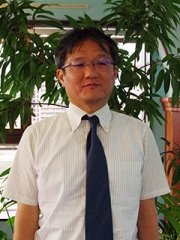
キーワード
- 古代都市
- 平安京
- 出土文字資料
- 地域史
- 食生活史
若松 正志 教授
近世の京都に関する研究、日本近世対外関係史研究
近世(信長・秀吉の時代から幕末まで)の京都や長崎を中心に、日本の歴史や社会・文化について、史料(くずし字で書かれたものを含む)を基礎に、データベースなども活用し、研究しています。
近世とくに江戸時代の京都については、イメージがわきにくい人もいるかもしれませんが、近世初期や幕末は政治的にも重要な場所でしたし、江戸時代を通して、経済や文化も栄えていました。そのような京都について、朝廷(天皇・親王・公家)や産業(観光・商業・モノづくり)を中心に、研究しています。
長崎については、江戸幕府の政策、「鎖国」、貿易の変遷、長崎奉行、都市の構造、町人の活動・生活、さらには貿易と国内経済・産業との関わりなどについて、研究を進めてきています。
このほか、歴史教育や日本の地域性、食文化、現代社会の問題にも関心をもっています。
本研究科では、中世後期から近代前期までの日本史分野(政治・経済・文化)で研究する大学院生を、指導しています。

キーワード
- 朝廷
- 親王
- 文化
- 長崎
- 都市




