文化学部京都文化学科の「京都文化基礎演習A」(担当:吉野 秋二 教授、受講生12人)では、京都市左京区の平安神宮および周辺地域の踏査を行いました。
踏査に先立ち、事前学習を実施しました。踏査予定地ごとに担当する学生を分け、関連書籍などを調査し、庭園や建築様式など岡崎・白川地域における文化遺産の特色について考察を行いました。調査結果はスライドやレジュメにまとめ、発表を行いました。
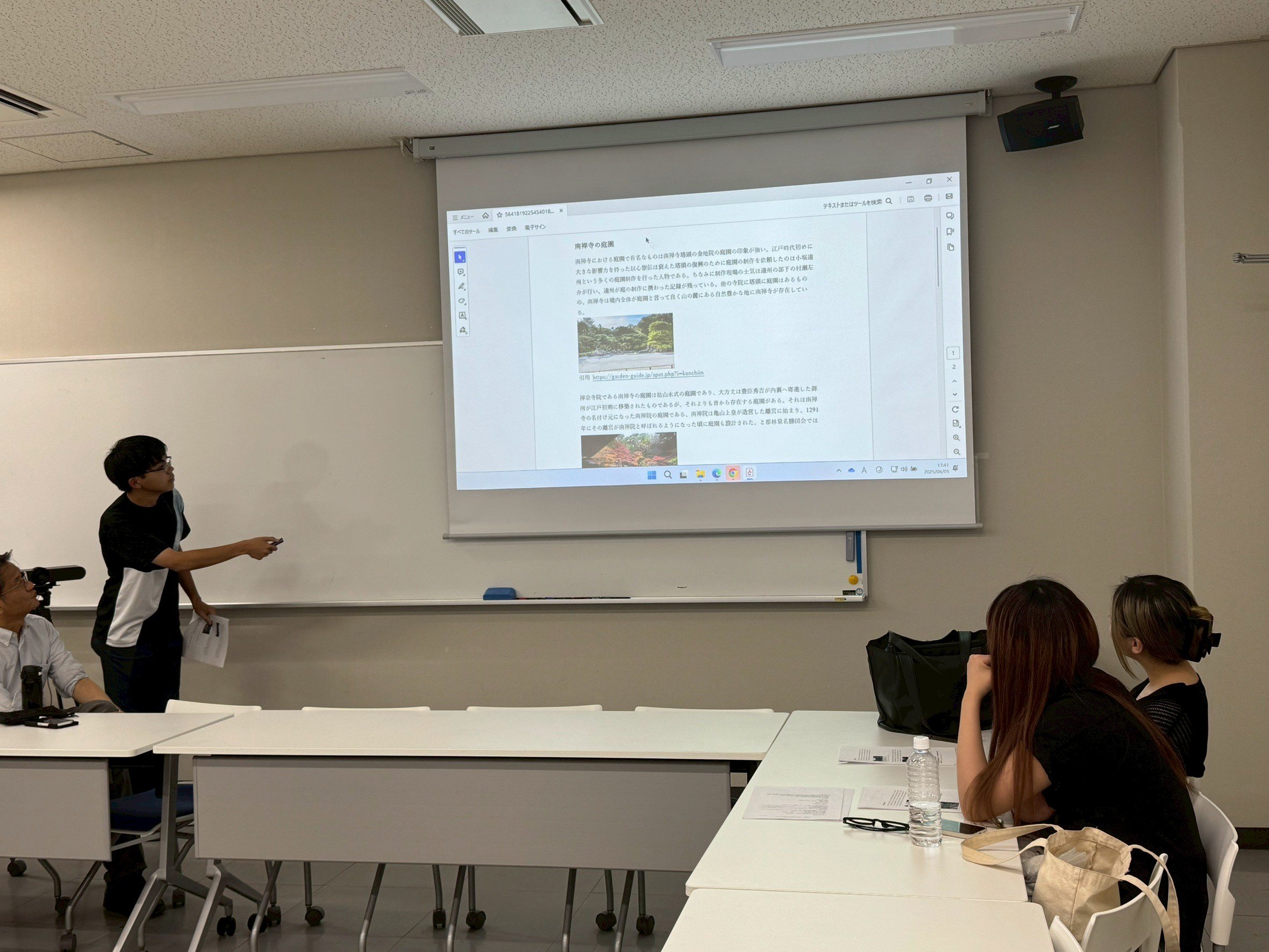
フィールドワーク当日は、平安神宮南の大鳥居に集合し、境内へ向かいました。平安神宮は1895年に創建された神社で、桓武天皇および孝明天皇を祭神としています。殿舎は平安宮の大極殿・朝堂院を縮小復元する形で構成されており、南正門は平安宮の応天門、拝殿は大極殿にあたります。現在「平安神宮百三十年祭」の準備工事が進められているため、拝殿外観の一部は見学できませんでしたが、学生の解説をもとに「右近の橘」「左近の桜」など境内の細部について考察を深めました。

平安神宮の殿舎の背後には、東西に広がる広大な神苑が営まれています。一行は苑内西部から北部、東部へと回遊し、植栽や導水・排水など園池の基本的要素を確認しました。
平安神宮を後にした一行は、神宮の北方に位置する丸太町通沿いの岡崎神社へ向かいました。岡崎神社は、平安時代に創建された東光寺の鎮守神に由来する神社で、氏神の使いとして兎を祀っています。境内各所には兎の像が置かれており、兎をかたどったお守りなども販売されています。学生の解説を手がかりに、これらの慣行がいつ、どのような形で始まったのかについて議論しました。
その後、一行は永観堂門前を経由し、南禅寺へ向かいました。南禅寺では、三門や法堂などの建築的特徴を観察し、方丈では休憩をとりながら桃山・寛永文化を代表する庭園や障壁画を鑑賞しました。
南禅寺の境内には、琵琶湖疏水が南から北へ迂回するように流れています。一行は水路閣からインクラインへと疏水に沿って南下し、最後にインクライン下を通る「ねじりまんぽ」(れんがが渦巻状に積まれた歩行者用トンネル)を観察して踏査を終えました。
当日は晴天に恵まれ、地域の歴史や景観を総合的に探究する、充実した学外授業となりました。





