
2025年7月10日(木)、「平和構築論Ⅰ」(担当:クロス 京子教授)において、株式会社日建 代表取締役社長の雨宮 誠氏をお招きし、講演会「地雷のない世界を目指して-モノづくりを通じた国際貢献-」を実施しました。地雷除去機の開発による国際貢献のあり方と民間企業による国際協力についてお話いただきました。
(学生ライター 国際関係学部3年次 島袋 梨央)
雨宮誠氏は、お父様が創設された建設機械の製造・整備を行う株式会社日建の跡を継がれました。学生時代は、国際貢献についての思いを持っていたものの、中々自分を見つけることができずにいたそうです。現在では、「モノづくりを通して国際貢献を行うことでその大きな思いが形になっている」と話されました。
講演会の初めに、現在世界にはどれくらい地雷の使用されているのか解説がありました。今もなお、世界では120カ国に約1億個の地雷が埋設されており、現在進行中のロシア・ウクライナ戦争においても使用されるなど、その数は増加し続けているそうです。対人地雷はあくまで手足を失わせるなどの負傷を目的としたものであり、多くの人々が地雷による障がいを負っています。また、不発弾や地雷の存在は紛争後の復興に時間がかかり、資源をより多く失わせることに繋がります。紛争後も残存し、民間人に無差別に被害を与えることから地雷は“悪魔の兵器”と呼ばれています。
カンボジアでは、ポルポト政権による大虐殺後の約20年間に渡る内戦で地雷が多く撒かれました。内戦終結後、都市部から貧しい農村部へ人々が移動し、地雷の被害にあったそうです。1995年、内戦が終了したカンボジアで、雨宮氏のお父様が幼い娘を連れたおばあさんに1ドル札を渡され、「日本人なんでしょ、あなたたちの技術で私たちを助けて」と言われた経験が地雷除去事業を起こすきっかけとなったそうです。そこから開発がスタートし、2000年に除去機の第一号が誕生しました。
東南アジアやアフリカなど各国における活動やご経験を聞くなかで、地雷による子どもへの被害が特に印象に残りました。子どもたちは不発弾や対人地雷をおもちゃと間違えて触れることが多く、大人とは違い、爆発した際に起こる爆風と熱で亡くなる事故が多発しています。実際に水を汲みに行った子どもが地雷を踏み、亡くなるという事例が起きているそうです。子どもの85%は病院に行く前に亡くなり、生存した場合でも手足の切断を伴うことが多いため、成長過程で伸びた骨を削り取る手術を繰り返さなければいけません。

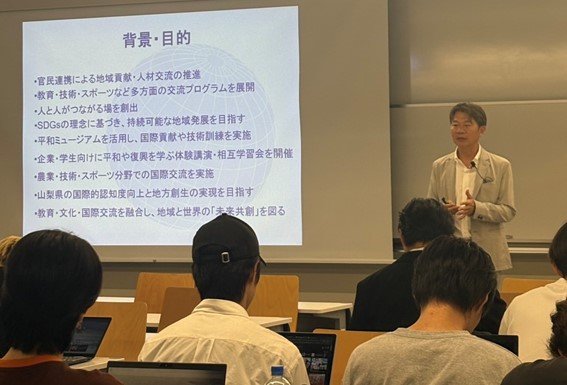
日建は営利団体であり、中小企業であるからこそ、地雷除去機の開発・製造に柔軟に取り組めると話されました。自分たちの手で技術指導を行うため、「現地に足を運び、心を通わせるところからがスタートだ」と述べられました。つまり、現地で行う事業において「この人たちがなにを求めているのか」と、人々に寄り添うということを一番大切にしているため、支援を必要とする人々の声を聞かずに自分たちの思いを押し付ける事業を行ってはいけないということです。そのため地雷除去に関する技術指導だけでなく、豊かで平和な大地の復興のために啓蒙活動も共に行ってこられました。中でも地雷原付近にある「危ない」という文字が読めない子どもが多いというエピソードが印象的でした。「一つでも地雷があれば、そこは“死んでいる土地”である」と述べられ、子どもたちに除去活動や仕掛け爆弾の爆発の様子を見てもらうことで、地雷の恐ろしさや地雷原に入ることの危険性を伝えていらっしゃいます。実際にその様子を見学した子どもたちからは「怖い」「もう地雷原に入りたくない」といった声があがったそうです。また日建の開発した地雷除去機の後ろには鋤がついており、地雷の除去を行うと同時に土地を耕す役目を果たしています。「カンボジアはもともと実り豊かな土地だったので、現地の人々が自らの手で豊かさを取り返すための手助けを行っている」と述べられました。
前社長である雨宮氏のお父様は大変子ども好きな方だそうです。そのため、子どもたちのためにサッカーなどのスポーツを通した支援を行うなど、貧困や人身売買といった犯罪に巻き込まれやすい子どもたちに教育やスポーツの機会を与える事業にも力を入れてこられました。
雨宮氏は講演会の終盤に、ご自身が大切にされている“人を思いやる心”についてお話しされました。「誰かの未来のために、そして人々がのびのびと暮らすための平和へ貢献には、特別な才能はいらない。様々なことに関心を持ち、何か一つの分野で良いのでコツコツと努力すること、そのうえでその結果が自分自身の強みになるはず。自分の強みを早く見つけた人は、他者よりも一歩早く成功できるのではないか。」と述べられました。
講演会の最後には質疑応答が行われました。学生からは「地雷除去の機械があるのにも関わらず、今でも除去を人の手によって行われているのはどうしてか」と質問がありました。「地雷を機械で除去することは本来の方法ではない。機械で地雷を除去した際に爆発すると、その破片などが周りに飛び散ってしまう。農地復興のことを考えると地雷を爆発させたくない。機械で草や表面を綺麗にして、そこに人が入って地雷の探知を行い、地雷を見つけたら人の手で取り除くことが本来の地雷除去の方法だ。地雷の数が多い地雷原の場合は、人命を考えて機械でまとめて地雷除去する」と雨宮氏は答えられました。


地雷が多く埋まる地域はアジアやアフリカといった発展途上国で、私たちが住む日本と地雷を結び付けて考える機会というのは、そう多くありません。しかし、平和を祈る気持ちや誰かを思う気持ちは世界共通のものであると思います。実際に誰かを思う気持ちから、“地雷除去”という事業を雨宮氏のお父様が始められ、雨宮氏が引き継がれたことで、紛争後の現場に生きる人々の平和に繋がっています。地雷を除去することで実り豊かな大地に復興させ、国家の礎を築くという平和への取り組みや思いを伺い、雨宮氏の「人に寄り添う」姿勢に感銘を受けました。人と支え合って生きている私たちにとって、平和のために何が出来るのか、何から始めることが出来るのかということを改めて考える講演会になりました。




