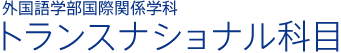

トランスナショナル科目とは、人権や環境といった国家だけでなく企業や個人が連携して解決を図るべき問題を学ぶ科目です。
従来の学問でも、トランスナショナルな事柄は将来の重要問題として一部で取り上げられることはありました。しかし、21世紀を迎えた今、より活発な人口の移動などに代表されるグローバル化が進み、国境を超えた人権の問題や安全の問題を、正面から取り上げる必要が出てきました。特に環境問題などは地球温暖化や異常気象など、みなさんも肌で感じているような切迫した事態を迎えています。そこで、地球規模の新しい問題をいくつかの学問の一部として扱うだけでは不十分であり、様々な分野の学問が問題の取り組みにどのように貢献できるかが重要だと考えられるようになりました。こうして、グローバルな場の中での問題への取り組みを考えるトランスナショナルな学問が発展してきたのです。
「国際社会論」を中心に、環境、NGO、メディア、ジェンダーなどを扱うトランスナショナル科目はこのような時代の要請に対応する科目なのです。

国際社会が抱えている問題、課題は「国家」という枠組みを超えて多様化が進んでいます。例えば、パレスチナ問題を考えてみましょう。「パレスチナ人」は独立を目指していますが、まだ国籍を持たず、多くが難民として暮らしています。政府を持たないパレスチナ人のこれまでの生活を支えてきたのが、国連のUNRWAという国際機関でした。また、UNRWAの活動と協力する多くのNGOやNPOがあり、これらの組織なしには、パレスチナ難民の保護や人権の擁護はおぼつかなかったでしょう。
パレスチナ問題の解決をめぐる中東和平においては、近年、アメリカなど大国の影響力のみが注目されます。もちろん、大国の役割は和平推進に必要ですが、これまで国連や各種のNGOが見落とされがちな問題に注目し、継続的に対応し続けてきたことが、和平の重要な土台を築いたことは忘れてはならないでしょう。トランスナショナル科目は、これまでの国家中心の学問だけでは十分に理解できない問題を正面から取り上げます。
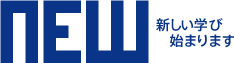
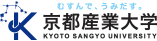
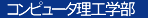
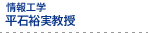
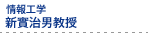


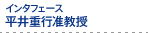
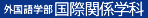

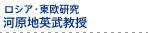
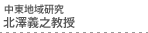
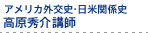
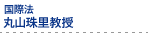

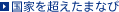
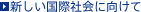

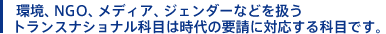




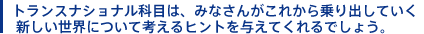
 これまで国際社会においては、国家が重要な行為者として中心的役割を果たし、それが国際社会の全てを決めるものと捉えられてきました。しかし国際社会の中で、変化する現実に対応し、或いは現実を変えてきたのがNGOやNPOであり、EUなどの地域機構、多国籍企業、移民・難民たちなどです。現在は、国家や新たな国家以外の主体がグローバルな変化にどう向き合っていくべきかを考える時期にさしかかっています。トランスナショナル科目は、みなさんがこれから乗り出していく新しい世界について考えるヒントを与えてくれるでしょう。
これまで国際社会においては、国家が重要な行為者として中心的役割を果たし、それが国際社会の全てを決めるものと捉えられてきました。しかし国際社会の中で、変化する現実に対応し、或いは現実を変えてきたのがNGOやNPOであり、EUなどの地域機構、多国籍企業、移民・難民たちなどです。現在は、国家や新たな国家以外の主体がグローバルな変化にどう向き合っていくべきかを考える時期にさしかかっています。トランスナショナル科目は、みなさんがこれから乗り出していく新しい世界について考えるヒントを与えてくれるでしょう。
